今日、2月29日(水)早暁からの雪は、わが所沢市でも久しぶりに10㎝を超える
積雪となりました。
朝8時50分頃、2階から東方を見たところ。わが家のそばを走る西武鉄道池袋線の
線路周辺です。


モノクロ写真のような風景の中に、ポツンと点る信号機のランプ。


この頃が、降雪のピークだったようです。

朝食後、わが家の玄関先と駐車場、そして西に50mくらい伸びている私道の雪かき
をして、とりあえず人が通れるくらいの歩き幅を確保しました。
この後は、正午近くわが家の庭先などに積もった雪の様子。


今年は実るでしょうか、柿の木です。

昨年暮れ、連れ合いが植え替えをしたニホンサクラソウの鉢は、雪帽子の下に。

西隣、Tさんの庭のアメリカハナミズキ?


南のWさんと、わが家の自動車の屋根。

物差しで測った訳ではありませんが、積雪量はおよそ12~15㎝近く、日本海側
の雪とは比べものになりませんが、首都圏ではこれでも大雪なのです。

にほんブログ村
積雪となりました。
朝8時50分頃、2階から東方を見たところ。わが家のそばを走る西武鉄道池袋線の
線路周辺です。


モノクロ写真のような風景の中に、ポツンと点る信号機のランプ。


この頃が、降雪のピークだったようです。

朝食後、わが家の玄関先と駐車場、そして西に50mくらい伸びている私道の雪かき
をして、とりあえず人が通れるくらいの歩き幅を確保しました。
この後は、正午近くわが家の庭先などに積もった雪の様子。


今年は実るでしょうか、柿の木です。

昨年暮れ、連れ合いが植え替えをしたニホンサクラソウの鉢は、雪帽子の下に。

西隣、Tさんの庭のアメリカハナミズキ?


南のWさんと、わが家の自動車の屋根。

物差しで測った訳ではありませんが、積雪量はおよそ12~15㎝近く、日本海側
の雪とは比べものになりませんが、首都圏ではこれでも大雪なのです。
にほんブログ村

























































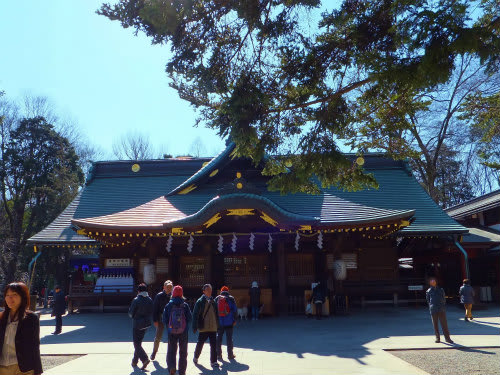























































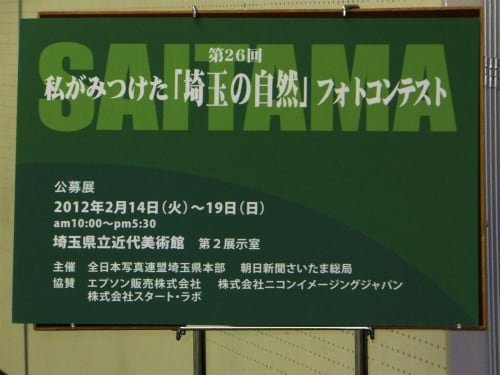


































 。
。




























