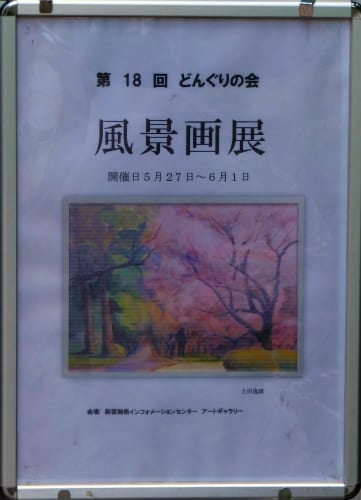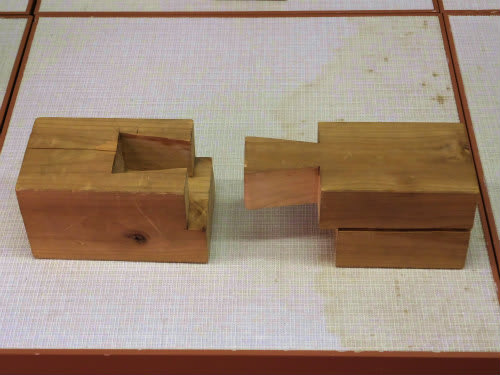2014年5月28日(水)
新宿御苑の初夏の見どころといえば、何といてもバラ花壇に咲き競うバラの花でしょう。

何度か新宿御苑に出かけた中で、今年はバラの最盛期に観賞することが出来ました。



どの花も、ちょうど見ごろです。




ひとつひとつに花の名前があるようですが、それをいちいちメモする間もなく、シャッタ
ーを押し続けます。



斑(ふ)入りの花も。




白い花でも少しずつ違う彩り。




自然ならではのあざやかな彩りの数々。






花壇に沿って少しずつ移動しました。




新宿副都心のビル群が間近に…





ほぼ一巡して、バラ花壇を離れることにしました。
御苑の入口にあったリーフレット「新宿御苑のみどころ 初夏」によれば、新宿御苑のバ
ラは、6月いっぱい見られそうです。
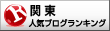 関東地方 ブログランキングへ
関東地方 ブログランキングへ

にほんブログ村
新宿御苑の初夏の見どころといえば、何といてもバラ花壇に咲き競うバラの花でしょう。

何度か新宿御苑に出かけた中で、今年はバラの最盛期に観賞することが出来ました。



どの花も、ちょうど見ごろです。




ひとつひとつに花の名前があるようですが、それをいちいちメモする間もなく、シャッタ
ーを押し続けます。



斑(ふ)入りの花も。




白い花でも少しずつ違う彩り。




自然ならではのあざやかな彩りの数々。






花壇に沿って少しずつ移動しました。




新宿副都心のビル群が間近に…





ほぼ一巡して、バラ花壇を離れることにしました。
御苑の入口にあったリーフレット「新宿御苑のみどころ 初夏」によれば、新宿御苑のバ
ラは、6月いっぱい見られそうです。
にほんブログ村