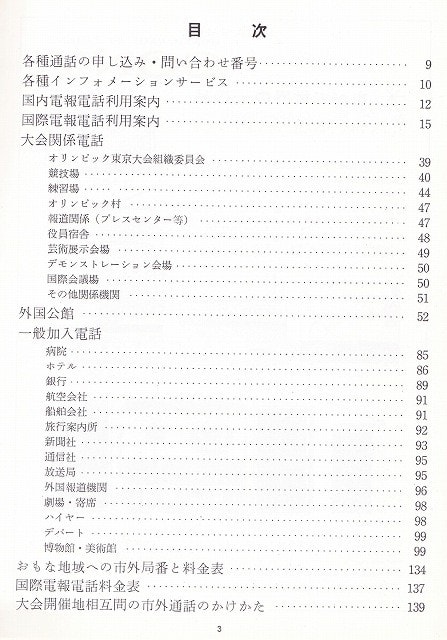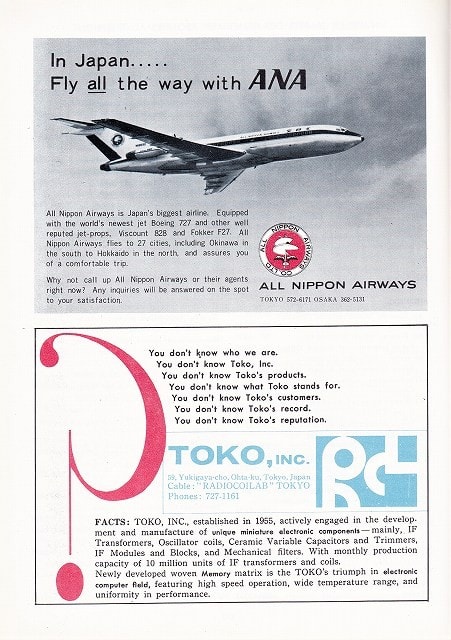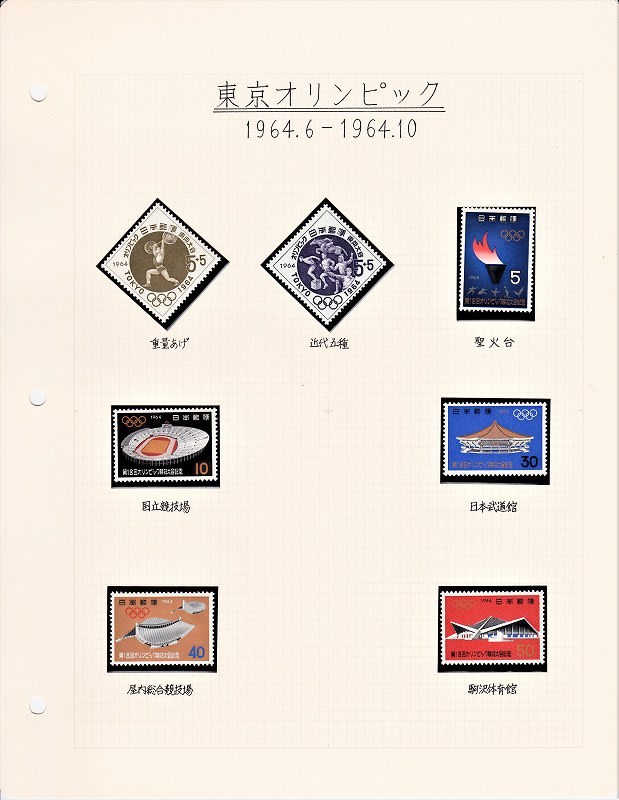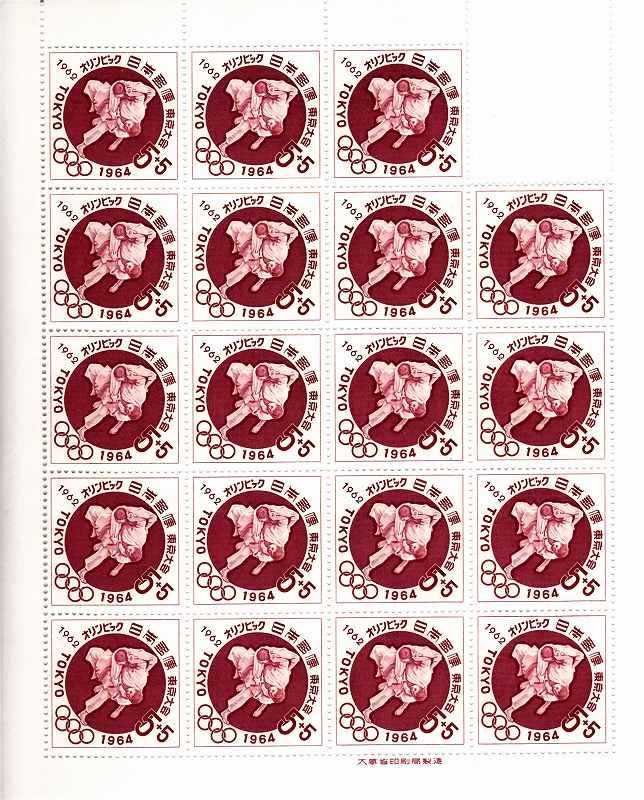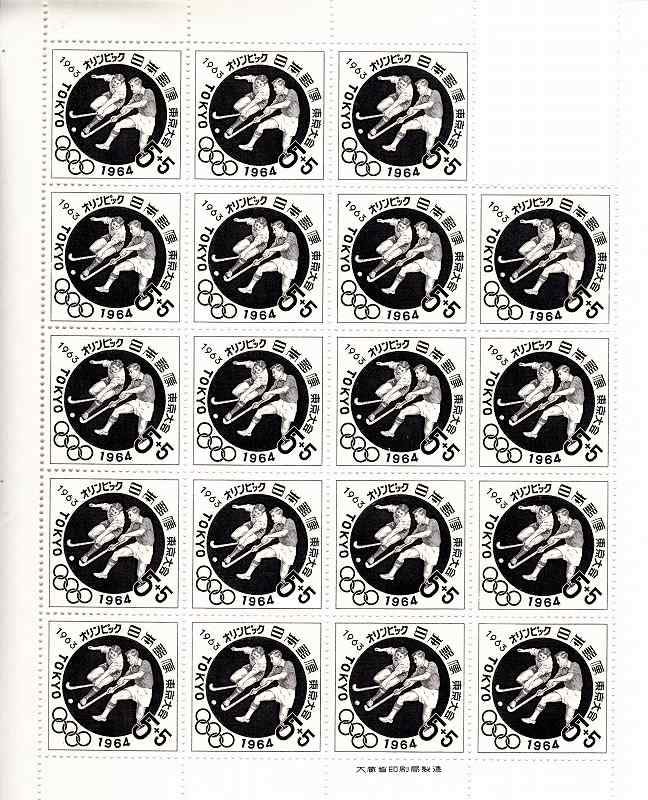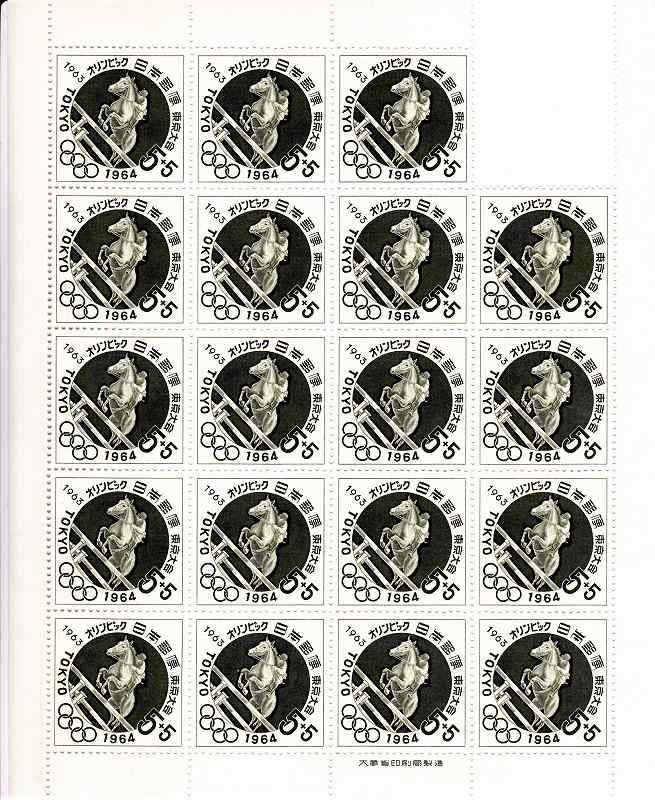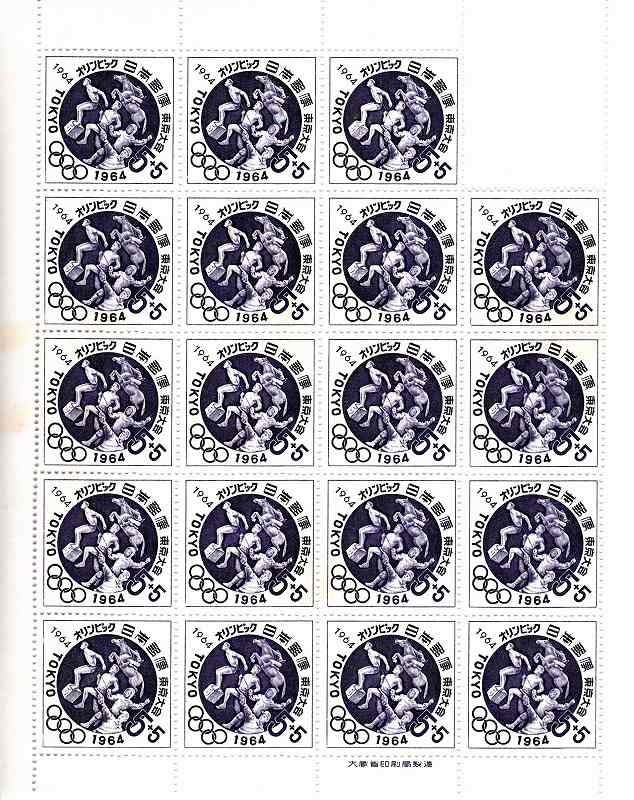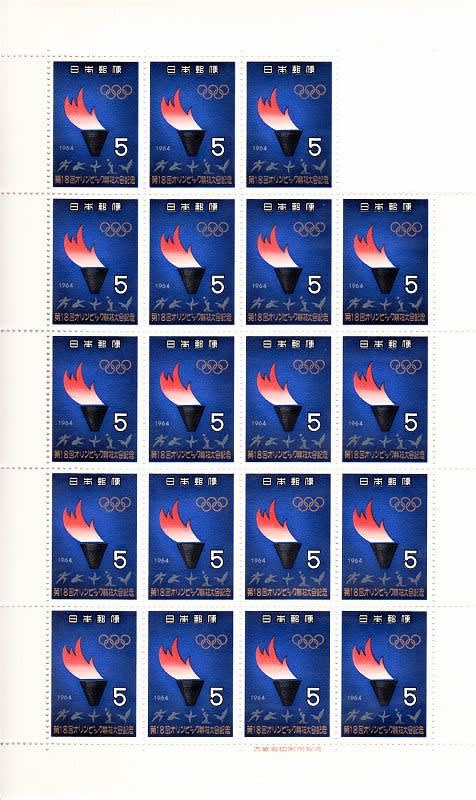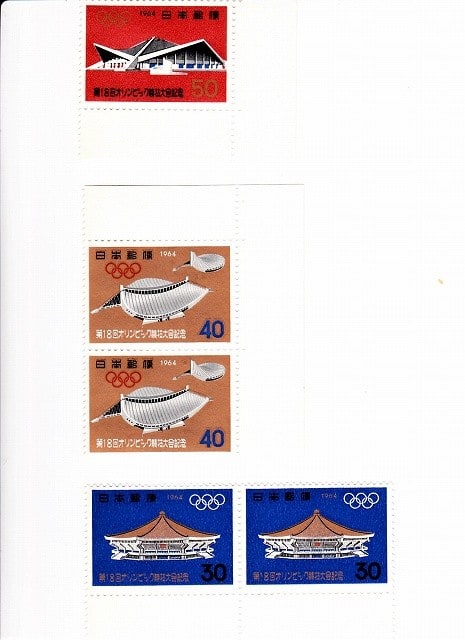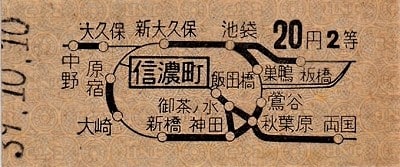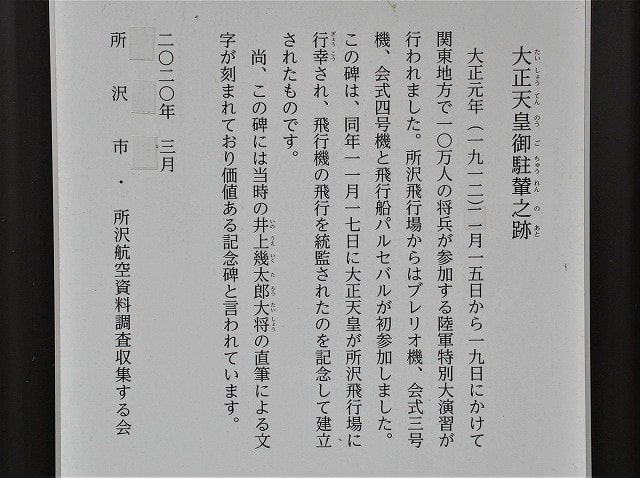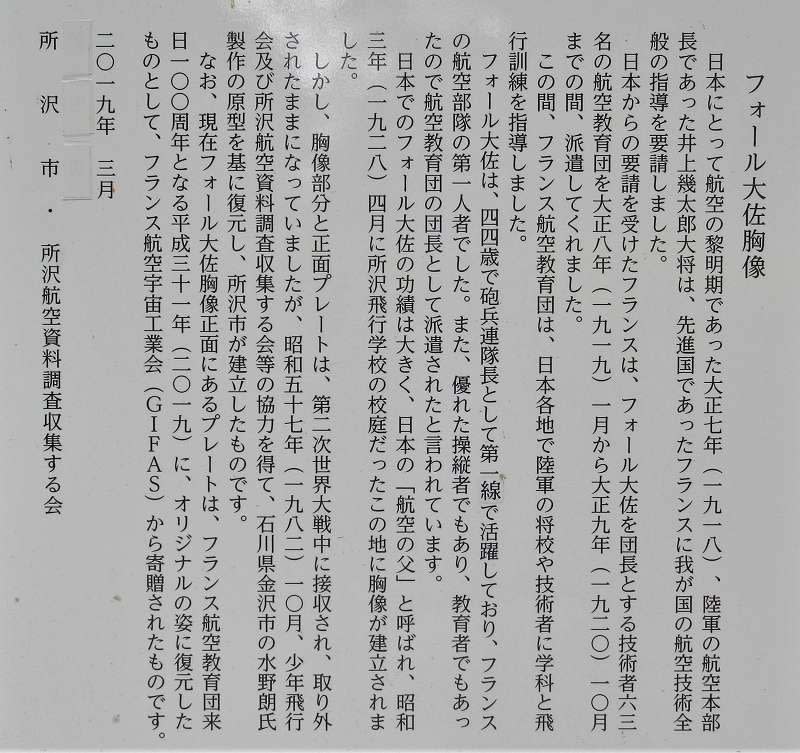2020年10月29日(木)
さわやかな快晴になったので、8月28日(金)以来約2か月ぶりに電車に乗り、市外
へのウオーキングに出かけた。
市外といってもわが家からは都県境を越えてわずか、電車もひと駅ずつ3回乗り換えて
4駅目の西武拝島線東大和市(ひがしやまとし)駅に9時39分に下車した。

駅の南側に出ると丸い郵便ポストがある。駅名は東大和市だが東大和市は線路の北側の
みで、南側一帯は小平市である。小平市内には丸形のポストが37あって都内では1位と
か。ちなみに23区内にはたったの5つだけという。

ポストの前から電車に平行して南西へと緑陰の続く野火止(のびどめ)用水上散策路を
進む。下を野火止用水が流れているのだが、暗渠(あんきょ)になっているのでその様子
は分からない。

散策路が右カーブすると、線路の北側に西武拝島線玉川上水車両基地の車両が見える。

散策路にはカシの実だろうか、どんぐりがいっぱい落ちていた。


野火止用水が玉川上水に合した都水道局の小平監視所の施設の横を進み、まもなく隣の
玉川上水駅前へ。


南に延びる多摩都市モノレールの高架の手前から折り返し、玉川用水右岸沿いの遊歩道
に回る。

都水道局小平監視所の先で玉川上水が斜面から流れ出るところに下ると、清流復活の碑
がある。この場所は、小平市内で玉川上水の水辺に下りられる唯一の場所だという。



さらに右岸の遊歩道を下流に向かう。南側の新興住宅地の間に畑が何か所か残っていた。



次の橋、西中島橋で玉川上水の流れを見下ろし、左岸に渡って少し戻ると「こもれびの
足湯」があるが、木曜の今日は定休日だった。


こもれびの足湯

西中島橋から、右岸より幅広い左岸の遊歩道を少しで、小平市内の玉川上水の分水のひ
とつ、新堀(しんぼり)用水が流れ出す胎内掘(たいないほり・ほっこぬき)と呼ばれる
ところの、昨年復元された抗口(分水口)があった。

新堀用水は、この先しばらくは玉川上水左岸に沿って小さい流れが続いている。

近くには「国指定史跡 玉川上水」の説明パネルがあり、「玉川上水は羽村取水口から
四谷大木戸までの43㎞にわたる水路で、承応3(1654)年仁完成し、多摩川の水が
江戸市中の広い範囲に供給されて江戸が大きく発展したこと。
その後、明治31(1898)年に完成した淀橋浄水場への水路として昭和40
(1965)年に廃止されるまで利用されていた」ことなどが記されていた。
間もなく、東大和市駅横から南下してきた道路が交差する都道の小川橋へ。橋の北西側
に石橋供養塔が立っているが、そばに金網があって正面からは撮れず、右側のみを撮る。


小川橋を渡って右岸に回り、再び右岸沿いの遊歩道を進む。南側は住宅地の横を進んで
広葉樹林に囲まれた上水新町地域センターでトイレを借りる。樹林内にリンドウのような
花が何株か咲いていた。


その先にも保存樹林になっているエリアがある。


近くのくぬぎ橋を渡って流れを見下ろす。


再度左岸の遊歩道に回るとすぐに百石橋(ひゃっこくばし)。橋を渡ってさらに左岸遊
歩道を少しで「きつねっぱら公園」と呼ぶ小公園があった。

隣接する大けやき通公園も小さな緑地。ここで玉川上水と分かれ、丸木造りのトイレの
横から北に延びる大けやき通に入る。

通の東側は武蔵野美術大の敷地、その一隅の学生寮らしい建物の裏手に柿がたくん実を
つけていた。

畑の中を平行する2本の通を過ぎて青梅街道が近づいたところに、「竹内家のケヤキ」
と呼ぶ大ケヤキが立っていた。

小平を代表する樹木であり、竹内家がここに移り住んだ寛文年間(1661~73)に
台風に備えて植えた樹木の中の1本とのこと。樹齢300年以上、高さ35m、目通り周
囲6.5m、枝張り面積400㎡あり、市内最大の巨木だという。

すぐ北側で小川橋からの通と青梅街道街道とが合する小平上宿交差点に出た。青梅街道
を東に少しで小川寺(しょうせんじ)前へ。
小川寺は、明暦2(1656)年に小川九郎兵衛(おがわくろべえ)が小川村の開発を
始めたとき、江戸市ヶ谷河田町の月桂寺住職の雪山碩林大禅師(せつざんせきりんだいぜ
んじ)を勧請(かんじょう)して開山して建立した臨済宗円覚寺派の寺院という。

青梅街道に面して北向のりっぱな仁王門があり、さらに中門をくぐると右手に本堂が東
向きに建っている。


広い境内にはりっぱな植栽がよく整えられ、多くの石像や庭石などが配されている。


本堂に参拝後、左手の門を入って本堂背後に回ると、さらに良く整えられた庭園が広が
り、モミジやススキ、多くの庭石や灯ろう、石像などがある。



それらの間を一巡する遊歩道が巡らされ、玉川上水の分流らしい流れもある。


境内東南側には、その流れを生かした趣ある池も設けられ、そばのジュウガツザクラが
咲き出していた。

池の前から南側に出ると広大の墓地になっていて、手前南西側に小川村の開拓と馬継場
(うまつぎば)基礎を確立したという小川九郎兵衛墓がある。


中門の東側にある鐘楼も確認して小川寺を後にした。

そばの手押し信号で青梅街道の北側に回り、すぐ西側のうっそうとした鎮守の森に祭ら
れた小平神明宮に入る。

小川神明宮は、明暦2(1656)年、「逃げ水の里」といわれた不住の地に、開発の
ため移住した人々の守護神として阿豆佐味天神社(西多摩郡瑞穂町)の別宮から選祀し鎮
座されたとか。

鳥居を入ると、100m余りの長い参道は武蔵野特有のケヤキ、エノキ、ムクなどの広
葉樹におおわれ、何本かのケヤキが市の保存樹木に指定されていた。

正面の本堂に参拝してから境内を一巡する。右手には八幡神社、八雲神社、春日神社を
祀る東殿があり、他に幾つもの建物がある。

拝殿の西側には小平市保存樹木の大イチョウがまだ緑いっぱいの葉を広げ、その下に神
米として奉納されたらしいワラがはさ木に干されていた。

参道の途中には、水の恵みに感謝する「御井神 水波能売神」の額のかかる小さい祠が
祀られ、傍らから地下125mの水脈からくみあげた清水が流れ出ていた。

境内の東側、園児の歓声の絶えない小平神明幼稚園を見ながらが参道を鳥居際まで戻る
と、りっぱな小川村開拓碑が立っているが碑文は判読しがたい。

鳥居際には日露戦役の戦歿者慰霊顕彰と従軍者顕彰という戦捷記念碑があり、碑文は乃
木希典大将と思われる希典書と刻まれている。

青梅街道を小平上宿交差点まで戻り、さらに西進して小平消防署出張所交差点を右折し
て大ケヤキの横から北に延びてきたけやき通りに入る。西武新宿線の踏切を越えて栄町の
北側で野火止用水の橋際へ。

橋の北東側には用水工夫像(ようすいこうふぞう)があり、通りの西側から流れを見下
ろし野火止用水左岸の遊歩道に入る。

こちらも玉川上水の遊歩道同様、落葉広葉樹林下に歩きやすい土道になっている。


少し先で流れは左折して南西へと向きを変えて暗きょとなり、暗きょの上を人工のせせ
らぎが設けられ、その一部にホタルを飼育するエリアもあった。

500m余りで西武新宿線の高架下をくぐって青梅橋際へ。青梅橋は野火止用水を青梅
街道が横断するために架けられたもので、昭和38(1963)年に暗渠になったという。
スタートしてゴールの東大和市駅はすぐ先、当時の駅名は青梅橋駅だった。13時39
分に着いた。

駅の北側、青梅街道沿いの食堂で昼食をして、14時10分発上り電車に乗る。
(天気 快晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 立川、歩行地 小平市(大半が立川
市と東大和市との市境)、歩数 16,100)
 アウトドアランキング
アウトドアランキング

にほんブログ村
さわやかな快晴になったので、8月28日(金)以来約2か月ぶりに電車に乗り、市外
へのウオーキングに出かけた。
市外といってもわが家からは都県境を越えてわずか、電車もひと駅ずつ3回乗り換えて
4駅目の西武拝島線東大和市(ひがしやまとし)駅に9時39分に下車した。

駅の南側に出ると丸い郵便ポストがある。駅名は東大和市だが東大和市は線路の北側の
みで、南側一帯は小平市である。小平市内には丸形のポストが37あって都内では1位と
か。ちなみに23区内にはたったの5つだけという。

ポストの前から電車に平行して南西へと緑陰の続く野火止(のびどめ)用水上散策路を
進む。下を野火止用水が流れているのだが、暗渠(あんきょ)になっているのでその様子
は分からない。

散策路が右カーブすると、線路の北側に西武拝島線玉川上水車両基地の車両が見える。

散策路にはカシの実だろうか、どんぐりがいっぱい落ちていた。


野火止用水が玉川上水に合した都水道局の小平監視所の施設の横を進み、まもなく隣の
玉川上水駅前へ。


南に延びる多摩都市モノレールの高架の手前から折り返し、玉川用水右岸沿いの遊歩道
に回る。

都水道局小平監視所の先で玉川上水が斜面から流れ出るところに下ると、清流復活の碑
がある。この場所は、小平市内で玉川上水の水辺に下りられる唯一の場所だという。



さらに右岸の遊歩道を下流に向かう。南側の新興住宅地の間に畑が何か所か残っていた。



次の橋、西中島橋で玉川上水の流れを見下ろし、左岸に渡って少し戻ると「こもれびの
足湯」があるが、木曜の今日は定休日だった。


こもれびの足湯

西中島橋から、右岸より幅広い左岸の遊歩道を少しで、小平市内の玉川上水の分水のひ
とつ、新堀(しんぼり)用水が流れ出す胎内掘(たいないほり・ほっこぬき)と呼ばれる
ところの、昨年復元された抗口(分水口)があった。

新堀用水は、この先しばらくは玉川上水左岸に沿って小さい流れが続いている。

近くには「国指定史跡 玉川上水」の説明パネルがあり、「玉川上水は羽村取水口から
四谷大木戸までの43㎞にわたる水路で、承応3(1654)年仁完成し、多摩川の水が
江戸市中の広い範囲に供給されて江戸が大きく発展したこと。
その後、明治31(1898)年に完成した淀橋浄水場への水路として昭和40
(1965)年に廃止されるまで利用されていた」ことなどが記されていた。
間もなく、東大和市駅横から南下してきた道路が交差する都道の小川橋へ。橋の北西側
に石橋供養塔が立っているが、そばに金網があって正面からは撮れず、右側のみを撮る。


小川橋を渡って右岸に回り、再び右岸沿いの遊歩道を進む。南側は住宅地の横を進んで
広葉樹林に囲まれた上水新町地域センターでトイレを借りる。樹林内にリンドウのような
花が何株か咲いていた。


その先にも保存樹林になっているエリアがある。


近くのくぬぎ橋を渡って流れを見下ろす。


再度左岸の遊歩道に回るとすぐに百石橋(ひゃっこくばし)。橋を渡ってさらに左岸遊
歩道を少しで「きつねっぱら公園」と呼ぶ小公園があった。

隣接する大けやき通公園も小さな緑地。ここで玉川上水と分かれ、丸木造りのトイレの
横から北に延びる大けやき通に入る。

通の東側は武蔵野美術大の敷地、その一隅の学生寮らしい建物の裏手に柿がたくん実を
つけていた。

畑の中を平行する2本の通を過ぎて青梅街道が近づいたところに、「竹内家のケヤキ」
と呼ぶ大ケヤキが立っていた。

小平を代表する樹木であり、竹内家がここに移り住んだ寛文年間(1661~73)に
台風に備えて植えた樹木の中の1本とのこと。樹齢300年以上、高さ35m、目通り周
囲6.5m、枝張り面積400㎡あり、市内最大の巨木だという。

すぐ北側で小川橋からの通と青梅街道街道とが合する小平上宿交差点に出た。青梅街道
を東に少しで小川寺(しょうせんじ)前へ。
小川寺は、明暦2(1656)年に小川九郎兵衛(おがわくろべえ)が小川村の開発を
始めたとき、江戸市ヶ谷河田町の月桂寺住職の雪山碩林大禅師(せつざんせきりんだいぜ
んじ)を勧請(かんじょう)して開山して建立した臨済宗円覚寺派の寺院という。

青梅街道に面して北向のりっぱな仁王門があり、さらに中門をくぐると右手に本堂が東
向きに建っている。


広い境内にはりっぱな植栽がよく整えられ、多くの石像や庭石などが配されている。


本堂に参拝後、左手の門を入って本堂背後に回ると、さらに良く整えられた庭園が広が
り、モミジやススキ、多くの庭石や灯ろう、石像などがある。



それらの間を一巡する遊歩道が巡らされ、玉川上水の分流らしい流れもある。


境内東南側には、その流れを生かした趣ある池も設けられ、そばのジュウガツザクラが
咲き出していた。

池の前から南側に出ると広大の墓地になっていて、手前南西側に小川村の開拓と馬継場
(うまつぎば)基礎を確立したという小川九郎兵衛墓がある。


中門の東側にある鐘楼も確認して小川寺を後にした。

そばの手押し信号で青梅街道の北側に回り、すぐ西側のうっそうとした鎮守の森に祭ら
れた小平神明宮に入る。

小川神明宮は、明暦2(1656)年、「逃げ水の里」といわれた不住の地に、開発の
ため移住した人々の守護神として阿豆佐味天神社(西多摩郡瑞穂町)の別宮から選祀し鎮
座されたとか。

鳥居を入ると、100m余りの長い参道は武蔵野特有のケヤキ、エノキ、ムクなどの広
葉樹におおわれ、何本かのケヤキが市の保存樹木に指定されていた。

正面の本堂に参拝してから境内を一巡する。右手には八幡神社、八雲神社、春日神社を
祀る東殿があり、他に幾つもの建物がある。

拝殿の西側には小平市保存樹木の大イチョウがまだ緑いっぱいの葉を広げ、その下に神
米として奉納されたらしいワラがはさ木に干されていた。

参道の途中には、水の恵みに感謝する「御井神 水波能売神」の額のかかる小さい祠が
祀られ、傍らから地下125mの水脈からくみあげた清水が流れ出ていた。

境内の東側、園児の歓声の絶えない小平神明幼稚園を見ながらが参道を鳥居際まで戻る
と、りっぱな小川村開拓碑が立っているが碑文は判読しがたい。

鳥居際には日露戦役の戦歿者慰霊顕彰と従軍者顕彰という戦捷記念碑があり、碑文は乃
木希典大将と思われる希典書と刻まれている。

青梅街道を小平上宿交差点まで戻り、さらに西進して小平消防署出張所交差点を右折し
て大ケヤキの横から北に延びてきたけやき通りに入る。西武新宿線の踏切を越えて栄町の
北側で野火止用水の橋際へ。

橋の北東側には用水工夫像(ようすいこうふぞう)があり、通りの西側から流れを見下
ろし野火止用水左岸の遊歩道に入る。

こちらも玉川上水の遊歩道同様、落葉広葉樹林下に歩きやすい土道になっている。


少し先で流れは左折して南西へと向きを変えて暗きょとなり、暗きょの上を人工のせせ
らぎが設けられ、その一部にホタルを飼育するエリアもあった。

500m余りで西武新宿線の高架下をくぐって青梅橋際へ。青梅橋は野火止用水を青梅
街道が横断するために架けられたもので、昭和38(1963)年に暗渠になったという。
スタートしてゴールの東大和市駅はすぐ先、当時の駅名は青梅橋駅だった。13時39
分に着いた。

駅の北側、青梅街道沿いの食堂で昼食をして、14時10分発上り電車に乗る。
(天気 快晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 立川、歩行地 小平市(大半が立川
市と東大和市との市境)、歩数 16,100)
にほんブログ村