2010年2月25日(木) 四国遍路前半第7日
=22番平等寺=
6時起床、6時30分に朝食、3人が先発したあとの7時11分に民宿龍山荘
を出る。すぐ先で県道28号に入ると、緩やかな上りとなる。昨夜はひと雨あっ
たようで、道路が濡れていた。
朝から気温が高いので、厚めのシャツは脱いで薄着になる。阿瀬比の交差点
際にあるヘンロ小屋3号阿瀬比を過ぎ、谷間の遍路道へ。

紅梅や白梅が咲き、ミカンが実りウグイスが鳴く、私のお気に入りのところだ。

雨がパラパラしてきたので、ザックカバーをする。
標高200mの大根峠へ向かう杉林の上りとなり、ステップが高めの疑木の段
をひと上り。

下りも結構傾斜があり、折り畳み杖を使った。
杉林を下って行くと、今朝崩落したらしいツバキが倒れて道をふさいでいた。

牛舎の近くに出て里道を進む。
22番平等寺(びようどうじ)の山門前に着いたら雨になったが、すぐに止んだ。
境内には、昨夜同宿の名古屋のNさんが居られたが、間もなく先発する。

本堂にはたくさんの千羽鶴が奉納され、本堂下の斜面にしだれ梅とスイセン
が花を競う。

参拝を終える頃に再び雨となり、ポンチョを被って寺を出た。しかし2㎞も進ま
ぬうちに晴れてきたので脱ぐ。その代わりに南風が強まり、菅笠があおられる。

番外霊場の月夜御水庵(つきよおみずあん)には、樹齢1,000年、高さ31m
という大杉が立ち、お地蔵さん7体が並んでいた。

その先、山間を抜ける1.7㎞ほどの車道はいつも交通量が少ない。今回も1
台に抜かれただけだった。途中に、竹を出荷するために段を設けた竹林が2か
所あった。

国道55号に出て間もなくの鉦打(かねうち)トンネル(301m)は、両側に歩道
があり左側はガードレールもあり安心。

トンネルを出たところに、ヘンロ小屋4号鉦打がある。

今日は距離が短めなのと回り道もわずかなので、初めての番外霊場弥谷(い
やだに)観音に回ることにした。
ヘンロ小屋の手前に少し戻り、福井ダムの橋を渡る。車道を500mほど進ん
で疑木の段を下って斜面をトラバース、夫婦地蔵や笠地蔵の前を通過し、急登
して弥谷観音の下に出た。

そばに広場があり、東屋やトイレ、プレハブ小屋の納経所がある。しかし納経
所は無人だった。
道路の上の段を上がると、国道工事のため近年移転したという弥谷観音の新
しいお堂がある。

そばに、石舟に乗った新しい七福神と、ゆるぎ石という大岩があった。
水が少なく、ダムとはいえない様相のダムの西岸を回って国道55号に戻る。
すぐ近くから細道を下ると、「小野の一里松跡」の説明板が立つ。間もなく県道
25号へ。
今日のコース地図には、昼食を調達出来そうな店の表示がない。運良くそば
に小さな商店があったのでパンを買い、そばの無人小屋↓を借りて昼食代わり
とした。

県道を緩やかに上がり、阿南市から美波町に入ると下り道となる。間もなく、
珍しい「カニに注意」の道路標識があり、6月から9月の月夜に、この地に生息
するアカテガニが、産卵のため道路を横断することがあるという。
そばに、いろいろな名目での記念日に植樹をした一角があった。

県道の気温表示は18度を示し暖かい。美波町側は道路の改修があちこちで
進み、かなり左右に回っていた県道が、何か所か緩やかなカーブになっていた。
JR牟岐(むぎ)線の由岐(ゆき)駅近くの踏切を越え、駅舎のある「ぽっぽマリ
ン」と呼ぶ建物↓に入り、漁具や貝、過去の大地震のことなど、美波町関連の
展示を見る。

県道に戻ってJRのトンネル上を越え、海に向かって下って行くと、海岸のそば
にある今日の宿、民宿明山荘の看板が見えてきた。
宿に入る前に田井ノ浜の海岸をのぞく。3月27日で終わったNHK総合テレビ
朝のドラマ「ウェルかめ」に何度も登場した浜辺である。

14時45分に宿に入り、ひと休みして入浴する。広い風呂からは海も見られ、
湯もぬるめで気持ちよい。今日の宿泊者は私ひとり、館内には「ウェルかめ」の
ポスターも貼ってあった。
【コースタイム】民宿龍山荘7:11ーヘンロ小屋3号阿瀬比7:53ー大根峠8:29ー
22番平等寺9:22~10:00ー月夜御水庵10:45~52ーヘンロ小屋4号鉦打11:41
~52ー弥谷観音12:10~20ー小野の一里塚跡近くの小屋(昼食)12:28~50
ー阿南市・美波町境13:33ーぽっぽマリン(由岐駅)14:12~19ー民宿明山荘
14:45
(天気 晴後曇一時雨、距離 19㎞、歩行地 阿南市、美波町、歩数
37,200、遍路地図 21-1、22-1、22-2図)
=22番平等寺=
6時起床、6時30分に朝食、3人が先発したあとの7時11分に民宿龍山荘
を出る。すぐ先で県道28号に入ると、緩やかな上りとなる。昨夜はひと雨あっ
たようで、道路が濡れていた。
朝から気温が高いので、厚めのシャツは脱いで薄着になる。阿瀬比の交差点
際にあるヘンロ小屋3号阿瀬比を過ぎ、谷間の遍路道へ。

紅梅や白梅が咲き、ミカンが実りウグイスが鳴く、私のお気に入りのところだ。

雨がパラパラしてきたので、ザックカバーをする。
標高200mの大根峠へ向かう杉林の上りとなり、ステップが高めの疑木の段
をひと上り。

下りも結構傾斜があり、折り畳み杖を使った。
杉林を下って行くと、今朝崩落したらしいツバキが倒れて道をふさいでいた。

牛舎の近くに出て里道を進む。
22番平等寺(びようどうじ)の山門前に着いたら雨になったが、すぐに止んだ。
境内には、昨夜同宿の名古屋のNさんが居られたが、間もなく先発する。

本堂にはたくさんの千羽鶴が奉納され、本堂下の斜面にしだれ梅とスイセン
が花を競う。

参拝を終える頃に再び雨となり、ポンチョを被って寺を出た。しかし2㎞も進ま
ぬうちに晴れてきたので脱ぐ。その代わりに南風が強まり、菅笠があおられる。

番外霊場の月夜御水庵(つきよおみずあん)には、樹齢1,000年、高さ31m
という大杉が立ち、お地蔵さん7体が並んでいた。

その先、山間を抜ける1.7㎞ほどの車道はいつも交通量が少ない。今回も1
台に抜かれただけだった。途中に、竹を出荷するために段を設けた竹林が2か
所あった。

国道55号に出て間もなくの鉦打(かねうち)トンネル(301m)は、両側に歩道
があり左側はガードレールもあり安心。

トンネルを出たところに、ヘンロ小屋4号鉦打がある。

今日は距離が短めなのと回り道もわずかなので、初めての番外霊場弥谷(い
やだに)観音に回ることにした。
ヘンロ小屋の手前に少し戻り、福井ダムの橋を渡る。車道を500mほど進ん
で疑木の段を下って斜面をトラバース、夫婦地蔵や笠地蔵の前を通過し、急登
して弥谷観音の下に出た。

そばに広場があり、東屋やトイレ、プレハブ小屋の納経所がある。しかし納経
所は無人だった。
道路の上の段を上がると、国道工事のため近年移転したという弥谷観音の新
しいお堂がある。

そばに、石舟に乗った新しい七福神と、ゆるぎ石という大岩があった。
水が少なく、ダムとはいえない様相のダムの西岸を回って国道55号に戻る。
すぐ近くから細道を下ると、「小野の一里松跡」の説明板が立つ。間もなく県道
25号へ。
今日のコース地図には、昼食を調達出来そうな店の表示がない。運良くそば
に小さな商店があったのでパンを買い、そばの無人小屋↓を借りて昼食代わり
とした。

県道を緩やかに上がり、阿南市から美波町に入ると下り道となる。間もなく、
珍しい「カニに注意」の道路標識があり、6月から9月の月夜に、この地に生息
するアカテガニが、産卵のため道路を横断することがあるという。
そばに、いろいろな名目での記念日に植樹をした一角があった。

県道の気温表示は18度を示し暖かい。美波町側は道路の改修があちこちで
進み、かなり左右に回っていた県道が、何か所か緩やかなカーブになっていた。
JR牟岐(むぎ)線の由岐(ゆき)駅近くの踏切を越え、駅舎のある「ぽっぽマリ
ン」と呼ぶ建物↓に入り、漁具や貝、過去の大地震のことなど、美波町関連の
展示を見る。

県道に戻ってJRのトンネル上を越え、海に向かって下って行くと、海岸のそば
にある今日の宿、民宿明山荘の看板が見えてきた。
宿に入る前に田井ノ浜の海岸をのぞく。3月27日で終わったNHK総合テレビ
朝のドラマ「ウェルかめ」に何度も登場した浜辺である。

14時45分に宿に入り、ひと休みして入浴する。広い風呂からは海も見られ、
湯もぬるめで気持ちよい。今日の宿泊者は私ひとり、館内には「ウェルかめ」の
ポスターも貼ってあった。
【コースタイム】民宿龍山荘7:11ーヘンロ小屋3号阿瀬比7:53ー大根峠8:29ー
22番平等寺9:22~10:00ー月夜御水庵10:45~52ーヘンロ小屋4号鉦打11:41
~52ー弥谷観音12:10~20ー小野の一里塚跡近くの小屋(昼食)12:28~50
ー阿南市・美波町境13:33ーぽっぽマリン(由岐駅)14:12~19ー民宿明山荘
14:45
(天気 晴後曇一時雨、距離 19㎞、歩行地 阿南市、美波町、歩数
37,200、遍路地図 21-1、22-1、22-2図)

















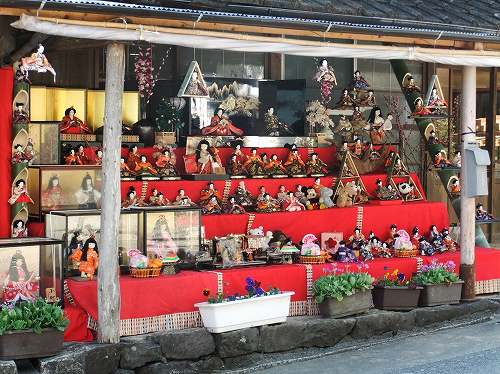




























































































 。
。




