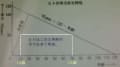これは我家の玄関先数㍍に立つ
Kさんちのクルミの大(中?)木の現在の姿です。

毎年夏には涼しい木陰を提供してくれていたのですが
3~4㎝に育った小さな実を付けていた昨年夏頃から
葉が黄色くなり始めて初秋には全て散り落ちてしまったのです。
周りは実質的に我家の庭として使わせて頂いてはいても
クルミの実は小さいまま収穫して例年の如くKさんちにお届けしましたが
内部の果肉はごく僅かでとても食せなかったと聞きました。
以降ここまで一つも芽が出ず、小枝は簡単にボキッ。。。
根元をよ~く見ると、今まで気付かなかった穴が開いていて
内部は20~30㎝の空洞になっていますので
これが原因で枯れてしまったのかも知れません。

せっかくこんなに大きく育っていて勿体ないとの思いはとても強く
何年か前に別のクルミの伐採木に種を打ち込んで上手く行った
ヒラタケをまた作れないものかとその道に詳しい
友人Tに尋ねると「枯れ木はダメだよ」
キノコは生きていた伐採木に菌を植えるなんてことは
ついぞ知りませんでした。
でも、枯れたことが確認できたのはこの春
芽吹かなかったからなのにそれでも遅いのかなぁ。
まだ切り倒してさえいないし、、、
そんなこんなの思いからキノコ会社にメールで問い合わせてみると
「ヒラタケは菌糸伸長が強いためキノコが出る可能性は高いです」
ただし種を売りたいがための回答かも、とは少し疑いつつも
ダメ元でこの可能性に賭けてみることにしました。

(7年前、別のクルミ伐採木での短木栽培)
そして同時にもう一つ、ガキの頃からの夢だったツリーハウスも
滅多にない機会なので作ってみたくなりました。
そこでその辺りの事情と希望をKさんにお話ししたところ
この木をそっくり譲って頂けることに
頂いた枯れ木なら失敗しても叱られることはないですし
下を農機具置き場にも利用出来ます。



(これらのガーデンハウスを参考に)
さてさて、いかなる首尾になることでしょう
************** タイムスケジュール **************
【ツリーハウス】
1.幹の穴に発砲ウレタン等を注入しこれ以上の拡大を防ぐ
2.枝を落とし秋までに土台(置き場の屋根)を作る
3.来年、上部にハウス部を製作
【ヒラタケ栽培】
1.夏までに枝を落として秋には接種用の太い枝を玉切り
2.年内に植菌(長木&短木)し仮伏せ
3.来年梅雨明け頃を目安に本伏せ
(続く)
2つの新しいカテゴリーとして連載します