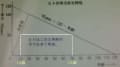現時点で葬祭センターや仏壇店でも、顧客から話題に挙がる割に
墓じまいを実際に進めた話はあまり聞かないそうで
特に田舎であるこの地方での具体例はまだごく少ないと言います。
昔から伝わる伝統的な考え方に基づく祭祀が受け継がれている中で
それに沿わない事をして周囲から後ろ指を指されるのは嫌だし
なかなか親戚の同意が得づらいこともある上、寺との話が面倒臭そうなので
つい現状維持にしてしまうことが多いらしいですのが、その伝統が
将来も維持できるのであれば別に変える必要性など全くありません。
問題なのは実家のように、祭祀継承をすべき子供がいない
そして我家のように、子供が娘のみですでに嫁いでいるうえ遠方に住んでいる等の
物理的理由によって現状を維持するのが困難と推測できる場合
はたまたは経済的、精神的に多くの負担を強いる可能性を懸念する場合は
身内で話し合った上で、現実に目を背けず、出来る範囲の道筋を
付けておいてやらないと結局ツケを回すことになるというものです。

さて実際に墓じまいと改葬に一歩踏み出す時の一番最初の壁は
日頃何かと口喧しかったり、祭祀の際などは必ず采配を振るうような
親戚がいる場合は、この方の同意を得ておかないと
後々揉めて付き合いづらい事態に陥る可能性があることでしょう。
もっとも、終わった後の結果報告だけをするという
強行突破もないわけではありませんが、他人と違って親戚
特に近しい身内とのゴタゴタは、何かと顔を合わせる機会を避けられず
そのたびにお互いが気まずい思いを抱くという精神的負担が大きいので
出来れば避けて円満解決を図る方が良いことは確かです。
冠婚葬祭に関してではなかったにしろ、実父とこの種の争いが元で
長年の確執に陥った私が言うのですから間違いはありません。
親戚の次に、今回のように菩提寺に墓がある場合で
より高いことがあると言われる壁は、例の「埋蔵許可証」に
寺の署名捺印をもらわなければならないことです。
檀家のままでその寺の永代供養墓(碑)に移す場合は別でしょうが
墓じまいの多くは遺骨を取り出し檀家を離れることが前提になるので
いわゆる「離檀料」も原則として必要とされます。
この離檀料、法的根拠はないと法律の先生方は言いますが
それは争いになった場合の話であって、円満に話を進めるためには
必要なお金と考えた方が良いのではないでしょうか。
元を辿れば江戸時代に、参拝者の絶えない大きな有名寺院を除いて
町内の小規模寺に担わせたこの檀家制度、現在の戸籍に当たる
「宗門人別改帳」など重要な役目も果たしたそうですが、一方で
檀家だけの葬祭を生業とするいわゆる「葬式仏教」を根付かせてしまったと
雑学の本で読んだことがあります。
そんな歴史的経緯を加味しつつ、これまで祖先の墓を護っていただいた感謝を
形に表したものとの解釈もあるようですが、そこは人それぞれ
感謝していないから払わないとの理屈も成り立ってしまうのですから
いっそ後腐れないための「手切金」と考えた方が分かり易いかも知れません。
寺から数十、数百万円単位の高額な金額を要求されたなどの情報は
ネットでしか見たことがなく、絶対数が少ないこともあってか
これまで身近で聞いたトラブルめいた話は
永代供養碑を勧められたりしてなかなか離檀に応じてくれず
ずいぶん苦労したという話の1つだけです。
最近ではこうした時代背景から行政書士などのプロも関わってくれますので
そこに依頼する方法もありますが、まだ揉めてもいない初めからではなく
せめて、まずは自分の口から想いを伝えてみたらどうでしょう。
田舎では第三者やプロに頼んで事を進めることを"ケンカ腰"と捉え
ならばこちらも、と構えられて円満な話し合いが
遠のいてしまうケースが無きにしも非ず、だからです。
いずれにしてもまだまだ具体例が少ないですし相手のある話ですから
ケースバイケースになることは止むを得ず、とりあえず話し合いの場を持ち
こちらの意向に対する菩提寺の住職の出方を掴まなければなりません。
我家のように"悩むより産むが易し"に驚くこともあるのですから。
さて、同時に必ず悩むことになるのはお布施額
つまり墓じまいと離檀に伴うその具体的な金額についてです。
まずは会員になっている大手仏壇チェーン店Hではなんと全く情報なし。
別途尋ねた葬祭センターGさんも手持ちの情報はまだ少な過ぎるので
付き合いのある業者仲間など数人に当たってみますとのこと。
そして後日の電話での回答は「上限で10万円程度では」。
同時に教えてくれた、現在の墓に祀られている先祖の遺骨を取り出す際の
「御霊抜き(みたまぬき)」とも呼ばれる「閉眼供養」のお布施額は
上限で5万円程度ではないかとのこと。
この魂を抜く理由は、新たに墓を建立して遺骨を埋葬する際に行った
「開眼供養」によって家の名前などが彫り込まれた一番上の
縦長の竿石(さおいし)に宿った仏様の魂を鎮めて抜き取り
ただの石に戻すためとされています。
かくして、離檀料+閉眼供養代を合わせたお布施の総額は
隣り合っているからと言っても別家の墓なので弟と2家、2基分として
それぞれ15万円ずつと弟と申し合わせていました。
日本仏教協会では、お布施に定価はなく「料」だの「代」も使わない理由は
"対価ではないから"との立場を取っているようですが、理屈は分かるにしても
それが故に毎回、とても悩むことに繋がるわけで、こうした心労を
敢えて民衆に強要する意味をどう説明するのでしょうか。
さて、菩提寺を訪ねて墓じまいと離檀の意向伝える場合
一般的に決定事項として住職に伝えると気分を損ねることが多いので
当初は"相談事"として話を切り出した方が良いとの情報を得ていました。
そこでまずは弟1人が菩提寺を訪ねて実家の事情を伝え、墓じまいをしたいのですが
いかがでしょうか?と、とりあえず疑問符を付けて形ばかりの相談事の体裁を
取って住職の出方を見たのは11月中旬のことでした。
そして特に否定的な方向の話は何もなかったそうなので一日二日置いて
すぐに続いて今度は私が、隣り合う女房家も同時に墓じまいをしたい事情と
その意向を伝えたところ、こちらも全く問題なさそうな感じです。
ただし、どちらも再検討して日を改めて伺うことにしたのは
戦術として相談事の形を取っていたからです。
3~4日後に2人揃って訪問し、離檀としての墓じまいと
改葬の方向で決まった旨を伝えると「すっきりしていいんじゃないの」
当方は間違いなく「すっきり」しますが
寺側の何が「すっきり」するかは敢えて尋ねませんでした。
そしてその場で打合せ通りのお布施額を提示してこれでお願いしたい旨を伝え
21日に閉眼供養を執り行う予定まで話を持って行くことが
出来たのは11月16日のことでした。
これで最大の壁は乗り超えられる見込みが立ったことになり
当日供養が終わった後にお布施を渡し、一番大切な埋蔵証明書の署名捺印を
その場で受け取る段取りまで念のため確認しておきました。
ちなみに閉眼供養さえ終えておくと後は石材店の仕事となり
その費用は、墓地が山の傾斜地にあってどうしても人手に多く頼るため
相見積もりの結果の安い方でも2基合わせて約50万円。

積雪を避けて年内には終わることになっています。
(続く)