京都に「東奥」という姓があって、「あちおく」と読むそうだ。どういうルーツだろうかと検索したら、青森県に結構ある。「そうか、青森か」と思ったら、「とうおう」だった。
青森に東奥があるのは当たり前で、「あちおく」とは関係なさそうだ。
丹波に、東奥(あちおく)という地名があるから、どうもここと関係ありそうだ。
しかし、ここの電話帳には「東奥」さんは無い。東奥さんは全国でも100人もいないらしいが、ここに出自があっても、もう全員、出てしまったのかも知れない。
その経緯は分からないが、この地名の読み方は不思議だ。何かを基点にして東の奥のことだろうが、東を「あち」と読むのはなぜだろう。この謎に詳しい専門家もいるのかも知れないが、その専門家を知らないから、勝手に妄想してみる。
東を意味する日本の言葉には、「ひがし」、「あずま」、「あがり」、「ひで」、「もと」、「こち」など色々あるが、一様に、日が昇り明るくなる方向を表している。「ひがし」も日に向かうの意味から出ている。
しかし、この中で、「こち」だけは性質が違っている。
「東風(こち)ふかばにほひをこせよ梅の花あるじなしとて春なわすれそ」のように、東風のことを「こち」と言うのは、もしかしたら「あち」と関係あるのかも知れない。
「あずま」は日本武尊が妻を偲んで「吾妻はや」と言ったのが語源だとされているが、実はこれは後付けの説明で、もともと、東のことを「あがる」や「あける」のような意味の音で呼んでいたのではなかろうか。例えば出ると明けるを併せた「あずる」のような言葉があったのかも知れない。沖縄では今も東を「あがり」と言う。
超古代は、東を「あずま」、「あがり」のような意味の「あ」音で表現していたのではなかろうか。「アジア」の語源も東を意味する。
もし、東を「あち」と意識していたとすれば、そこから吹いてくる風を「こち」と呼んだのかも知れない。
普通、東風と言えば東から吹いてくる風と決まっているが、裏を返せば西に吹いていく風でもある。
彼方(あち)らから吹いてくる風よりも、此方(こち)らに吹いてくる風と考える方が皮膚感で考えれば先に思いつく。コチに吹いてくる風とはアチから来る東風のこと。
この場合、最大の問題は、彼方(あち)の「あ」が、東を表す「あ」と、どう一体化しているのかということだが、遠くを表す「あち」らは、指さして表現しなければならないほど、注目を喚起する表現だ。驚いた時に出る声も「あ」だ。
朝、太陽が昇り目が覚める。朝の「あ」、明るいの「あ」、開けるの「あ」・・・みな驚きを持って眺めることを「あ」で表現する。
根源的な意識を表現する音として、東も彼方も「あち」だったのかも知れない。











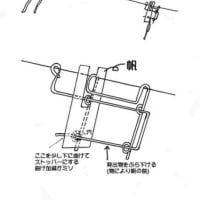






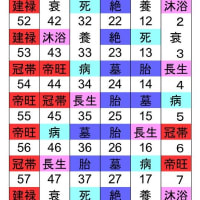
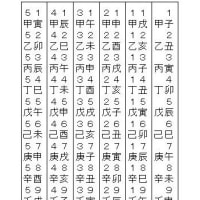
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます