昨日、ポケモンのロゴを確かめようと公式サイトを見たら、当然のことながら『』で『Pokémon GO』『ポケモンGO』と表記してあった。
本や映画のタイトルは『』で囲むことは知ってはいるが、自分ではあまり使わない。
『』は、実際に言葉が音になる「」に対し、音の出ない言葉のイメージがあるため、内心、脳内、心の言葉のような場合に限定したいからだ。
確かに、タイトルも人間が発する音ではないから、『』で囲むのが理に適っているかも知れないが、「ポケモンで遊んだ」と言う場合、実際の会話には「」も『』も無い。音が出るか出ないかの違いしか無いのだから、タイトルも、音で発生されて始めて世に現れる。
どうも、ややこしい話になったが、要は、タイトルを『』で表現すれば、柴犬にリボンを付けたようで、存在感が薄くなるような気がするのだ。
だから、日頃は「」で表現しているが、必要に応じて””や<>、[]を使う。
ただ、『ポケモGO』の場合、公式サイトで『』を使っていれば、それは『』とセットでタイトルだから、そのまま使うしかない。そう考えて、世間の常識にも合致する『』で表記した。
しかし、言葉も文章も、文法に従って話すのは文化的ではないと思う。
一つには、言葉は生き物であり、人によって声色が違うように、人や集団による個性が付け加えられることで、生きた文化を支えている。
例えば、外国人が話す日本語が、どことなく不自然なのは、アクセントの問題だけではない。文法通り型どおりの言葉だからだ。
実際のネイティブが話す母国語は変化に富んでいる。文法はその生きた言葉を解析し、法則性を見つけたものだから生きた言葉ではない。だから、文法通りに話せば、むしろ窮屈で不自然になる。言葉を含め、人間の行動は機械のようなものではない。
カラオケでも、上手い人が歌えば高得点が出ず、どう聞いてもへたくそな歌に100点が出る。
言葉も、少し不自然な遊びがあってこそ楽しめるものだ。聞く側もその遊びの幅を推量しながら、対話するから思考が広がり、そこに文化が生まれる。
20代の頃、酔っ払った50代の雑誌の編集者が、こっちが話す言葉が納得できず、「おかしい?、おかしい?」と言い続けていた。
言葉の定義に関して、「大体そういう意味」と言うところを、「その界隈」と言ったのが、50代の編集者にとっては、初めて聞いた言い回しだったので、「おかしい」と言ったものの、意味的には外れていない。だが何かおかしい。酔っ払ってるから整理が付かない。「おかしい?、おかしい?」
聞き慣れない言葉使いに、編集者としてどうしても引っかかったのだろうが、あらゆる場面でこういうやり取りをしながら、言葉というものは変化していく。多くの作家も造語や独自の言い回しをしている。
どこかで、タイトルに「」を使った人に対し、『』を使うことも知らんのかと、内容よりも文法を攻撃している人がいたが、これこそが、近年の国語教育、受験教育の弊害ではないだろうか。











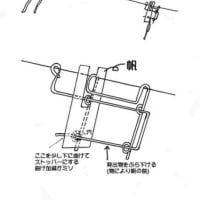






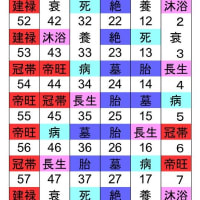
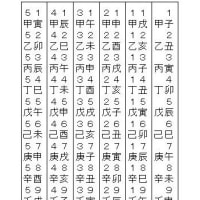
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます