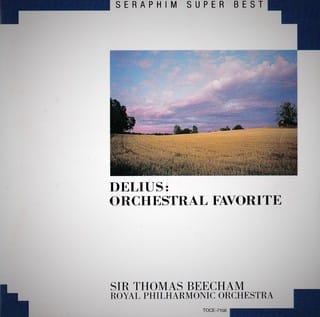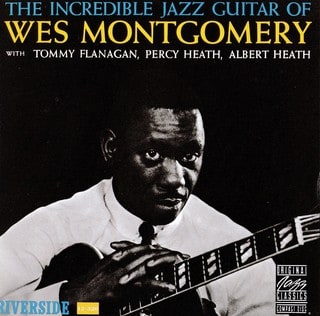グスターヴ・ホルスト(1874-1934)は、イギリスの作曲家。
異国趣味があって、「日本組曲」なる管弦楽も作っている。
さて、有名な組曲「惑星」を久しぶりに聞こうか。
占星術への関心から生まれた作品と言われる。
各楽章に惑星の名前が付いている。
冥王星はまだ見つかっていなかった。
それぞれの星は神と結びつけられている。
これらのことを含んで星の輝き、動きが音楽となっている。
こんな風に言われると、興味が高まるね。
第1楽章 火星:戦争の神
第2楽章 金星:平和の神
第3楽章 水星:翼のある使いの神
第4楽章 木星:快楽の神
第5楽章 土星:老年の神
第6楽章 天王星:魔術の神
第7楽章 海王星:神秘の神
《ロリン・マゼール指揮/フランス国立管弦楽団/CBS》
異国趣味があって、「日本組曲」なる管弦楽も作っている。
さて、有名な組曲「惑星」を久しぶりに聞こうか。
占星術への関心から生まれた作品と言われる。
各楽章に惑星の名前が付いている。
冥王星はまだ見つかっていなかった。
それぞれの星は神と結びつけられている。
これらのことを含んで星の輝き、動きが音楽となっている。
こんな風に言われると、興味が高まるね。
第1楽章 火星:戦争の神
第2楽章 金星:平和の神
第3楽章 水星:翼のある使いの神
第4楽章 木星:快楽の神
第5楽章 土星:老年の神
第6楽章 天王星:魔術の神
第7楽章 海王星:神秘の神
《ロリン・マゼール指揮/フランス国立管弦楽団/CBS》