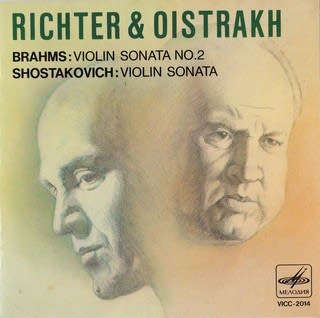ニコロ・パガニーニ(1782-1840)の「ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.6」。
パガニーニの29歳の時、1811年に作曲されている。
悪魔と契約を結んでいるとの噂を呼ぶパガニーニの超絶技巧。
神との契約とならなかったのは、その風貌にもよるのか。
パガニーニ自身も愛奏したという「第1番」を聞く。
第2楽章は、とりわけヴァイオリンが際立つ。
《サルヴァトーレ・アッカルド(ヴァイオリン)/シャルル・デュトワ指揮/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団/PO》
パガニーニの29歳の時、1811年に作曲されている。
悪魔と契約を結んでいるとの噂を呼ぶパガニーニの超絶技巧。
神との契約とならなかったのは、その風貌にもよるのか。
パガニーニ自身も愛奏したという「第1番」を聞く。
第2楽章は、とりわけヴァイオリンが際立つ。
《サルヴァトーレ・アッカルド(ヴァイオリン)/シャルル・デュトワ指揮/ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団/PO》