蛭川徹さん!
蛭川さんのheel landing の重要性についてのコメントについて、青木先生から解説が届いています(笑)。
-
「平坦踏着」か、「蹄先先着」か、あるいは「蹄踵先着」か、という疑問ですが、尤もな疑問であるし、またこのブログの一説を読んで、大切なことは先着部位ではなく、平坦負重であることにいち早く気付いてくれた蛭川さんの明晰さには、改めて感心しました。
平坦負重が重要であり、先着部位は負重バランスを論議する上では、余り重要ではないのですが、競走馬時代の常歩は、確かに蹄先先着が多数見られます。
その理由の一つは、競走馬が速度を求められるからです。速さだけを求められる調教が日常的に繰り返されると、前肢も後肢も、着地時の地面からの逆圧(前後分力の衝撃や制動力)を最小限に抑えるため、アシは着地する前から後方に引き戻されながら着地するような動作が強調されます。
屈腱群の筋電図の機能で説明した、着地直前の総指伸筋との共同作業による「ポインティング動作」の直後から、アシは後ろに引き戻されながら着地するのです。
乗馬でも同じ引き戻し動作は見られますが、速度を求められる競走馬は、制動力も大きくなるので、なおさらこのアシの引き戻し動作を強調されて、安全対策と共に、速度減衰を抑える方向に適応しています。このような日常的な適応が、おそらく四肢の筋肉の協調性(Muscle Cordination)を微妙に変化させ、常歩でも習慣的に蹄先先着が現れるのでしょう。
この着地前のアシの引き戻し動作が、馬体の前進速度よりも速く引き戻されれば、蹄先先着でも安全性には問題はありませんが、もしも、馬体の速度よりも、アシの引き戻し速度が遅ければ、蹄先先着した途端に、馬は蹉跌(つまづき)を招き、あるいは冠膝を招いて、大事故に繋がる可能性が高まります。
常歩だけでなく、蛭川さんが遅い駈歩でも蹄先先着を認めたのは、その駈歩の速度よりも、アシの引き戻し動作の速度が速かったからではないでしょうか。
襲歩のレベルでは、それらの馬たちもおそらく蹄踵先着に切り替えているはずです。実際の馬場でのデータはありませんが、トレッドミルの上での襲歩では、どの馬も蹄踵先着です。競走馬が引退し、乗馬の調教を受け続けると、速度を求めない乗馬では、いずれは蹄先先着が消滅します。
さらに言えば、襲歩では、多くが前肢は内弧歩様で走ります。その結果、内蹄踵の先着が強調されます。内蹄踵の挙踵や内蹄側の蹄冠裂(Big Brownのような)が起こりやすいのも、この襲歩時の内弧歩様や、内向性(仮性内向の要因)踏着が関係しているはずです。
-
う~ん、さすが青木先生。
研究結果に基づいていて、しかも深いな。
古典的にflat landingが重要とされ、馬の歩様を観て、
「どこどこを紙一枚削れ」
と名装蹄師が指示して、その通りにしたら馬の跛行が治った。
などという伝説を聞いたことがあるが・・・・・・・
青木先生の解説を聞いた後では笑い話のようだ。
-
さて、
蛭川さんのコメントの主旨は、
蹄尖で着地する馬と、蹄踵で着地する馬の蹄踵部の発達の比較から、
「2mmのクッションがついていることよりも、
蹄叉のサポートを増やし馬が自ら衝撃緩和機能を最大限に引き出す方が方向性としては正しいのではないか」
というところにあったはず。
今年のケンタッキーダービー出走馬のうち最も立派な蹄叉をしていた馬の写真を次回お見せしましょう。
-
-
蹄なくして馬なし。
と言われるが、
馬の蹄についても
霧中模作。
-
だけどサ~
休養馬の蹄が糞だらけで
蹄叉が腐ってボロボロなんてのは
問題外だゼ。










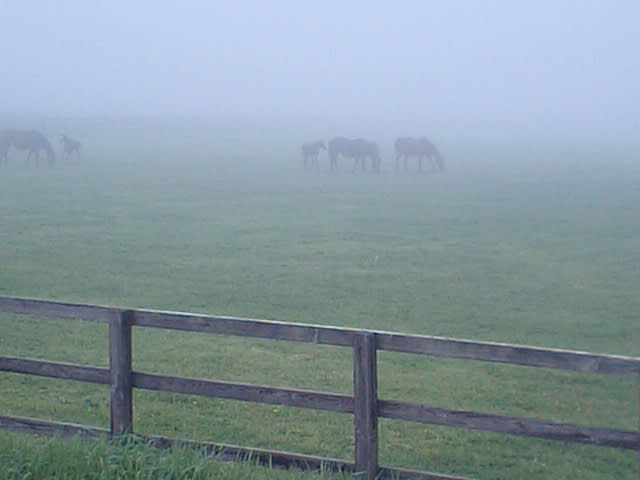
青木先生直々にコメント頂けるとは恐縮です。
最終的に(蹄骨の)Flat Loadingが成されれば、先着部位についてはギャロップにおいて重要ではない・・・(ギャロップではみな蹄踵先着になるが)、これについては理解できたと思います。しかしギャロップ以下の速度の運動時、先着部位の違いによる蹄内バイオメカにクスの変化による負荷の変化の影響はいかがなものでしょうか。
以前こちらのブログで紹介されていたThe Lame Horse の著者、Dr. Rooney 氏はナビキュラーの研究で数千体に及ぶ解剖検査を行いその結果、ナビキュラー症候群の最も最初のダメージをナビキュラーボーンの骨膜の変色と発見しました。その後氏は、死んだ馬の肢を機械にかけ繰り返し上下の負荷をかけて解剖検査を行なった結果、蹄尖先着にセットした肢はナビキュラー骨膜の変色が見られ、蹄踵先着の肢は蹄そのものが潰れても変化がなかったそうです。
ナビキュラーはともかくとしても、ギャロップ時が故障の確立が最も高く、またその程度も大きいものとは思いますが、速度が遅くともコンスタントにある種の異常歩様(?)を続けていることによる弊害の存在は否定できないと思います。BTCで乗っていて気がついたことですが、砂の馬場に残る足跡が偶に踵の無いものが有ります。実際にこの目で確認しましたが、蹄が砂に蹄尖から刺さり踵を負重せずに反回する事があります。この時Load は明らかに蹄尖部にあり、蹄が本来持つバイオメカニクスは機能していないはずです。ギャロップ時にはFlat Loadingしているのでしょうが、かりに速歩でもこのような状態がコンスタントであれば何かしら大なり小なり弊害がありそうな気がします。
ケンタッキーダービー出走馬の立派な蹄叉、拝見させてもらいました。凄いですね。関わる馬全てにあの様な蹄叉を育ててやりたいものです。あの馬は常歩時、蹄踵先着で歩いていないか、装蹄師は改装時あの蹄叉にナイフを入れているのか、1年のうち裸蹄にするオフシーズンは有るのか、あと蹄枕の発達はどうか、大変興味があります。
Mr Ramey氏は、馬の肢の球節から下を車のスプリングサスペンションに例えると蹄枕がその末端にあるストッパーの役割をしている、と言います。競走馬の蹄枕の発達程度と故障の割合のデーター、誰かとってくれないでしょうか?
ナビキュラー病の、慢性の、高齢馬に多く、しかも競走馬より乗馬に多い。という発生状況を考えると、遅い走速度の小さな荷重による変化の蓄もナビキュラー病を引き起こすのでしょう。私はナビキュラー病はほとんど診たことがありません。
蹄踵へ荷重しないまま反回するステップがありますか・・・・蹄跡をそこまで観ているのはたいしたものです。
USAではnatural hoof careの考え方を競走馬の装蹄師も取り入れているのかも知れませんね。USAでは、いろいろな目的のいろいろな種類の馬を装蹄・削蹄しないといけないのでしょうから、考えを揺さぶられることも多いはずです。
閉鎖社会の徒弟制度は鎖国のようなもので、進歩が遅れます。オッと、これはグチです(笑)。