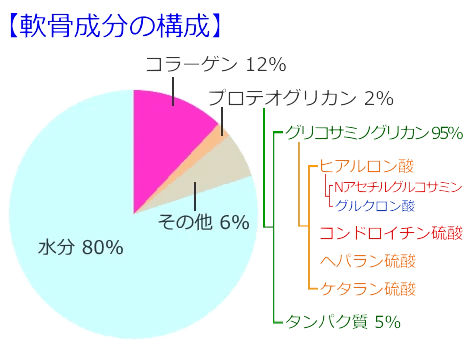もう1つ北獣誌2025年3月号から。
こちらは原著論文「日本輓系種にみられた馬増殖性腸症の発生牧場におけるLawsonia intracellularisの浸潤状況調査」
空知家畜保健衛生所からの報告。
昨年(2024)に日本獣医師会雑誌に「日本輓系種にみられた馬増殖性腸症の1例」として、2022年11月に国内の重輓馬で本症の発生が初めて報告されている。
その翌年1月と11月に当該牧場とその近隣の野生動物の調査を実施した報告。
ー
う~ん、採材が虫食いでわかりにくい。
6厩舎に分かれていたようだが、血液・糞便を採取していない厩舎が2つあり、それとは別に厩舎の環境材料を採取していない厩舎が2つある。
なんで?
結局1月に調べた成馬たちは7頭中7頭で抗体は陽性。
しかし、1月の糞便は12頭(繁殖牝馬7頭、明け1歳馬5頭)すべてで陰性。
ただ、11月の当歳馬6頭(表では1/7となっている)は1頭がPCR陽性。
厩舎環境は、敷料、餌槽、水槽、馬房壁を17箇所調べ、馬房壁の2箇所がPCR陽性。
野生動物は、アライグマ14頭、ネズミ2匹、タヌキ1頭を調べ、近隣酪農場でつかまえたアライグマ2頭がPCR陽性。
ー
どこからどうやって入ってきたかわからない馬のLawsonia intracellularis感染症だが、重輓馬サークルへも広がってしまったのだろう。
重輓馬生産地域の獣医さんにも、この病気について知っておいてもらう必要がある。
多少の地域的重なりや、人や馬の交流があるのでいたしかたない。
重輓馬も離乳後の当歳馬が感染し、重篤な症状を示すのだろう。
発生が懸念される地域ではワクチンを投与するのが望ましいだろう。
そして、野生動物が媒介していることがこの事例でも確認された。
アライグマ、ネズミが厩舎に出入りしていることは望ましくない。
対策はされているのだろうが・・・・・・
私は、厩舎ではイヌやネコを飼ってはどうかと思う。
イヌはアライグマやタヌキの侵入を阻止し、ネコは厩舎のネズミを減らしてくれると思う。
イヌを放し飼いにしてはいけない、とか
ネコは家の中で飼え、とか
ご意見も、お役所の指導もあるだろうが、街中と田舎ではちがう飼い方が認められても良いのではないだろうか。
////////////////

薪棚の中にドングリが隠されていた
誰が隠したんだろう?
この林にはリスはいないと思う
そして隠したまま忘れたうかつ者だ