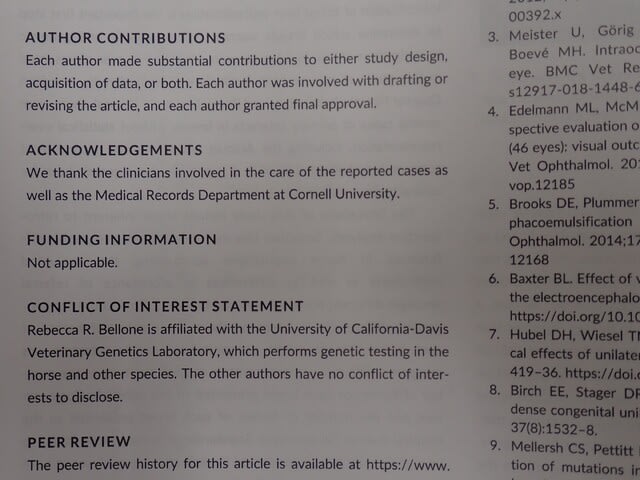Equine Veterinary Journal の掲載論文の変化について思うこと。
本分の最後に、共著者(共同発表者)のそれぞれがその論文について何の役割を果たしたのか表記するようになっている。

A はこの研究のすべてのデータに関係しており、そのデータの尊厳に責任があり、B とともに分析の正確性にも責任がある。
CとDは、この研究のデザインを行った。
Aがデータを入手した。
AとBがCT画像を評価した。
EとAが統計解析を行った。
すべての著者は論文を下書きし、校閲し、最終論文を承認した。
ー
論文に責任を持つ人だけが共著者であることを示している。
そして、各人が何の役割を果たしたかを示している。
さらに、役割を果たしていない人、責任を持っていない人が共著者に入っていないことを示している。
-

すべの著者が研究デザインと実施に貢献した。
発案、データ収集、統計解析、データ分析、そして文章著述はAが行い、Bが校閲した。
C,D,E,Fは調査の発案と計画に貢献した。
Gは調査の技術的実践について支援し・・・・
ー
役割を果たしていない人は共同報告者に入っていませんよ。
ー
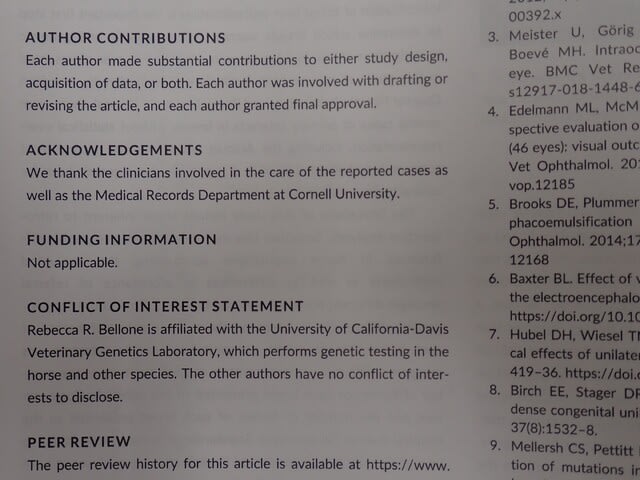
すべての著者は、研究デザインとデータ収集、あるいはその両方に間違いなく貢献した。
それぞれの著者は論文の著述、あるいは校閲にたずさわった。
そして、それぞれの著者が最終論文を承認した。
-
関係していない人が共著者になっていたり、最終論文を見ないままになっていたりしませんよ。
ーーー
本来、論文の共著者とは、その論文について責任を負う人ということになっている。
一緒に診療したとか、採材に協力したとか、論文作成にアドバイスしたとか、etc.という人には、謝辞を述べるにとどめるべきなのだろう。
ー
「協力したのに共著者にオレの名前が入ってない」「もう二度と手伝わない」
と言われると、以降の調査研究ができなくなる。
それなら、計画段階 concept の段階から研究に入ってもらって、実践 implementation も手伝ってもらうのが本来なのだろう。
ー
私も長く調査、研究も行い、学術論文にも名前を連ねてきた。
時代は進み、研究として緻密さと厳格さが要求されるようになっている。
ダイナミックではなくなっているかもしれないが、そうあるべきところへ進んでいるのだろう。
ー
著者の中で、とくに筆頭著者 first name は研究者として社会的にも研究歴として特別な扱いを受ける。
最も責任が重く、その論文著述、その研究を最も主体的に行った者が筆頭著者がなるべきであろう。
そうでないなら研究上、論文報告上の虚偽だ。
///////////

前日は好く晴れて山容が見えていたのに、登頂前夜は大雨。
朝は雨が止むのを待って登り始め、原生林の中を歩き、急登にあえぎ、なんとか頂上へ。
雄阿寒岳。
原生林に囲まれ、大小の湖沼を麓に持つ独立峰。
眺望が素晴らしい・・・・そうだ;笑

登りでへばっていると下りもなかなかたいへんだ。
秋の日は短い。
それでもゆっくり降りたので、倒木いっぱいの原生林をたっぷり味わえた。
晴れた日にまた登りたい。
ー
そう言うと、論文投稿、論文掲載を高みに登る summit って呼ぶ。