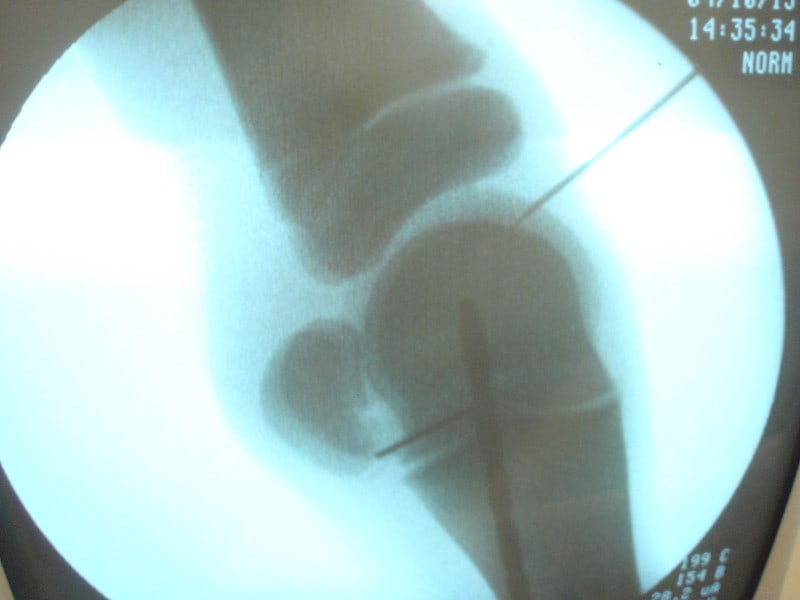2005AAEPでのG.A.Perkinsの講演は、「重症馬に」ということになっているのだが、
では、どうやって脱水を評価するか。
-
体重は体重算出用のテープか体重計で調べることができる。
脱水は、皮膚テント、粘膜の湿潤度、毛細血管再充満時間(CRT)、心拍、拝尿、頚静脈充満、眼球陥没などで評価する。
皮膚テント(秒) 粘膜 CRT(秒) 心拍 その他
5% 1-3 少し粘 <2 正常 排尿減少
8% 3-5 粘 2-3 40-60 動脈圧低下
10-12% >5 乾燥 >4 >60 頚静脈充満低下・眼球陥没
検査室データでは、
PCV、血清蛋白値、尿比重、BUN、クレアチニン、乳酸などを脱水の評価に使う。
(参考引用おわり)
-
皮膚テントは、エンデュランスの獣医委員をしていると、
「頚じゃなくて肩先でみてください」
とライダーに言われたりする。
頚の皮膚は汗の具合や頚の位置でたるんだりするからだ。
-
口粘膜は正常では濡れてピカピカ光り、きれいなピンク色をしている(馬によって色素がついているのがいるので注意)が、脱水すると唾液が粘り強くなり、乾いて泡立ったりする。
-
口粘膜を指で押して、白くなったところが元に戻るまでの秒数がCRT。
この表はかなり厳しく計っている。
おまけに表示の仕方がヘンだ。(3-4秒だったらどうなの?;笑)
-
心拍は脱水だけの指標ではない。
-
検査データではPCVが汎用される。
しかし、貧血があると間違いの元だし、
馬の種類、性別、季節によって正常値が異なる。
だから、血清蛋白値その他も参考にすべきだ。
乳酸値は疝痛馬では脱水というより痛みと腸管の絞扼部の有無に影響される。
---
さて、どうでしょう。
5%程度の脱水の馬にはしょっちゅうお目にかかるのではないでしょうか??
その欠乏量は(維持量や予想欠乏量は別にしても)500kgの馬なら25?なのです。
(つづく)
//////////
3週間ほど蹄球部の化膿が治まらない1歳馬。
木片にしてはあまりに丸くて滑らかで大きい。
軟骨か?
骨片か?
切開して取り出したら・・・丸くて長い枝だった。
-
鼻涙管が鼻側開口部近くで狭窄している。
というか途中で傷がついてそこから漏れてくる。
全身麻酔して、眼の方から管を入れて、本来の開口部ではないところを切開して管を引っ張り出した。
このまま管を残しておけば、あらたな開口部が作られる。
-
どちらも吸入麻酔までは必要ないが、立位でやろうとするのはちょっと難しくて危険。
---
脚を投げ出して昼寝していた。
物音に気づいておきたけど
寝ぼけている。
そんな顔でショ?