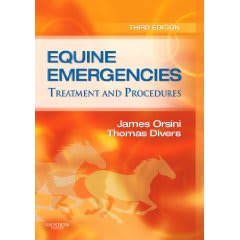仔馬が調子悪くて診ていたら、母馬の上眼瞼に腫瘤があるのに気づいた。
仔馬が調子悪くて診ていたら、母馬の上眼瞼に腫瘤があるのに気づいた。
上瞼も馬類肉腫 Equine Sarcoid の好発部位だ。
「大きくなるようだと治療しなければいけないかな」
と話していたら、突然こんなになってしまった。
全身麻酔して手術することにした。
血腫にもなっているのだが、上眼瞼の中には白い腫瘍塊もある。
できるだけ完全に摘出する。
 Sarcoid は牛パピローマウィルスが感染することで起こるとされていて、たいへん再発が多いことも知られている。
Sarcoid は牛パピローマウィルスが感染することで起こるとされていて、たいへん再発が多いことも知られている。
それで、自家移植免疫療法も併用することにした。
摘出した腫瘍塊をフリーズスプレーで凍らせておいて(左下)、
腫瘍と牛パピローマウィルスに対する免疫を促進させるというのがねらいだ。
どのくらいその効果があったかを客観的に評価するのは難しいが、再発しなければ良しとしよう。
 血腫になってしまっていたので、瞼の腫れは残ったが、Sarcoidとしての再発はないようだ。
血腫になってしまっていたので、瞼の腫れは残ったが、Sarcoidとしての再発はないようだ。
Sarcoidができる場所にもよるが、あまり大きくなるまで放置しない方が良いように思う。
大きくなりすぎると、摘出・切除手術するにもてこずるし、完全な切除・摘出が難しくなる。
---
明日から東京行き。
JRA調査研究発表会とウマ科学会。
12月1日はウマ科学会獣医師ワーキンググループによる症例検討会。
クイズ形式?による会場参加型の研修会になる予定だ。
私にも初めての経験だ。
参加される方、東京で会いましょう!