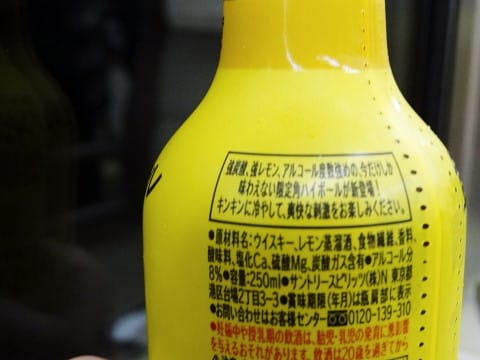家族旅行のときは、明るい時間帯にチェックインして、のんびり温泉に入ったり、2時間近くの食事タイム。今回は観光がメインで、宿は泊まるだけのプランなので、1泊2食付きで2万や3万とかの超贅沢なところではない。朝食のみ提供なので、夕食は外食。
実はといいますと、宇奈月温泉は今回で2回目。前回は2004(平成16)年あたりだったかな、国王様が家族旅行の費用をすべて出してくれたので、私がホイホイ付いて行ったのは覚えています。そのときはあわびの踊り焼も出たところなので、グランドホテルだったような??
駅前でどこか見たような人を見かけました。「あっ、Kさんですか?」と話しかけられ、びっくりした。「K先生(うちの姉のこと)が少し前、富山にいらしたんです。お世話になっております」「あの~、すいません、どちらさまなんですか?」「○○だけど」「ああっ、思い出した!ン十年前のデフファミリーin富山でお会いしましたよね」「そうそう!!ところで、今日は?」「黒部渓谷鉄道のトロッコ列車観光から帰ったばかりです」「富山は長い間、裏日本と言われていて、あんまり観光客は来なかったんですよ。新幹線のおかげで東京からアクセスしやすくなりましたね」「宇奈月という手話表現はどうやるんだっけ?」(「温泉」の手話表現に、口の形は「うなづき」)「あっ、なるほど」
国王様の実務範囲は海外、北海道から沖縄に及ぶ(数日前も鹿児島)ので、ろう者の世界は狭い。私の実務範囲は市内を支えるところなので、出張も市内のみ。
手話も、その土地で使われている方言みたいなものもあります。固有名詞の地名も、その土地で使われている表現を尊重します。
例えば、北朝鮮の手話表現は「北」、チマチョゴリのリボンを表現しますが、北朝鮮のろう者は、そんな表現は使わない。まして、国名に「北」を冠するなんて侮辱行為に等しいらしい。正しい表現は、南朝鮮(ナムチョソン)との統一を願い、朝鮮半島の地形を表現。NHK手話ニュースキャスターたちも、現地の手話を尊重し、そのような表現を使われるようになりました。

田舎の休日は自宅で御飯を作る家が多いのか、シャッターが閉まっている飲食店が多い。そのなかで開いていたところは焼肉店でした。

日本人に合わせているのか、甘~いキムチでした。キムチが甘ければ食べやすいかも知れませんが、少し糖分が気になります・・・。

盛り合わせ。

モツ鍋。ここで2時間くらい滞在しましたが、お客さんは1人も来ませんでした。私たちだけの貸し切り。

翌朝。ホテル自慢の朝食バイキング。

あれほど、美味しいごはんを提供できるなら、夕食もできるはずなのに、なぜかやっていません。

あれこれ欲張ってかき集めてしまいました。朝食にパスタとは・・・。その分、白飯を減らしました。1泊朝食付き7500円のホテルでした。温泉も付いていて、リーズナブル。次の記事は、高岡までの移動手段。
実はといいますと、宇奈月温泉は今回で2回目。前回は2004(平成16)年あたりだったかな、国王様が家族旅行の費用をすべて出してくれたので、私がホイホイ付いて行ったのは覚えています。そのときはあわびの踊り焼も出たところなので、グランドホテルだったような??
駅前でどこか見たような人を見かけました。「あっ、Kさんですか?」と話しかけられ、びっくりした。「K先生(うちの姉のこと)が少し前、富山にいらしたんです。お世話になっております」「あの~、すいません、どちらさまなんですか?」「○○だけど」「ああっ、思い出した!ン十年前のデフファミリーin富山でお会いしましたよね」「そうそう!!ところで、今日は?」「黒部渓谷鉄道のトロッコ列車観光から帰ったばかりです」「富山は長い間、裏日本と言われていて、あんまり観光客は来なかったんですよ。新幹線のおかげで東京からアクセスしやすくなりましたね」「宇奈月という手話表現はどうやるんだっけ?」(「温泉」の手話表現に、口の形は「うなづき」)「あっ、なるほど」
国王様の実務範囲は海外、北海道から沖縄に及ぶ(数日前も鹿児島)ので、ろう者の世界は狭い。私の実務範囲は市内を支えるところなので、出張も市内のみ。
手話も、その土地で使われている方言みたいなものもあります。固有名詞の地名も、その土地で使われている表現を尊重します。
例えば、北朝鮮の手話表現は「北」、チマチョゴリのリボンを表現しますが、北朝鮮のろう者は、そんな表現は使わない。まして、国名に「北」を冠するなんて侮辱行為に等しいらしい。正しい表現は、南朝鮮(ナムチョソン)との統一を願い、朝鮮半島の地形を表現。NHK手話ニュースキャスターたちも、現地の手話を尊重し、そのような表現を使われるようになりました。

田舎の休日は自宅で御飯を作る家が多いのか、シャッターが閉まっている飲食店が多い。そのなかで開いていたところは焼肉店でした。

日本人に合わせているのか、甘~いキムチでした。キムチが甘ければ食べやすいかも知れませんが、少し糖分が気になります・・・。

盛り合わせ。

モツ鍋。ここで2時間くらい滞在しましたが、お客さんは1人も来ませんでした。私たちだけの貸し切り。

翌朝。ホテル自慢の朝食バイキング。

あれほど、美味しいごはんを提供できるなら、夕食もできるはずなのに、なぜかやっていません。

あれこれ欲張ってかき集めてしまいました。朝食にパスタとは・・・。その分、白飯を減らしました。1泊朝食付き7500円のホテルでした。温泉も付いていて、リーズナブル。次の記事は、高岡までの移動手段。