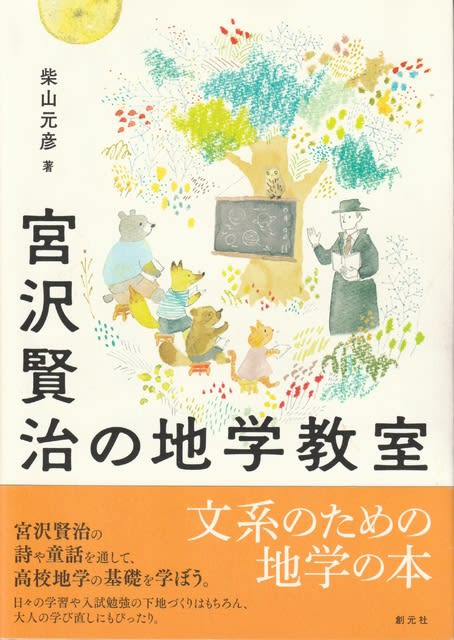あの森永さんが余命を知ってから書いた渾身の1冊。
・・・ということを知り、俄然読みたくなった。
一方で、なぜ無名の出版社なのか、もしかしたらトンデモ本?
という、少々腰が引けた気持ちがなかったと言ったらウソになる。
まして内容がジャニーズやら、日航機墜落事件やら、
そしてこれまた話題となった「ザイム真理教」の続きという
なんか内容的にバラついている気がしたのも確かだ。
深掘りしているであろう「ザイム真理教」を読むべきか
それともあちこちの話題であろう本書を読むか散々迷って
つい「コスパ」を考えてこちらにしてしまったことを白状する。
読後の第一印象は、とにかく「すごい」。
バラついた内容という先入観はまったく覆された。
特に一番「今なんでこの話題?」と思っていた日航機事故。
ちょっとやそっとじゃ100%にわかには信じがたいが
もし本当にこういうことが裏で起きていたとしたら
現状の日本の政治や外交の問題の原因が確かに腑に落ちる。
びっくりするような陰謀論にも見えるけれど
でも確かに物事はその方向に流れている。
そして大手出版社が本書の出版を断ったというのも
読了後には理解できる。
バブル経済のあのタイミングと本当の正体。
中曽根、小泉が犯した罪。
政界、官界、外交の闇。
それらの本質が本書にわかりやすく書いてある。
それにしてもここまでとは・・・。
本書に書いてあることは、当事者である政界、官界はもちろん
各マスコミも、経済、政治などの評論家も知っていると思われる。
でも口を閉ざさざるを得ない状況。
彼らは果たして本書を書いた森永さんを
苦々しく思っているか、心の中で喝采を叫んでいるか。
書いた森永さんもすごいが
出版を決めたひとり出版社三五館シンシャがとにかくすごい。
「社員がいないので、何があっても自分が被ればいい」という覚悟と、
ジャニーズ問題→ザイム真理教→日航機事故と進めた内容。
それらの話題がスムーズに流れ、全て繋がってくる。
これぞ編集力。
でもさ、こんなもの見せられると
マスコミ報道をそのまま信じることができなくなる。
もちろん彼らの苦渋もわかるし、姿勢にも理解は示せるから
一方的に責めようとは思わないけど
じゃあ我々は何を信じればいいのだろう。
「書いてはいけない〜日本経済墜落の真相」森永卓郎:著 三五館シンシャ