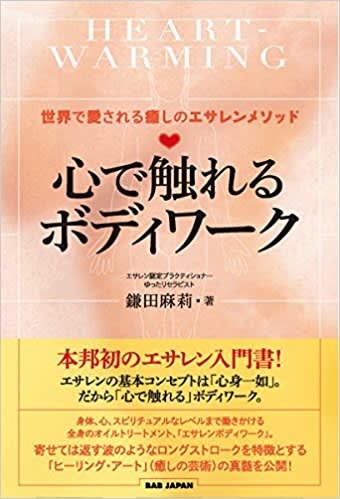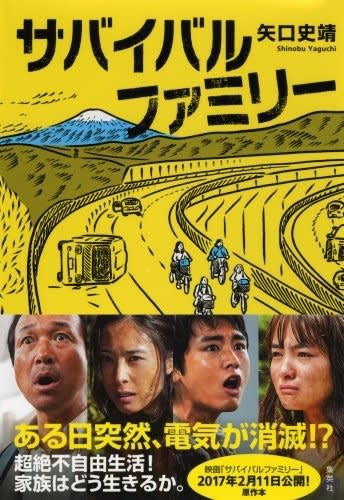ここのところ、仕事上カメラが欲しいと思っていた。
今携わっている、あるいはこれから携わる予定の仕事で
そろそろ買わなきゃなと機種選定を始めていた。
欲しい機能を備えた機種は、レンズも合わせ5〜6万円ぐらいと知り、
資金繰りの関係から「来春ぐらいまでには買えるかな」と
胸算用し始めたのが先週半ばごろ。
そんな中、先週土曜日に神楽披露のため
はなまき産業大博覧会へと出かけたのだった。
10時半からの神楽の出番を終え、
道具片付けに神社へ帰るまでの間、
お昼近いこともあり1時間ほど自由時間となった。
出店を見て歩き、お昼ごはんも仕入れた後で
飲食店中心の花巻市総合体育館第2アリーナから
誘致企業などが集まる第1アリーナへとぶらり行ってみる。
入ってすぐ右側に出展されていた富士フィルムブースに
「カメラ特売」の看板をすぐに見つけた。
「へー、どんなカメラがいくらぐらいなのかな?」と立ち寄ってみる。
「えっ???安いじゃん!!!」
コンデジから、ミラーレス、一眼など様々な機種が
数千円から、高くても3万円ぐらい(しかも一眼はレンズ2本付き)。
幾つか手に取り、機能も確認してみる。
3万円で売っていた、レンズ2本セットのミラーレスがいいと思ったけど
聞いてみるとどうやらその場ではカード買いはできないようだ。
「欲しいけどなー、現金あまり持ってないしなー」
と逡巡しながら、他の機種も触ってみた。
その中で見つけたのがこの1万円の札が付いている写真のFINEPIX S09900W。
「ほー、広角もズームも固定レンズだけでOKなのか」
説明を聞いてみたら接写もできるとのこと。
たしかに対象物に2cmほど近づけてもちゃんとピントが合う。
ためつすがめつ見ていたら
説明してくれていた女性社員の後ろから
上役っぽい少し年配の方が「それ、良ければ8千円でいいですよ」と。
急いで財布の中を確認。万札がある!!
ということで、ひょんなことからカメラを衝動買い(^^;
あとから価格ドットコムで値段を調べてみたら
同じ機種の値段はほぼ3万円ほど。
すげー!! それを8千円で買っちゃった(笑)
確かに本当は件の3万円で売られていた機種が欲しかったし
知人に薦められていた5〜6万の機種もそれと同じシリーズだったから
ちょっと無理してでもそちらを選ぶべきだったのかもしれないが、
欲しい機能は全て揃っていたし、
仕事用で欲しかっただけで、趣味として凝るつもりはなかったので
8千円ならこれで充分でしょ(^_-)
衝動買いって大抵後ろめたさや若干の後悔があるんだけど
これはもう大正解。
不思議な縁で、このカメラは私の元にやってきた。