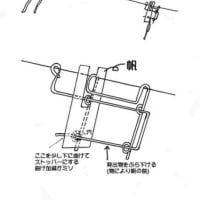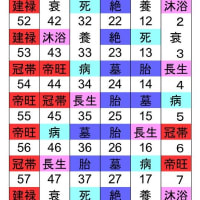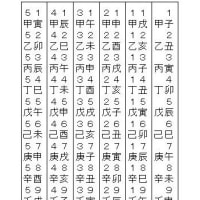先日、西陣の狭い道を自転車で走りながら、リュックからスマホを出そうと道に面した家の格子際に止めた。格子下の側溝沿いの敷石が10㎝ほど高く、またがったまま足を乗せると安定するからだったが、リュックを外そうとしていると、目の前の玄関ドアが少し開き、中から大型犬が口を突き出して、猛烈な勢いで吠え始めた。
状況と意味は解ったので、すぐその場を移動した。その間、30秒も経っていない。
京都に何十年も暮らし、京都人の良さも理解しているつもりで、折に触れ、京都人は意地悪ではありませんよと喧伝に務めているのだが、こういう時には、『ああ、これじゃあしょうがないなあ』と、情けなくなる。
近頃は、祇園でも、一見さんお断りとは言っていられなくなったそうだが、その心は広く京都に根付いているようだ。
千年の都、京都は利権の中央だ。ここから公家や社寺が全国の領地を支配し、領地と権利でせめぎ合ってきた。そういう土地柄は庶民に至るまで浸透し、土地に対する権利意識が強い。
土地に対する所有意識は特に京都でなくても強いが、地方豪族や武士集団が自らの血肉として一所懸命に守るのとは色合いが異なる。お上から与えられた土地、継承によって得られた土地に対する権利意識は、自分自身の「物」である前に、自分に与えられた「権利」そのものを所有物と考えている。
自分の物であれば、多少汚されても自分の裁量で寛容になれるが、形のない権利は主張しなければ消えてしまうし、賜った物を汚されることは、自分が勝手に容認するわけにはいかない。権利を守るのは使命だ。
京都で遭遇する私有地の権利主張は、誰も表だっては口にしないがしぶとく、ただの所有欲以上の敏感さを感じる。京都に来て初めて感じた自慢話は、「借家がある」と言う会話で、これがステータスを表す。
自分に権利のある土地を守るためには、何でも許される感覚があり、文句があるなら出るとこに出てもらえば良いと言うことだろう。
実際、権利に「お互い様」は無い。狭い曲がり角に置く「いけず石」や、「駒寄せ(除け)」など、いちいち自分の口で、「ここに入るな」とは言わないが、掃き清めた門前とともに、暗黙の威嚇になっている。
京都人は争うことを好まない。しかし、権利と秩序を守る「使命感」は強い。この矛盾を解決しようとする多様な手段が、「意地悪」になってしまう。
力によらないで秩序を保つためには、流儀を知らずに「なんでやねん!」と言い出しそうな、心得ない「一見さん」は初めから避けたい。
窓の格子に人影が見えた瞬間、『うちの前で何やろ!』と、恐怖心と権利意識が働き、かといって、何者か解らないし、自分が出て角を立てたくない。そっとドアを押して、この日のために飼ってある犬を覗かせて、一見さんお断り。
用意周到なのが京都人だ。
ただ、こんな家の人でも、知り合いなら極めて好意的で、全く違う顔を見せる。犬なら知り合いと他人をよく心得ているから、先ず犬に様子を見させたというわけだ。
そもそも知り合いは、自ら先に声をかけ、驚かせないようにする。
大阪人が京都人を嫌うのは、いきなり入りこんでくる大阪人に、小心な京都人が繰り出す様々なバリアを、「得体が知れない、腹黒い」と思ってしまうことが大きいのだろう。