もう、車を持っていないので、「へー!」という話なのだが、欧州車オーナーの記事によると、近頃の車には抜いて確かめるオイルゲージが無く、コンピューターで判断し、それがまたややこしく、コンピューターの要求する条件に合わせなければ計測できないのだそうだ。
そのレベルや真偽のほどは解らないが、欧米の科学信仰は「デキル亊はスル事」の精神があり、コンピューター技術もどんどん取り入れる。新しい技術は神から賜ったのだから、使うべしの衝動があるようだ。だから、教会が月探検や遺伝子操作、AIの新技術にストップをかける。東洋人から見れば不思議な教会の横槍だが、そもそも科学自体が神の賜り物と考えられているからだ。この点、中国には何のこだわりも歯止めも無い。
欧米の新技術に対する積極性は、それが本当に前より良いかではなく、とにかく新しい技術を優先する。コンピューターコントロールを過信して起こった飛行機事故も少なくない。(→「飛行危機」)
自動車の自動運転については様々な事が懸念されているが、問題は何でもコンピュータ任せにするのではなく、何を任せ、何を任さないかだ。
自動車の運転に関して、視聴覚や機器操作の判断は、おそらく人間より機械の方が確かだろう。だから、無人の車が公道を走るのは危ないというなら、飲酒運転やスマホ操作、高齢運転の方が遙かに危ない。一方、A300の様に人間の意思とコンピュータの意思が矛盾して起こった飛行機事故では、設計思想に重大な誤りがあった。操縦主体を人より機械を優先していた。
これから先、ますます自動化が進むだろうが、無駄な議論をするより、機械的「判断」はどんどん機械に任せ、何をどのように動かすかの「意思」は、確実に人間を優先するというポイントを押さえれば良いのではないか。
欧州車にマニュアルのオイルゲージが無く、コンピューターだけでオイル交換の意思決定をするのだとしたら、小さな事のように見えるがA300と同じ設計思想であり、いきなりEV転換を義務づける発想と同じで、やっぱり教会に叱ってもらうしかない。もっとも、その教会は、原爆開発当時にはごく一部の反戦論者を除き、口を挟むことはなかった。











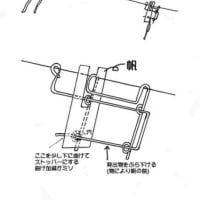






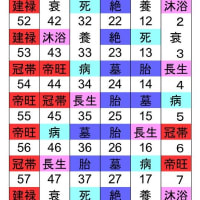
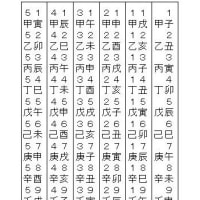
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます