愛車で10分弱のところこに、市の中央公民館がある。「中央」という立派そうな名が付いているけれど、隣の支所の影のような目立たない施設だ。その一隅にささやかな図書室がある。
児童書が多く、家庭的な趣きを主としているが、書棚をゆっくり眺めてゆくと、ハッとさせられる本に出合うことがある。こんなに小さな図書室なのに、品揃えがいいな・・と思う。県立図書館等の本も快く取り寄せてくれる。
この図書室で先日見つけたのが、ジョン・ダワー(1938~)著、(三浦陽一・高杉忠明 訳)「 敗北を抱きしめて」(岩波書店 2001年 第1刷発行)。
・

ピュリッツァー賞を受賞しており、当時、大きな反響を呼んでいたのを私も記憶している。だのに、お恥ずかしいことに、私はまだ読んだことがなかった。世間一般も、今ではまるで話題に上らせなくなったようだ。
上下の2巻で構成されていて、取り敢えず借りた上巻だけで400ページ近い厚さだ。加齢と共に読書力が衰えた私にはハードルが高いかと不安だったが、読み始めたら止まらない。全てのページが劇的であり、かつ詩的でもあった。私の精神もまた、この国の戦後の渦中で血肉が形成されたことを、改めて思い知らされるものであった。
私にとっては、言わば、私の前半生を照らし出してくれる本だ。
序文の一部を以下に抜粋しておく。
現代の日本には、新ナショナリズム的な強い主張があり、そのうちもっとも強力な声のいくつかは、まさに本書が論じた敗戦後の年月に照準をあわせている。それは敗北と占領の時期を自由な選択が実際には制限され、外国のモデルが強制された、圧倒的に屈辱的な時代として描きだすのである。私自身は、この時代がもっていた活力と、日本の戦後意識の形成において日本人自身が果たした役割の創造性とを(略)、このような見方よりも積極的に評価している。大切なことは、当時、そしてその後、敗戦というみずからの経験から、日本人自身が何を作り上げたかということである。これこそは、敗戦から今日までの半世紀、日本人の多くが「平和と民主主義」と自分との関わりを考えるとき、たえず試金石としてきた問いであった。
児童書が多く、家庭的な趣きを主としているが、書棚をゆっくり眺めてゆくと、ハッとさせられる本に出合うことがある。こんなに小さな図書室なのに、品揃えがいいな・・と思う。県立図書館等の本も快く取り寄せてくれる。
この図書室で先日見つけたのが、ジョン・ダワー(1938~)著、(三浦陽一・高杉忠明 訳)「 敗北を抱きしめて」(岩波書店 2001年 第1刷発行)。
・

ピュリッツァー賞を受賞しており、当時、大きな反響を呼んでいたのを私も記憶している。だのに、お恥ずかしいことに、私はまだ読んだことがなかった。世間一般も、今ではまるで話題に上らせなくなったようだ。
上下の2巻で構成されていて、取り敢えず借りた上巻だけで400ページ近い厚さだ。加齢と共に読書力が衰えた私にはハードルが高いかと不安だったが、読み始めたら止まらない。全てのページが劇的であり、かつ詩的でもあった。私の精神もまた、この国の戦後の渦中で血肉が形成されたことを、改めて思い知らされるものであった。
私にとっては、言わば、私の前半生を照らし出してくれる本だ。
序文の一部を以下に抜粋しておく。
現代の日本には、新ナショナリズム的な強い主張があり、そのうちもっとも強力な声のいくつかは、まさに本書が論じた敗戦後の年月に照準をあわせている。それは敗北と占領の時期を自由な選択が実際には制限され、外国のモデルが強制された、圧倒的に屈辱的な時代として描きだすのである。私自身は、この時代がもっていた活力と、日本の戦後意識の形成において日本人自身が果たした役割の創造性とを(略)、このような見方よりも積極的に評価している。大切なことは、当時、そしてその後、敗戦というみずからの経験から、日本人自身が何を作り上げたかということである。これこそは、敗戦から今日までの半世紀、日本人の多くが「平和と民主主義」と自分との関わりを考えるとき、たえず試金石としてきた問いであった。












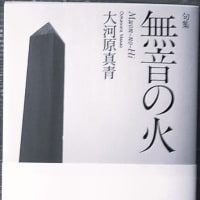

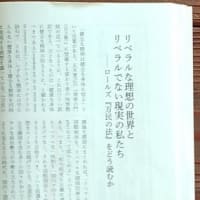
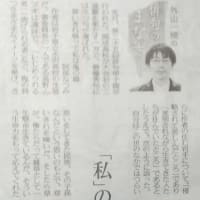
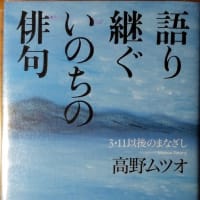
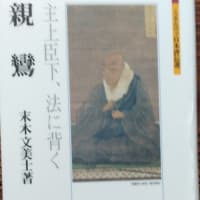


本当に「最良の書」、その良さは言葉に尽くせない感じがします。
これだけ素晴らしい本が、今、忘れ去られたようになっていることが、不可解であり、憤りさえ覚えます。