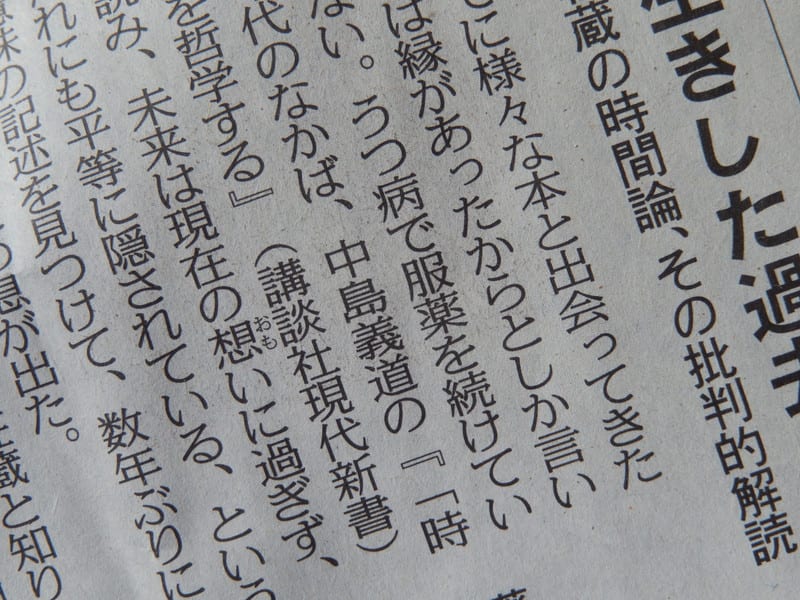梅雨明け後の猛暑を受けて、あちらの田んぼもこちらの田んぼも穂が出てきました。早稲の田は早くも穂を垂れ始めています。
梅雨明け後の猛暑を受けて、あちらの田んぼもこちらの田んぼも穂が出てきました。早稲の田は早くも穂を垂れ始めています。
当菜園の紫蘇も勢いが増して生長したので、恒例の紫蘇ジュースを作りました。
 作り方は畏友からの伝授。材料は、紫蘇の葉300g に対して砂糖1㎏・リンゴ酢500㏄・水1800㏄。
作り方は畏友からの伝授。材料は、紫蘇の葉300g に対して砂糖1㎏・リンゴ酢500㏄・水1800㏄。
①先ず、晴れた昼間に菜園の赤紫蘇を株ごと引き抜き、日陰で葉を摘みます。虫害などで傷んでいる葉は除きます。
②積んだ葉をビニール袋に詰めて、計量します。雨や夜露で濡れている葉は計量に適しません。葉は埃を被っているので、洗ってからよく乾して後に測るという方がいますが、手間の掛け過ぎでしょう。
③計量後に葉をよく洗って、埃などを洗い流します。
④大鍋に紫蘇の葉と砂糖と水を入れ、強火に掛けます。沸騰したら弱火にして20分位ことこと煮ます。
⑤火を切ると同時にリンゴ酢をドドドッと入れます。リンゴ酢ではなくてクエン酸を使う方が多いようですが、リンゴ酢の方が香りがいいような気がします。
⑥大鍋に出来上がった紫蘇ジュースの元を、濾したら完成。私は、空瓶等にジョウゴを乗せ、そのジョウゴにガーゼを掛けて、お玉で一杯ずつ注ぎます。
⑦大鍋底に残った紫蘇の葉は、まだ沢山のジュースを含んでいるので、一握りずつ絞って利用します。まだ高熱を孕んでいると火傷の危険があるのでご注意ください。
⑧粗熱が取れたら、冷蔵保存します。
⑨好みに合わせて3~5倍くらいに薄めて供します。夏は冷やして夏バテ快復の一助に。冬は温めても美味しいです。
不器用で料理が大苦手の私ですが、この紫蘇ジュースは簡単に作れて、透明なワインカラーが見た目も綺麗で、お裾分けすると喜ばれます。
砂糖は、上記の分量ではやや多めかも知れません。私は1割引きぐらいで作っています。
赤紫蘇を使うのが一般的ですが、青紫蘇でも作れますし、香りは青紫蘇の方が上、という評価もあります。ただ色が淋しいので、赤紫蘇を混ぜて作るという方法もお勧めです。