長谷川櫂が、岩波書店の「図書」2月号に再び夏目漱石について述べている。

やはり俳人らしく?簡潔にして要旨明快だ。明快過ぎて、返って「これでいいんだろうか・・・」と不安になるぐらいだ。以下、一部抜粋する。
人間の根源にあって人間を衝き動かす二つの欲望、お金と性こそが文学の永遠のテーマなのだ。
この文学の基本的な性格がぴたりとあてはまるのが夏目漱石の『こころ』(大正3年、1914年)なのである。
お金の争いで敗れて深刻な人間不信に陥ってしまった先生は、恋の争いでは勝ったものの生涯、自己不信に苦しめられることになった。
漱石の小説にはしばしば「高等遊民」が登場する。仕事をせず、親の財産で遊んで暮らすインテリのことである。
『こころ』の先生もまた高等遊民である。
明治の国家主義は天皇から庶民まで国家の役に立つ「有為の人」となることを求めた。そこからみれば職業をもたず国の役に立とうとは思わない、むしろ職業を軽蔑する代助(漱石著『それから』の登場人物)や先生のような高等遊民は反国家主義的な存在である。
立派な大人ではあるが、親の経済的支援を受けているから自立した人間でもなく永続もしない。しかし国家のためではなく自分のために生きる、新しい生き方にもっとも近いところにいたのが高等遊民ではなかったか。
ところが自由の光に目のくらんだ動物が檻へ後退りするように先生は明治の国家主義へ逆戻りしてしまうのである。
すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。其時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったような気がしました。
私は妻に向ってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積りだと答へました。
自分の生と死は自分の責任で完結させる。それが高等遊民というものだろう。それなのに、なぜ明治の精神に殉じるのか。自分で自分を支えるという孤独な営みに耐えきれなかったのか、明治の国家主義の亡霊にひれ伏す先生の最期は、やがて訪れる国粋主義時代の大衆の姿を予見しているかのようである。
ずいぶんと分かりやすい解説だ。正直なところ「目からウロコ」が落ちたかと思わせられる。しかしまたあまりにも分かりやす過ぎて、それでいいの?と反問したくなる。文学も歴史も、もっともっと複雑で混沌としていて、その解説は少なくとも重層的、多面的でなければならないのではないか。長谷川櫂の解説では「深層」どころか「表層」ではなかろうか、と疑ってしまう。もっとも、「表層」を暴いただけでも手柄ではあるとも思う。

やはり俳人らしく?簡潔にして要旨明快だ。明快過ぎて、返って「これでいいんだろうか・・・」と不安になるぐらいだ。以下、一部抜粋する。
人間の根源にあって人間を衝き動かす二つの欲望、お金と性こそが文学の永遠のテーマなのだ。
この文学の基本的な性格がぴたりとあてはまるのが夏目漱石の『こころ』(大正3年、1914年)なのである。
お金の争いで敗れて深刻な人間不信に陥ってしまった先生は、恋の争いでは勝ったものの生涯、自己不信に苦しめられることになった。
漱石の小説にはしばしば「高等遊民」が登場する。仕事をせず、親の財産で遊んで暮らすインテリのことである。
『こころ』の先生もまた高等遊民である。
明治の国家主義は天皇から庶民まで国家の役に立つ「有為の人」となることを求めた。そこからみれば職業をもたず国の役に立とうとは思わない、むしろ職業を軽蔑する代助(漱石著『それから』の登場人物)や先生のような高等遊民は反国家主義的な存在である。
立派な大人ではあるが、親の経済的支援を受けているから自立した人間でもなく永続もしない。しかし国家のためではなく自分のために生きる、新しい生き方にもっとも近いところにいたのが高等遊民ではなかったか。
ところが自由の光に目のくらんだ動物が檻へ後退りするように先生は明治の国家主義へ逆戻りしてしまうのである。
すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。其時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったような気がしました。
私は妻に向ってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死する積りだと答へました。
自分の生と死は自分の責任で完結させる。それが高等遊民というものだろう。それなのに、なぜ明治の精神に殉じるのか。自分で自分を支えるという孤独な営みに耐えきれなかったのか、明治の国家主義の亡霊にひれ伏す先生の最期は、やがて訪れる国粋主義時代の大衆の姿を予見しているかのようである。
ずいぶんと分かりやすい解説だ。正直なところ「目からウロコ」が落ちたかと思わせられる。しかしまたあまりにも分かりやす過ぎて、それでいいの?と反問したくなる。文学も歴史も、もっともっと複雑で混沌としていて、その解説は少なくとも重層的、多面的でなければならないのではないか。長谷川櫂の解説では「深層」どころか「表層」ではなかろうか、と疑ってしまう。もっとも、「表層」を暴いただけでも手柄ではあるとも思う。












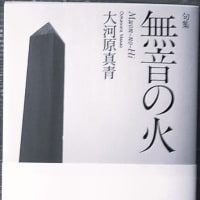

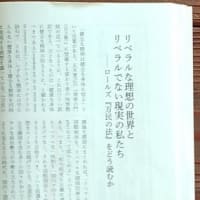
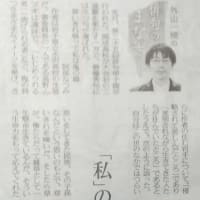
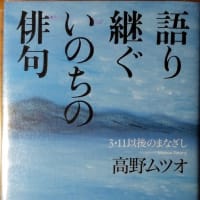
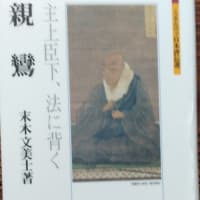


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます