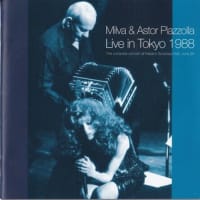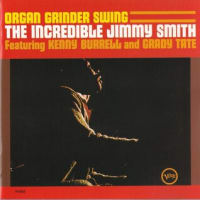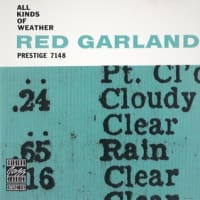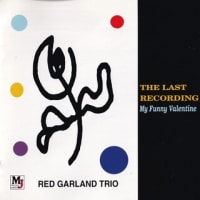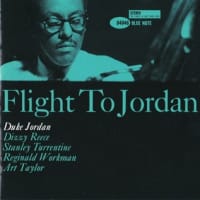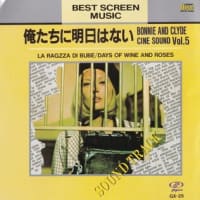16世紀を生きた神学者でもある文筆家のエラスムスによる『痴愚神礼讃』(中公文庫)を読んだ。
訳者が、日本語がたくみな沓掛良彦氏で、読んでみようと思った。
はじめに、エラスムスのこと。
宗教改革は「エラスムスが卵を産み、ルターがこれを孵した」と言われる。
エラスムスの書は、汎く読まれ、時代を動かしたのである。
しかし、エラスムスは、あくまで書斎の人・「観照の人」であった。
ルターのように過激な行動に出ることはなかった。
カトリックの中にあっての“体制内改革”を求めた。
それによって、カトリックからも、ルター派からも敵対視されることになった。
『痴愚神礼讃』のこと。
全篇にわたって、痴愚女神による自己礼讃が展開されている。
痴愚こそが、はかない人生を過ごす人間に幸いをもたらしていると。
愚かさやうぬぼれは大切であると力説される。
それによってこそ、生の喜びもあると語られる。
愚かな者、小さい者は祝福されるのが世の実相と指摘される。
もっともらしく、偉そうに、清廉潔白ぶっている者にろくな者はいないと。
そして、人間社会の滑稽さが諷刺される。
権力者が揶揄される。
聖職者の実態が暴かれ、嘲笑される。
世俗権力と堕した教皇が批判・唾棄される。
エラスムスの鋭い目と言説は、諷刺によって、世のありのままの姿を明らかにする。
その語りは、痛快である。
ただ後段になると、いささかトーンに変化がでる。
イエス・キリストの真の教えは何かなどの堅い話が出てくる。
少しまじめになってしまっている。
イエス・キリストは、愚かな羊をめでたことが指摘される。
これはいい。
また、キリスト教徒の幸福は、一種の狂気と痴愚にほかならないと指摘される。
これもいい。
『痴愚神礼讃』の紹介ができればと思ったがが、どうもうまくかけなかった。
以上の、断片から、中味がうまく推察されればと思う。