電脳六義園通信所別室
僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか
【再掲『まる子゛と清水』(14)】
【再掲『まる子゛と清水』(14)】
雪が降るのだ

清水に雪は降らない。とはいえ、何十年に一度くらい冠雪を記録することがあるようだが私は一度も体験していない。それほど温かい土地なのだ。小学生の頃うっすらと銀世界になったことがあるらしいのだが、残念ながら私は清水にいなかった。後日、従弟にその時の写 真を見せてもらったが、見慣れた清水が全く違って見えてとてつもなく面白かった。雪国の方には申し訳ないが、温暖な地方では、雪というのは驚くべき環境芸術である。
『特製ちびまる子ちゃん』第 2 巻第 8 話、まる子は清水市民会館へ「山口百恵ショー」を見に行く。百恵ちゃんが本当にいる、しかも「清水市民会館」のステージ上に。まる子の感動がよくわかる。10 歳年上の私も同じように「清水市民会館」に来た「スター」に胸を熱くしたことがある。「ちあきなおみショー」である。どういう経路でチケットを入手したかは失念したが、初めて清水で見る「生のスター」にかなり興奮して一人出かけて行ったのだ。
伴奏が始まり「ちあきなおみ」の歌声が聞こえるのに、ステージに本人の姿が無い。レコードをかけているのかと思っていたら、なんと私の席右側の通 路扉を開けて「三度笠姿のちあきなおみ」が歌いながら出て来たのには驚いた。「清水の次郎長」に引っかけたファンサービスだったのだろう。なんと「生きてるちあきなおみ」が目の前を太股もあらわな若衆姿で歩いているのだ。私は興奮して持っていたカメラでフィルム 6 本をたちまち撮り尽くし、後に母親から「馬鹿」呼ばわりされることとなった。
二度目に間近で「清水にいるスター」を見たのは「森進一」だった。なんと、私の通 っていた高校の敷地内で映画のロケがあったのだ。体育の授業中も撮影風景を横目で見ながら気もそぞろ、終業ベルが鳴るや否や私たちは「森進一」の元へ駆けつけたのだった。映画は歌謡映画だったらしく、「森進一」が歌いながら松林を歩くシーンを撮影していた。「ある日」という 3 文字の言葉を「森進一」が「あはるひ~」と例の声と形相で歌うシーンを何度も何度も撮影しているのを見て、映画というのは大変なもんだと感心したものだ。準備のいい奴がいてポケットに太書き用マジックを忍ばせていたのでサインしてもらおうということになったのだが、色紙などある訳なく、全員体操用シャツの背に「森進一」とサインしてもらった。その後卒業まで私たちは背中に「森進一」と書かれたシャツで体育の授業を受けることになった。おかげで、今でも「森進一」ファンである。
私は行けなかったが、清水市民会館で「郷ひろみ」ショーが催されたこともあった。その夜、静岡放送のラジオにコンサートを終了した「郷ひろみ」がゲスト出演していた。アナウンサーが、
「コンサートで清水市に行かれたそうですが、どんな印象でしたか?」
などと聞くので「どきっ」として聞いていると、
「だははは、いいですねぇ、哀愁があって。だははは」
などと言っているのである。あ、あ、あ、あいしゅう?「哀愁」って「物悲しい」って事だぞ。清水市民として「清水は物悲しい町である」な~んて、ぜ~んぜん感じたことないぞ。怒り心頭に達した私は、コーラをがぶ飲みしてラジオを消したのであった。

いつの事だったか、芸能人ではないが、「富岡多恵子」という女流作家が清水に来るというので大人たちが大騒ぎしていたことがある。なんでも、全国の港町を訪ね歩いて、エッセイにまとめるため清水にもやって来るというのだ。地元新聞も大騒ぎしていたような気がする。後日新聞か何かで彼女が清水について語ったことを読んだ時のショックは忘れられない。記憶の中の概略はこうだ。
“清水という町は天然の良港を持ち素晴らしい自然条件の下で発展して来たが、とうの昔にその恵みを受けることを自ら放棄してしまったようだ”
気のいいだけが取り柄の清水の大人たちに囲まれてのんびりと育った私には衝撃的だった。本当にその通 りだと思った。だが、そんな事をズバリと指摘する大人はまわりにいなかったのである。袖師や折戸あたりがいつの間にか海水浴不能になっていた。アサリや小鯵が油臭かった。巴川の水もどんよりと濁っていた。辺りが一面 銀世界になったように「清水の町」が違って見えたのを覚えている。心の中の哀愁の町に雪が降ったのだ。
(続くのだ)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

【再掲『まる子゛と清水』(15)】
【再掲『まる子゛と清水』(15)】
ケンカだ!
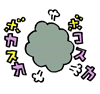
昔の夫婦はしょっちゅうケンカしていたような気がする。亭主が卓袱台をひっくり返して暴れたり、女房が家出したりするのは日常茶飯事だった。どうしてそんな事を知っているかというと、今よりず~っと住宅環境が悪くて、各家の家庭事情なんて筒抜けだったのである。私の親もよくケンカしていた。近所の人が仲裁に入るなんて当たり前で、私の親も良く仲裁に出かけて行った。そして最後はみんなで酒盛りになっちゃったりするのである。
『特製ちびまる子ちゃん』第3巻第1話、まる子の両親が夫婦げんかをする。母は家を出て行くと言い、父ヒロシは出て行けという。姉は父親と一緒に家に残ると言い、まる子は母について行くという。姉妹がいると言うのは便利なものだ。私は一人っ子だったので、こういう局面 は身を引き裂かれるような苦悩を味わったものである。子はカスガイと言うが、私はな~んの役にも立たなかったようだ。結局一方的に母が引き取って故郷清水で生活することになったのである。

こういう夫婦げんかは今でも昔同様、当たり前に行われているのだろうか。それとも昔のような夫婦げんかは減ってしまったのだろうか。いや、離婚率は上昇しているようだから、増えているのだけれど各家庭が密室化しているため他人の目に触れないだけなのかもしれない。それでは他人の目につきやすい「普通 のケンカ」はどうだろうか。路上のケンカという奴だ。
私が住んでいた町はいわゆる盛り場だったので、本当にケンカの多い場所だった。当時は、清水港に入港する船員の数もべらぼうに多かったのだろう。深夜になり、夜明けが近くなっても人通 りが絶えることはなかった。これだけ町が栄えると、子どもの頃からの暴力好きが高じて暴力を商売にしちゃった人とか、いわゆる不良と呼ばれるあんちゃんたちも町を闊歩していたので、気の荒い犬を一つの檻にいれたようで、ケンカが恒常的にそこここで勃発していたのである。
深夜、窓の下で激しい怒鳴り声と物音がするので、怖々覗いて見ると、男たちが殴り合いをしている。そのうち劣勢になったグループの者が、な、な、なんと我が家の雨トイから水を地面 に流す灰色の樹脂パイプを、バキバキと壁からもぎ取って、それで逆襲に転じたのである。ボカスカと叩き合う凄い音がしていた。映画の乱闘シーンなんて歯が立たないリアルさである。さすがに警察が呼ばれ、後日当事者に弁償してもらったのだが、そんなケンカが毎日のように発生していたのだ。清水というのは幕末以来、日本一ケンカの多い町だったと勝手に断言させてもらおう。子どもの目にはそう見えたのである。
しかし、不思議なことにケンカの末に死人が出ちゃったなどという話は聞いたことが無い。すれ違いざまに肩がぶつかったからと言って、いきなりナイフでグサッなんてことは、あまり無かったようなのだ。まず言葉でジャブの応酬、次第にテンションが高まって来たら、まず拳骨でボカスカ、回し蹴りでボカスカ、頭突きでボカスカ、手近なソフトな素材でボカスカ(石や鉄パイプはご法度)、そんな具合に「仁義ある戦い」を繰り広げていたのである。さすが海道一の大親分のお膝元である。
だいたい、ケンカというものはやってみるとわかるが、「仁義ある手順」に沿って行えば、相手を殺しちゃうまでエスカレートしないものなのだ。だんだん顔や手が腫れて痛くなって来るし、「馬鹿なこと、やってるなぁ」というのが自分でもわかって来るのだ。相手の痛みだって、ちょっぴりわかったりもする。よっぽど深い事情がない限り、お互いヘトヘトになった揚げ句、ポケットからナイフやピストルを取り出して…なんて馬鹿なケンカは無いのである。
しかし、最近のケンカは恐い。日本中で、年間何人ぐらい命を落としているのだろうか。問答無用で「グサッ」や「バ~ン」では、そりゃケンカとは言わないぞ。同様に最近の夫婦げんかも恐いのかもしれない。快適で適当に娯楽もある密室で、夫婦が互いの不満を鬱々と蓄積して行ったら、何かのきっかけで弾けて、あとは離婚までまっしぐら、「グサッ」や「バ~ン」にももう一歩なのである。適当に「仁義ある戦い」が年がら年中、勃発している町や家庭の方が安全なんじゃないかと、めっきり静かになった清水の町を歩きながら思うのだ。
(続くのだ)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

【再掲『まる子゛と清水』(16)】
【再掲『まる子゛と清水』(16)】
サッカーを
知らない!

『特製ちびまる子ちゃん』第 3 巻第 5 話、待望の清水エスパルス・長谷川健太くんの登場である。なんとまる子と健太くんはクラスメートだったらしいのだ。読んでみると、サッカー王国・清水の当時の様子がうかがい知れて面 白い。彼らが小学生の頃の「サッカー教育」フィーバーぶりは、中学時代の同級生が清水市立辻小学校の教員をしている時代にいろいろ聞いていたのでだいたいわかる。優れた選手が輩出されて当然である。で、いったいいつごろからこんなにサッカーが盛んになったのだろうか。
私は 6 年間東京の小学校で過ごしたが、子どもの遊びといえば何と言っても「野球」だった。休み時間に野球、放課後に野球、休日も野球と、明けても暮れても野球ばかりやっていたのだ。サッカーをしようなどという奴はぜ~んぜんいなかったのである。
ところが清水に戻ってみると、野球をやる奴なんか全くいない。休み時間の遊びはサッカー、放課後の遊びももちろんサッカーなのである。で、困ったことに、私はサッカーなんて全然やったことがないのだ。ルールも相手のゴールに球を蹴り込むこと、手を使ってはいけないことぐらいしか、ほとんど知らないのだ。それにひきかえ、地元小学校出身の級友たちは皆サッカーを良く知っているし、実際とても上手いのである。まる子や健太くんが幼稚園に通 っていた頃から既にこの有り様だったのだ。
「いなかっぺ」とか「田舎者」とかいう言葉は、都会人が地方出身者を揶揄する為だけにあるのではない。何につけ「ルール」を知らないと「田舎者」ということになるのだ。私は東京からの転校生扱いだったが、ことサッカーにおいては「田舎者」だったのである。
東京の子どもは野球をやっていて「フェア」と「ファール」の判断について良く口論をした。守備側のチームは、
「ファールで走るはいなかっぺ」
と、囃し立て、攻撃側のチームは、
「それを言うのは●●人」
と、やり返すのだが、この「●●人」はひどすぎてとても書くことができない。私は差別的だという理屈をこねて過度の言葉狩りをするのは決して好まないのだが、これは論外だと思う。是非撲滅したい言い回しだと思う。
清水では「いなかっぺ」のことを「田舎っさん」、子どもはツヤつけて「いなかっさー」、それを略して「かっさー」などと言っていたが、私はまさしくそれだったのである。全く弁解の余地は無い。サッカーに関して私が「かっさー」であることが知れ渡ると、私に与えられるポジションはバックスばかりになった。どうやら球を蹴りながら来襲する敵を、阻止するのが役割だということがわかって来たので、敵が攻勢に転じると素早く自陣奥深くに駆け戻って守備に備えるのだが、仲間たちは、
「馬鹿、もっと上がれ上がれ」
などと理解に苦しむことを言うのである。今ならよくわかるのだが、バックラインを上げて相手のオフサイドを誘えという意味だったのだ。遊びなのに、なんと彼らはオフサイド・トラップなどを駆使していたのである。
なんとか汚名挽回の機会を窺っていたのだが、その機会がついにやって来た。ポジション取りも知らないので好き勝手に走り回っていたら、こぼれ球を拾ってしまい、しかもゴールとの間にはキーパーしかいないのだ。猛然とドリブルでゴールに向かって走って行く私には「オフサイド」の声なんか耳に入らない。ドッキン、ドッキンと鼓動の音が聞こえるだけである。相手のキーパーもヘラヘラ笑って立っているだけである。「ここだっ!」と思ってボールを蹴ったらとんでもないコーナー方向へ飛んで行ってしまった。しまったと思って、照れ笑いしながら振り向くと、全員仰向けになって足をバタバタさせて笑い転げていたのである。
こうして「かっさーの神様」としての私の名は不動のものとなったのであった。

(続くのだ)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

【再掲『まる子゛と清水』(17)】
【再掲『まる子゛と清水』(17)】
別れ道
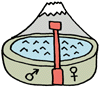
江戸時代の銭湯というのは入込湯といって男女混浴だった。老中松平定信の「男女入込停止」の触書とか、老中水野忠邦の「浴槽に板仕切りをつけろ」の命とかが出されたこともあったけど、明治の男女入込禁止令が出るまで銭湯では他人同士の男女が一緒の風呂に入っていたのである。
『特製ちびまる子ちゃん』第 3 巻第 9 話を読むと、小学校3年生のまる子は父ヒロシと一緒に風呂に入っていたようだ。ああ、良かった。実は、私も小学校3年生まで母と銭湯に入っていたのである。
清水というのは銭湯の少ない町だと思う。東京で私の住んでいた地域では、各丁目ごとに最低1軒の銭湯が存在していた。まあ、自宅に風呂のある級友なんて裕福な自営業の、ほんの一握りの奴しかいなかったのだから当然である。しかし清水のような港町に銭湯が少ないのは不思議なことだ。以前福岡県若松市に山福康政さんの個展を見に行ったら、この港町、銭湯がやたら多いのにびっくりした。港湾労働に携わる人が多い町は銭湯も多いのだ。しかし、清水と来たら私の知っている銭湯は島崎町と万世町に各一軒、それもとうの昔に廃業してしまっているのだ。港で働く人たちは不便なのではないかと心配になる。
実はまる子の家の通りを挟んだ向かいのブロックは法岸寺という大きなお寺があるのだが、その寺の敷地内に「法岸寺湯」という銭湯があったのである。私も何度か入ったことがある。この寺、地域活動に熱心で夏休み中などは本堂のご本尊の前に白い幕を張って、無料映画大会などを催したりしていた。私が子どものうちに廃業されてしまったのでまる子は知らないかもしれない。
さて、小学校 3 年生まで私は母と一緒に女湯に入っていたのだが、ある日突然、母から「 4 年生になったら一人で銭湯に行け」と申し渡されたのだった。考えてみると小学校 3 年生から 4 年生への時期というのは実に微妙な年ごろで、3 年生後半あたりから私は女性のからだが気になり始めていたのだ。

一つは、母から赤ちゃんはお母さんのお腹から生まれると聞いていたのだが、経産婦らしい女性のお腹を見ても割れた後が残っていないのが不思議だったのだ(それじゃぁ桃太郎の桃だ)。そして、もう一つ。女性は「子ども」「おとな」「年寄り」の3タイプに分類していたのだが、「子ども」と「おとな」の中間の人がいるということに気づき始めたのだ。そして、その中間の人たちというのが、実は小学校の廊下ですれ違う上級生のお姉さんたちであるということが、頭の中に立ちこめていた湯気が晴れるようにわかって来たのだ。そんなことを湯船の縁に頬杖突きながら考えていた私の視線に母が気づいて、独立を申し渡したのかもしれない。
4 年生になって今日から一人で銭湯へ行けと言われ、一人風呂敷に包んだ用具一式を抱え銭湯に出かけて行った。初めて一人で銭湯に入るというのは不思議なものだ。自分で手順を決めないと物事が進まないのである。湯船につかっていても、もう少し暖まっていなさいとか指図してくれる人がいないし、シャンプーとからだ洗いどちらを先にするかも自分で決めなければならない。蛇口が塞がっていると、お湯を使わせてくださいという勇気が無い。大人に囲まれて自分のからだの小ささが心細く思われたりするのだ。
いやはや、一人で銭湯へ行くと言うのは疲れるものだと思い知った。
翌日、母が真っ赤な顔をして、こっちへ来いと呼ぶ。
「あんた近所の笑い物だよ。昨日一人で女湯に入ってたんだって?」
そうか、一人で銭湯へ行く時は男湯に入らなければいけないんだ。しみじみ、今日から晴れて男の仲間入りするのだなぁと感慨深い 4 年生の私であった。
(続くのだ)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

【再掲『まる子゛と清水』(18)】
【再掲『まる子゛と清水』(18)】
は何処へ
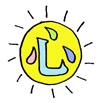
小学生時代、学校に行くのが憂鬱になるほど嫌いな学科というのがあっただろうか。私は「習字」の時間が嫌で嫌でたまらなかった。「算数」も、「理科」も、「音楽」や「図工」だって嫌だと思ったことのない我慢強い子どもだったのに、「習字」とだけはどうしても相容れなかったのだ。
だいたい、教師が何を生徒に求めているのかが、どうしても理解できなかった。お手本通 りに書こうと努力すると、もっとのびのびと書けと言われるし、のびのびと書くとお手本をよく見なさいと言われる。今度はなかなかうまく書けたなと思っていると、朱筆で訳のわからない線をぐにゃぐにゃ上から書かれたりするのだ。いつも、屈辱的な授業が早く終わることばかりを願っていたし、「習字」で良い点を貰おうなどと思ったことすらなかった。
そんな私だが、レタリングは好きだった。なぜ小学生がレタリングなどをやっていたかというと、当時、母親が新聞広告の「家庭で楽しみながら高収入」という宣伝文句に引かれてレタリングの通 信教育などを受講し始めてしまったのだ。定期的に課題が送られて来て、送り返すことを繰り返す教程が延々続くのだが、自分で上手くできない母は、図工が得意な私を身代わりにして受講させていたのだ。ひどい話である。
ところがやってみるとこれが楽しい。印刷に使用されている明朝体やゴシック体が面白いように描けるようになるのだ。おかげで私はレタリングが得意になったが、替え玉 受講を終了した母に「家庭で楽しみながら高収入」な仕事はついにやって来なかった。そういうものだ。

『特製ちびまる子ちゃん』第 4 巻第 3 話、まる子は冬休みの宿題「書き初め」で苦労する。課題は「おとし玉 」である。使用人に書かせたものを提出した花輪君は「銀賞」を貰い、おとし玉袋の文字をまねてレタリングしたまる子はクラスの笑いものになる。
私も「書き初め」の宿題は大嫌いだったので、いつも適当に済ませていた。ところが一度だけ本気で賞を貰いたいと思ったことがある。忘れもしない1963年、東京オリンピックの前年である。
その年、日本中は「外国から大切なお客様をお迎えする」を歌い文句に国民挙げてのオリンピック馬鹿フィーバーを繰り広げていた。その一環として小学生の書き初めで優れたものを外国人選手全員にプレゼントするという企画が持ち上がったらしい。課題は「美しい心」の四文字である。当時の子どもとしては「ガイジン」と聞いただけでドキドキしてしまうし、しかも「オリンピック選手」という「一流のガイジン」が日本の子どもが書いた「美しい心」を「外国」に持ち帰って床の間(床の間の無い家に育ったので外国にも床の間が有るものと思っていた)に家宝として末長く飾るなんていう幸運を逃してなるかと、誰もが思ったに違いない。
半紙を大量に買い込んで「美しい心」を次々に書いてみたのだが、これがなかなか難しい。特に「し」の字がうまく書けないのだ。まる子も「し」で苦労していた。すっと流してしまうとナメクジみたいだし、ぐいっと丸めると鼻みたいで間抜けに思えるのだ。見兼ねた叔母がお手本を書いてくれたのだが、さすがに大人は上手いなぁと感心してしまった。さっそく真似て書いていたのだが、やがて飽きてしまい一番うまく書けているものに署名をして提出することにした。今思うと、それは叔母が書いたお手本そのものだったような気もする。やがて、その作品は銀賞なんぞを貰ってしまって、朝礼で表彰されることになってしまうのだ。花輪君の替え玉 受賞と同じパターンである。この賞状というのが立派なもので、亀倉雄策さんデザインの東京オリンピック公式ポスターと共通 デザインになっていて、金賞は金、銀賞は銀と色分けして印刷してあるものだった。多分清水の生家の物置に今でもあると思う。
後日談だが、授賞した作品を外国人選手にプレゼントする企画は結局実現しなかったらしい。「ガイジンは日本語が読めないので有り難がらない」というのが教師の説明だったが、日本語が読めないことぐらい最初からわかっていそうなもので、子どもながらに間抜けな話だと思った。しかし実はもっと深い事情があったのかもしれない。たとえば、ほとんどの入賞作が、オリンピック記念にと張り切った親が替え玉 で書いたもので、そんなものを子どもが書いたと偽って渡し、後で発覚したら国際的恥辱になるとの判断があったとか…。
しかし、あの何千、何万という山のような書き初め「美しい心」は今何処に有るのだろう。どこかに保管されていたのが発見されて「ドキュメント東京オリンピック~あの小学生は今~」なんて番組が企画されないことを祈りたい気分である。替え玉 なんて、間違ってもやるもんじゃない。人間「美しい心」は大切なのだ。
(続くのだ)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

【再掲『まる子゛と清水』(19)】
【再掲『まる子゛と清水』(19)】
の財布

幼い頃、祖父の財布というのは小さな謎だった。両親の懐具合は、夫婦喧嘩の立ち聞きや、誰に聞かせるともない母の愚痴の内容で、おおよその見当はついたものだが、引退して働いてもいない祖父の財布に、どうしてお金が湧いて来るのかが不思議だったのだ。年金だとか、恩給だとかの存在を知らなかったのだから仕方がない。
祖父は良く「小遣いをやるから肩を叩け」とか「腰に乗れ」とか、孫に命令した。思うに、祖母は身の回りの世話を口実に良く孫に触っていたが、祖父というのはそんな回りくどい事をしないと自分の孫に触れなかったのかもしれない。身の入らない肩叩きを終えると財布から50円などという大金をくれたりするのだが、当時一日の小遣いが10円だったから子どもには大したお金だった。やはり、おじいちゃんはお金持ちなんだなぁと、思ったものである。
祖父は風呂上がりの夕方、越中ふんどしに浴衣を羽織って巴川の土手をゆらゆらと散歩するのが好きだった。誰も見ていないから恥ずかしくないものの、「あんな格好で歩いているじじいがお金持ちであるはずがない」と思える一瞬であった。
祖父は時々、私を連れて市内に嫁いだ娘を訪ねることがあった。孫でも連れてでなければ行きにくかったのかもしれない。子どもと年寄りが歩いてなど行けない距離なので、ハイヤーでも呼べば良いのにと、その度に思った。都会では庶民はタクシー、お金持ちはハイヤーという使い分けになっていたが、地方都市ではタクシーという呼び名は無くてすべてハイヤーだった。清水で営業車が屋根に電気看板をつけて街を流すようになるのはずっと後年のことである。
だが、バスで行くというので「やっぱりおじいちゃんは貧乏なんだな」と思った。まだ自家用車が庶民の夢だった時代、道路は未舗装路が多く、バス停のある国道 1 号線までは農道に毛の生えたような田舎道を随分歩かなければならなかった。当時清水市郊外では梨を栽培している農家が多かったようで、その道づたいにもたくさん梨畑があった。祖父は道に一番近いところから良く熟れていそうなものをもいで、「おりゃあいいけど、われ(お前)は、やっちゃあ駄目だぞ」と言って私にくれたものだ。最近は「幸水」や「豊水」などの新品種が出まわっているが、当時は「長十郎」だった。梨というものは冷やさない方が美味しいと私はこの頃から思うようになった。
バスを乗り継いでさらに延々田舎道を歩くのだが、祖父は何も買ってくれない。「おじいちゃんは貧乏だから仕方ないか」と、ふてくされて歩いていると、「やい(おい)、この葉っぱ何だかわかるか」と聞くので「知らない」とボソッと答えると、「こりゃあ、タバコの葉っぱだ。戦争中はこけぇら(この辺)はサトウキビも作ってただよ」などと教えてくれる。私は祖父の昔話が好きだった。

親戚が持たせてくれるお土産がまた大変。畑でもいだトウモロコシや枝豆を風呂敷包みで山ほど持たされるのだ。貧乏人の悲哀倍増である。更にふてくされて、清水市街にさしかかると祖父が急に「やい、『みどり寿司』に寄って寿司でも食ってかざあ(食べて行こう)」と言うではないか。「やっぱりおじいちゃんはお金持ちなんだ」と嬉しくなった。清水銀座の『みどり寿司』は、私の憧れの店だったのだ。
『特製ちびまる子ちゃん』第 4 巻第 6 話、まる子は祖父友蔵に連れられてお寿司屋さんに行く。その日年金 8 万円を手にした友蔵が、孫を喜ばせようと高価な玩具を買い与えた上、寿司屋で大盤振る舞いをし、金が足りなくなり玩具屋に商品を返しに行くという哀感溢れる話である。玩具屋は多分『富岡屋』だろうが、お寿司屋さんは何処だったのだろう。
『みどり寿司』に入った私はスタスタとカウンターに座り、祖父にテーブル席に連れ戻された。やっぱり、おじいちゃんはお金持ちではないらしい。後に母は祖父から「われ(お前)は、どういう子どもの育て方をしてるんだ」と、こっぴどく叱られたらしい。
その祖父も私が高校三年生の秋、晩酌中に倒れて還らぬ 人となった。死んでみれば、裸一貫から身を起こし、13 人もの子どもを育て上げ、家や工場、土地などを残したのだから、なかなかお金持ちだったのだと思えなくもないが、何の道楽もせず、年に一度の夫婦の旅を楽しみにし、無駄遣いを決して許さず、越中ふんどしで川の様子を見ながら散歩していた祖父が清貧の人のように思えてならない。母性というものは、祖母から母に、母から妻にと受け継がれ、どこか通 底するものをもっていつも私と共にあるような気がするのだが、ぎこちなくしか触れ合えなかった祖父への思慕と喪失感は年をとるにつれ増して来るのが不思議なのだ。
(続くのだ)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

【再掲『まる子゛と清水』(20)最終回】
【再掲『まる子゛と清水』(20)最終回】

子どもの頃というのは満天の星のごとく、世界がたくさんの不思議で満たされていたわけで、その内の一つがお金持ちに関するものだった。大人たちのように、「どうしてあの家はあんなに金持ちなのか?」などという、やっかみ半分の「汚れっちまった不思議」ではなくて、私の不思議は「日本のお金持ちってどうして幸せそうじゃないのか?」というものだった。
テレビでアメリカ製のテレビドラマなどを見ていると、アメリカのお金持ち(今思えばあれで極めて庶民的だったのかも)って、とても幸せそうだった。何でも知ってる素敵なパパと優しくて奇麗なママがいて、子どもたちはみんな金髪なのだ(やっぱ金は金持ちなのだ)。みんなででっかい車に乗ってピクニックに行ったり、でっかい犬と一緒に庭で芝刈りしているパパの横を転げ回ったり、バーベキューででっかい肉を串刺しにして食べちゃったりするのだ。誕生日やクリスマスのケーキだって山のように巨大なのである。それにひきかえ、日本のお金持ちがちっとも幸せそうに見えないのが不思議だったのだ。
「特製ちびまる子ちゃん」第 4 巻第 10 話、まる子は大金持ち花輪君の豪邸にヒデじいのお見舞いに行く。どう見てもあんな豪邸が清水にあったとは思えないのだが、花輪君に実在のモデルって居るのだろうか。
ただ清水にもお金持ちの家が集まっている地域が確かに有った。なんでお金持ちかというと、その一角に足を踏み入れると行けども行けども塀のある家ばかりなのである。
「あの家は金持ちだってね」「へえ~」
ってなもんで、木賃アパートや道路にいきなりドアのある家に住んでいた私たちにとって、塀で囲まれた家に住んでいるというのはお金持ちの証拠だったのである。そのあたりを歩く時は門の内側をのぞき込むようにして、どんな人がどんな暮らしをしているのかみんな興味津々なのだが、絶えて人の気配が無いのだ。なんか家の中で息をこらして肩身の狭い思いをして暮らしているように思えるくらいひっそりかんとしているのだ。
あんなに広い庭が有ったら、芝生の庭に縁台でも出して近所の人を集めて、スイカを食べたり花火をしたりビールを飲んだり(明らかに貧乏人の小倅の発想である)、もっと幸せを満喫すればいいのに(余計なお世話である)といつも不思議に思っていたものだ。
夏になると私たちは家の裏に転がっているミカンや桃やパイナップル缶詰の空き缶(貧乏人丸出しである)を拾って来て板切れに釘で打ちつけ、空き缶提灯を作った。その中にロウソクを立てるとちょっとやそっとの風では消えないし、開口部を横にするとかなり遠方まで照らすことができたのである。

日が暮れると皆で出掛ける場所は決まっている。お金持ちの屋敷街である。なにせ、真っ昼間から静まり返っているのだから、夜は暗くて全く人影すら無いわけで、絶好の肝試しの場所なのである。「おい、オバケ屋敷のほうへ行こうぜ」などと言うものもいた(ひどい話である)。
ひっそり静まり返ったレンガ塀の角々から泥だらけのランニング姿のガキどもが、顔の下のほうからロウソクを照らして「ギャハハハ~」と恐ろしい顔を出したり引っ込めたりしているお屋敷街というのは、ハロウィーンの様でもあった。そして、それでもうるさいと怒りもせずにひっそりと暮らしていた裕福な人たちは極めて日本的なお金持ち像であったのだなぁと、タレントや文化人の馬鹿パーティーをテレビで見るにつけ思うのだ。
(おしまい)
◉
(『清水目玉焼』アーカイブに加筆訂正した 2000 年 の連載再掲)

| 次ページ » |








 ▶︎
▶︎




