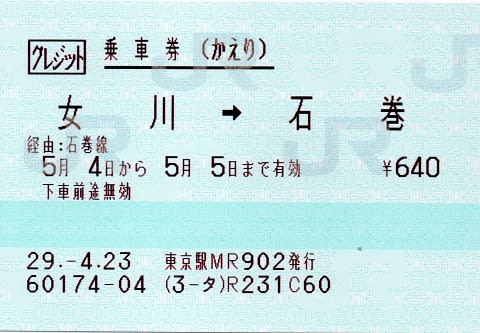仙石線は東北最大の都市、仙台と石巻を結ぶ路線なので、線路は複線と思ったら・・・東塩釜を過ぎると単線でした。

高城町。松島海岸は仙石線の駅、塩釜は東北本線の駅。東北本線と仙石線、ずーっと平行線だったけれど、交差するようになったのは2015(平成27)年5月30日から。まるで平行する総武線と京葉線だけど・・・交差するところは武蔵野線の西船橋~南船橋。総武線が京葉線に乗り入れることは滅多にない。こちらは2015年から東北本線の塩釜を出ると、仙石線に乗り入れ、高城町。

「上り仙台行きと交換するため、〇〇分停車します。〇時〇〇分発車します」とアナウンスがあったようだけど、耳からは情報が入らないので目に見える時刻表で数分止まることをしっかり確認し、ホームに出てみました。

駅本屋。ここでも、suicaエリア。スマホで調べてみたら、仙石線はすべてsuica対応。つまり石巻までエリアなんです。

1番後ろの車両だけど・・・

元の番号がうっすらと見えます。

今の番号は 仙センM10編成クハ204-3110だけど・・・山手線時代はサハ205-54。
サハといえば、運転席やモータも付かない付随車のはず、仙台で活躍するため、サハ205を運転席付きに改造し、改番。
新しくなったとはいえとも、国鉄フォントで重ね書き。

本家は富山県庁所在地の駅。ここは陸前を冠して、富山。漢字は同じだけど、読みが違う。本家は「とやま」、こちらは「とみやま」。

海岸沿いのため、新しく施工した防波堤。

これも津波が来ても防げるように後から取り付けたもの?

東名駅。東名高速道路の「とうめい」ではなく、「とうな」。

このあたりでも津波の被害があったかも知れませんが、新しい家が建っているのが見えます。

野蒜駅。2011年3月11日、東日本大震災が起きる数分前に野蒜駅を仙台行き上りと石巻行き下りを交換し、発車。両者とも激しい揺れに見舞われ、緊急停車。上りは野蒜から700m地点で停車、下りは600m地点で停車。
上りは避難指定地の野蒜小学校の近く。仙台の指令担当者からそこに避難するようにと指示があり、体育館へ。しかし、1階部分は津波に襲われ、避難した乗客が亡くなられた。
下りは野蒜から600m地点で幸いにも高台だった。「とどまった方が安全だ」。地元に住む年配の男性客が、乗客を外へ誘導しようとした若い車掌に助言。津波の襲来は免れたが、濁流にのまれる建物や車が窓越しに見えた。その時の乗客60名が一晩、車内で明かし、翌日、救助。

東日本大震災の数分前に野蒜を出た下り電車は無事だったのに、上りは津波で押し流され、コのように折れ曲がった。上りと下り、運命が分かれました。