本書の構成は以下の通りです。
まえがき
1 立ち現われ一元論
2 過去がじかに立ち現われる
3 過去透視・脳透視
4 「思い」の立ち現われ
5 過去の制作
6 生と死
あとがき
それなりの期待感をもって開いた本なのに、読み始めてまもなくから、何だかつまらないなぁ・・となった。(自分の理解力不足を棚に上げて!) 大森荘蔵って、竹を割るようにスッキリ明快な論理の人と思っていたのに、立ち現われ だなんて曖昧な語を鬼の首でも取ったかのように振り回していたのか・・ そういう考え方(?)を選んだのは貴方(大森)の勝手でしょ・・と言いたくなるほどに。
中島義道は、少なくともこの本では平易な言葉遣いを守っているけれど、揺れたり、捻じれたり、先走ったり、逆行したりする文脈を追っていると、イライラし、ウンザリしてくる。
それでも何故か、どんどん読み進んでいった。靄の向こうから私を引き込む深淵のようなものが感じられたからだろうか。
事態が急展開したのは「5 過去の制作」。倦んでいた私の姿勢が正された。こういう経緯だったのか・・大森荘蔵の哲学は。
~「過去の制作」後の一連の論文(その思索の集大成『時間と自我』が1992年に刊行されます)によって、大森哲学は大転回を遂げます。~過去の出来事は「実在的過去から立ち現れる」というのではなく、「<いま・ここ>で言語的に制作される」という転回です。
不勉強な私は、大森荘蔵の著書としては「時間と自我」(2013.2.12記事)しか読んでいないのだ。お恥ずかしい限り。
まず「私]がすでに成立していて、それが世界を制作するのではなく、Xが~世界を制作すると同時に、(いわば反対側に)自分自身を「私」として制作するのです。
「6 生と死」で、大森荘蔵という師に対する著者の、切々たる情愛が一挙に膨らみ、爆ぜんばかりに感じられました。
実在的過去が崩れること、それは、先生にとって~この宇宙がまったく「空無」になることであり、まさにそこに見えてきたのは「奈落」以外の何ものでもないのです。
~たとえ生きるために「程々の実在論」にすがらざるをえないとしても、その底には「空無の実在論」がぽっかり穴をあけていること、先生はこのことを恐ろしいほど実感していたのではないか、と思われます。
~「立ち現われ一元論」とは、世界を自分の「うち」に呑み込んでしまう試みなのではなく、逆に、「自分を世界へ解放してしまう」試みなのです。~しかし、こうした試みが完成したかと思われた瞬間に、先生は足元をすくわれる。~過去は、もしかしたら空無なのではないか? いや、この~現在すら、もしかしたら空無なのではないか?
ツマラナイと思い、ウンザリしていた 立ち現われ が、私にとって懐かしいもののように思えてきました。
~先生は~空無に身をゆだね、「まったく新しい哲学的言語を作成する」道が開かれていることを知りながら、その道を歩むことを断固として拒んだようなところがある。~俗衆とともに(?)、最後まで苦しみ抜こうとする覚悟のようなものがある。その意味で先生は~殉教者であろうとした。
南木佳士の書評(6/8東京新聞)は魅力的だったけれど、・・心情を表に出さぬ著者の姿勢 云々のくだりは当たらない。抑え切れるものではなかっただろう。
しかし・・空無の「奈落」を突き抜けて「向こう側」に至る道をたどること が、哲学によって果たして可能でしょうか? 中島義道は、自らがその道をたどるのだ・・と言いたいのでしょうか? 人は、宗教に拠らずに救われることが可能なのでしょうか?












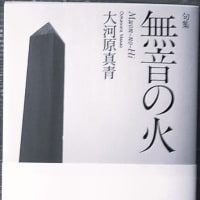

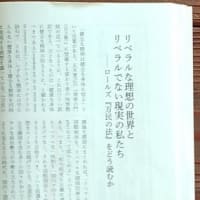
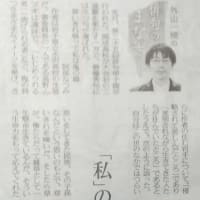
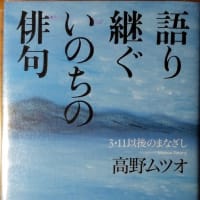
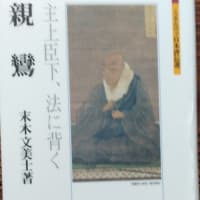


のっけから、ということになりますが、記事にある通り、この本を面白いと感じる読者はあまり多くはないのではないかと思います。私も、それほどのヴォリュームを持つ本ではないにもかかわらず、ところどころかなりの退屈さを押し殺して最終ページにたどり着きました。少なくとも、大森荘蔵の著書・論文をある程度の量読んだことがあり、かつ、現在でも大森哲学に関心を持ち続けている者でなければ、この中島義道の本を読み通す意義を見出すのは難しいのではないでしょうか。私も、そのような者ではありません。そして、率直に言って、そのような変わり者は、仮に現代の哲学者や哲学徒を見渡すことができたとしても、ほとんどいないのではないかと勝手に想像しております。むしろ、このご時世に、よくこんな売れそうにない本を出版したなと、出版社と編集者の蛮勇に感心しているくらいです。
一方、地味な哲学者(大森のことです)の半生にわたる思索の長い道筋を、一部のテーマではあれ、その諸概念の成り立ちを丹念に吟味しつつ、批判的に論じる(中島のことです)というのであれば、どうしても、こういう、良く言えばけれんのない、悪く言えば退屈なスタイルにならざるをえないのではないかと言う気もします。良質な哲学書というものは、しばしば、何でこんな、重大とはとても思えない小さな主題を、チマチマ、くどくど論じるのか、その理由がわからないという印象を読者に与えるものです。大森の著書も、それが真正の哲学的な思索であるがゆえに、そういう特色があると以前から感じておりました。
もともと、テーマの人間的・人生的な切実さがわかりにくい哲学者の思索を、これまた、癖の強い哲学者が自説をからめつつ論じるのですから、この本の退屈さと面白みの欠如は、むしろ、師弟関係にあった二人の哲学者の知的な誠実さであると考えるべきであるのかもしれません。
あえて、ザックリと非常にラフな読後印象を言うと、この本における中島の大森に対する批判は、二人の哲学的かつ人格的な資質・個性の相違を別にすれば、基本的には、「伝統哲学」からの批判であると思います。ここで言う「伝統哲学」とは、この本の207ページにもあるとおり、デカルト、ロック、カントを経てフッサールに至る「観念論哲学」を指します。ただし、「観念論」という日本語の語感は誤解を与えやすいので、むしろ、〈意識〉の哲学と言った方が適切かと考えます。この本を読んであらためて感じたことの一つは、現代の哲学アカデミズムで活躍している大森の弟子達の多くが、英米系のスマートな分析哲学や科学哲学を専門としていったのに対し(実は師である大森は最後まで独自の哲学を探求し時代の流行に全く関心を持たなかった)、弟子の一人である中島は、もちろんそうした現代哲学の最前線を十分咀嚼しながらも、自身は、独仏系(大陸系)の「伝統哲学」の遺産を自覚的に継承する道を選んだのだな、ということでした。まあ、この種の感想は的外れかもしれませんし、そもそも、哲学とは自分が抱える人生上の問題について我流に追求するものだと考える人間(こうした考えは確かに人生上の真実をついており、大切であることは言うまでもない)には、どうでもよいことでしょう。しかし、それにしても、大森は、初期の頃から、中島がよって立つような「伝統哲学」に対しては、明晰で緻密な、大森一流の説得力のある批判をしてきたはずです。したがって、今回の中島の批判に対する大森自身の反批判を聴くことができないのは、まことに残念なことです。「中島君、そうではありません」と。
実は、中島のこの本を読んで、幸か不幸か、これまで読んできた大森の著作を読み直したくなり、目下、ポツリポツリと拾い読みしているところです。ああ、懐かしい、などと思ったりもしております。それを終えた時点で、本題に入りたいと思っています。
おそらく、次回のコメントでは、中島のこの本の最主要な論点である〈過去の空無性〉について触れた後、宗教と哲学の関係というスーパー・ヘヴィーな重要問題について論じる能力は、酒席の放談は別にして、私ごときは生涯(と言うかたとえ百回生まれ変わっても)持てそうにありませんが、大森荘蔵と中島義道の哲学的・人格的資質の相違について、この本の一読者の立場から、勝手気ままな想像を楽しむことができればと思っております。懲りずに、例のごとく、長くなるかもしれませんが、ご容赦ください。それでは。
中島義道のこの本の主要な論点が〈過去〉の空無性であることは疑いないでしょう。「空無の過去」(P214)について、大森荘蔵と中島義道の考えは、少なくとも結論としては一致しています。まずは、この論点を、今回のコメントの前半に取り上げたいと思います。
ただ、最初に一つ指摘しておきたいのは、中島は、物理学に典型的に見られる「線型(リニア)時間」の虚妄性を執拗に攻撃し、物理学徒(それも素粒子論を専攻していたとびきり俊秀の物理学徒)出身の大森も、晩年の時間論では、この線型時間、すなわち数直線に表象される実数連続体tの虚構性を批判しました。しかし、私見になりますが、〈過去〉の空無性と物理学的時間や年代記的時間(歴史年表的時間)に代表される線型時間の性質は、とりあえずは別の問題として扱うことが可能であり、前者を論じるのに後者の解明が論理的に不可欠であるというわけではないと思います。アマチュアのまことに僭越で無謀な言い方になりますが、〈過去〉の空無性を言挙げするのに線型時間を標的とするのは、議論に不要な混乱を招く恐れがあると考えますので以下では触れません。
さて、中島は、この本の第5章「過去の制作」の最初の節で、大森が、1985年以降、大森哲学固有の従来からのいわゆる「立ち現れ一元論」からの過去理解から、「言語的な製作」としての過去理解へと「コペルニクス的転回」を遂げたと言っています。私は、市井の一読書人として、かつて大森の著作に親しんだ経験がありますが、もちろん大森の著作の全てを読んでいるわけではないので(多くを読んでいるとさえ言えない)、中島のこの主張がどの程度正しいのか判断する能力がありません。しかし、大森が晩年ないし晩年近くになって、〈時間〉をはじめ同じ哲学的テーマを扱っても、思索の重心を移動したのは分かります。大森の最晩年の著作から、「転回」以後の大森の時間論の出発点になったと思われる主張を引用します。
「……何であれ過去性を知覚的に描写することは不可能なのである。過去性の図解などはありえないのである。われわれはやむなく現在風景を代用して過去を図解するほかはない。ではいったい過去性はどのようにして理解されるのか。それこそほかでもない、動詞の過去形の了解によってである。この過去性の言語的了解、つまり過去性の意味はどのようにしてえられるのか。それは人間生活のなかでの無数の言語使用のなかで形成されてきたはずである。」(大森荘蔵「時は流れず」(P48、青土社)
これは極めて明快で正確な指摘であり、大森の時間論のなかから大森の個性を濾過した後にも残る〈時間〉のエッセンスの重要な一側面であると思います。たとえ、そこで述べられていることが、どれほど散文的で一見平板に見えようとも。
私達が〈過去〉の意味を了解するとは、まず第一に、どこどこに「あった」とか何かを「した」という日常言語の過去時制を正しく使用することと表裏をなしているということです。もちろん、また、言葉の時制は、人間が幼時から言葉を学ぶプロセスの中で、過去形・現在形・未来形、さらに進行形・完了形等と一体的に習得されるはずです。こうした意味にとどまる限りにおいて、やや強い言い方になってしまう気がしますが、大森の言うように、また中島が確認したように、〈過去〉とは「言語的な製作」であると言ってもよい。
(このコメント続きます 1)
しかし、ここから、「過去の実在性を否定する」といういかにも哲学者好みの主張に発展すると違和感が生じてきます。上記の大森の著書からの引用は、私達の常識と実感に十分接続するもので、水を飲むように喉を通ります。ここでは、むしろ、その常識と実感に即した「言語了解的時間論」(と言うほど大仰なものではありませんが)の立場から、違和感を表明しておくことにしましょう。
時制としての過去・現在・未来という概念の意味について考えればわかるとおり、過去という概念には、現在から見て「既に無い」、同様に、未来という概念には、現在から見て「未だ無い」という意味が含意されいる。したがって、過去が〈無〉であるということは、過去という言葉の定義(もちろん日常言語の使用から類推・確認される黙示的な定義だが)から論理的に導き出されるという点でトートロジカル(同語反復)な言明であると言うほかはない。つまり自明であり、そこには何の不思議もない。何故、そんなことが哲学的問題になりうるのか? そもそも、過去の事実とは、「今は無いがかつては有った」ことがらを意味するのは子供でもわかることである。過去は実在しないという主張は、「有る」と「有った」という、本来、現在形・過去形の時制に関わる日常言語の文法上の問題を、何か深遠な哲学的問題と勘違いしているにすぎないのではないか。
卑近な例で考えよう。私が、昨夜、一人で寝酒を楽しんでいたおり、ついつい飲み過ぎて手を滑らせ愛用のウィスキーグラスをテーブルから落とし割ってしまったとする。これを、現在(今朝)において想起・回顧する場合、「昨夜テーブルの上にグラスが有った」という過去形命題は真なる命題であり(私が酔っぱらって幻覚を持っていたのでない限り)、「今そのグラスは無い」という現在形命題も真である。ここからわかることは、あることがらが過去に事実として有ったかどうかを問うことができること、すなわち、過去形命題の真偽を有意味に問うことができることと、「既に無い」という意味で過去が〈無〉であることは何ら矛盾することではない、ということである。再び言うが、何故、そんなことが哲学的問題になりうるのか?
〈過去〉の意味を日常言語における過去時制の適切な使用と結びつけて理解する限り、〈過去〉が〈無〉であることは自明であって、そこに何ら「タウマゼイン」(P205)-哲学的な〈驚き〉はない、とする以上の考えは正しいでしょうか。私は、とりあえずは、正しいとしてよいと思っています。しかし、三点ばかり、留保が必要です。
第一は、古典的とも言える哲学的な懐疑論があるからです。この懐疑論によれば、そもそも、過去・現在も含めて、この世界が実在していると判断する根拠がないということになります。昨夜の我が愛用のウィスキーグラスはもちろん、現在私が打っているコンピュータも、それが置かれているデスクも、実在しているという根拠がないという非常識なほど徹底した懐疑論です。このラディカルな懐疑論は、様々な変奏曲をかなででつつ、古くから哲学マニアを熱狂させてきた感があり、確かにその議論は、暇のある或る種の思索的人間を熱中させる面白さがある。しかし、中島については知らず、大森は少なくとも晩年の時間論のなかでは、この類の懐疑論を語っているわけではないように思います。例えば、大森は、先に引用した最晩年の著作において、日常言語における過去形命題の真偽を有意味に問うことができると考えています。ただその真偽を検証する手続きに、過去の実在性は不要であると言っているだけです。しかし、ラディカルな懐疑論は、こうした考えそのものを不徹底、ないしナンセンスとみなすでしょう(まあ、この辺りの事情については本来デリケートな議論が必要でしょうが深入りする準備がありません。今後もありません。)
第二に、先に書いたように、〈過去〉の意味を了解することが日常言語の過去時制を正しく使用することと表裏をなしていることは、〈過去〉のエッセンスの重要な一側面ではあるが、その全てではないということです。例えば、個人の経験と結びついた過去を語るとき、〈記憶〉の重要性を外して考えるわけにはいきません。〈記憶〉は、プルーストを待つまでもなく、それ自体、文学や芸術にとって美しく深いテーマでしょう。しかし、現代を生きる私達にとって忘れてはならないことは、〈記憶〉は、本来、脳内の物理的・生理的プロセスによって形成されるということです。この点については、私は、科学が-もちろん大森が不思議なほど嫌悪した脳科学を先頭にして-、地道に、しかし徹底的に解明してほしいと期待しています。つまり、〈過去〉とは何かの理解に、言語分析は必要であっても十分ではないということです。
第三の点は重要であり、上記の「言語了解的時間論」-と仮に言っておきます-に対する次のような批判です。
言語了解的時間論の児戯に類するたわいのない日常言語分析の是非はともかく、そこでは、〈過去〉の空無性が結論されていながら、何らその不条理性が自覚されていない。〈無〉を前にして何ら〈驚き〉や〈不安〉がないことこそが、実は、言語了解的時間論の欠陥なのである、と。
確かに、過去・現在・未来という時制に関する私達の言語了解について、日常言語の文法・使用法等をいくら緻密に分析したとしても、〈時間〉のエッセンスについて、何か重大なことが言い忘れられている、という感覚は残るでしょう。その言い忘れられた何かが、いかにも哲学者風の、〈無〉を前にしての存在論的な〈驚き〉や〈不安〉であるかどうかは別にしても。要は、この批判では、論理の問題ではなく感受性の問題が俎上にのっているのです。そして確かに、哲学においては、論理の問題だけではなく感受性の問題も重要であるでしょう。
(このコメント続きます 2)
そして、この〈感受性〉という極めて曖昧な概念を媒介として、このコメントの後半の論点に議論を移したいと思います。それは、大森荘蔵と中島義道の哲学的感受性の相違についてです。中島の大森に対する深い人格的な敬意に疑いの余地はないにせよ、この二人の師弟は、両者の著書を読み比べると、哲学内容の相違以前に、対照的と言ってよいほど、哲学的感受性があまりに異なっていることがわかります。これは、おそらく、誰もが感じとっていることでしょう。その中島は、大森について論じたこの本の最終部分で次のように語ります。小零さんの記事にも引用されている個所です。
「これからあとは、ただの私の想像ですが、先生は『奈落』を突き抜けて『向こう側』に至る道をたどること、その可能性を充分察知していたのではないか? 『より強固で確固とした実在論への願望が湧きあがっていた』のではないか?」(P222)
私には、どう考えても、ここで想像されているのは、大森荘蔵の肖像ではなく、中島義道の自画像です。最晩年を含めても、大森の哲学的感受性から考えると、こうしたことはありえない。もちろん、私がこう言うのも想像にすぎません。
以下は、私が考える大森哲学のコアについての極めて乱暴で粗雑なスケッチです。迂回になりますが、大森と中島の哲学的感受性の相違について語るとき、これを外すわけにはゆきません。
私には大森のどの著書を読むときにも聞こえてくる、一つのメッセージがあります。それは、こういうものですが、大森の著書からの引用ではありません。だから、もしかすると、幻聴にすぎないのかもしれませんが。
「〈私〉と〈世界〉と〈現在〉は、一如として有る。それだけは言える。しかし、言えるのはそれだけだ。」
もちろん、「しかし」の前後を入れ替えることもできます。「言えるのはそれだけだ。しかし、それだけは言える。」と。
大森は、この単純なことがらを、禅僧のように言葉を超えた悟りによって得たのではなく、生涯かけて思索し探求し語り続けたように思えます。そう、緻密で明晰な言葉で、繊細に、かつ、骨太に力強く語り続けました。
大森哲学の最大の特色は、知覚や想起など全ての経験が流れ込む、いや、そうした原初的な経験が生じるこの〈私-世界-現在〉以外にいかなる手持ち札も持たず、いわば道具無しの徒手空拳で、〈時間〉だけではなく、〈自我〉や〈他我〉や〈物理的存在〉など様々な哲学的な謎について徹底的に思索したことです。安易な道具を持つことを自らに禁じたからこそ、時に「立ち現れ」などという哲学者らしからぬ言葉を創出したのでしょう。
〈私-世界-現在〉以外にいかなる手持ち札も持たずに思索すること、ここにこそ、大森哲学の最大の魅力と、そしてまた限界があったと思います。少なくとも、その思索の出発点において、大森は、〈私-世界-現在〉を〈超越〉するいかなる存在も認めていません。そして、私の見るところ、思索の出発点だけではなく、その到達点においても、結局、一如として有る〈私-世界-現在〉の圏域を越え出ることはなかったように思います。もう一度書いておきましょう。
「〈私〉と〈世界〉と〈現在〉は、一如として有る。それだけは言える。しかし、言えるのはそれだけだ。」
以前にも書きましたが(2013年2月12日付記事に対するコメント。本、哲学ジャンル)、私は、大森の著書からは、一読者として随分学ぶところが多かったと感じています。上記の大森哲学のメッセージは、結論としてのみ受け取ると単純に見えますが、そこに至る強靭な思索の道筋は、今でも、深い哲学的思索の一つの見事な典型であると思っています。しかし、私自身は、違う道筋を探ることに決めました。ここでは詳述する余裕はありませんが、大森の思索の道筋からは、私にはどうしても受け入れがたい不自然で奇怪な結論がしばしば導き出されるからです。そして何よりも、結局、私自身の人生上の重要な問題を解決しないからです。しかし、言うまでもなく、それは私自身の問題であって大森の問題ではありません。
(このコメント続きます 3)
ここからは一読者としての全くの想像になりますが、大森がその徒手空拳の哲学的思索に苦しみを感じなかったわけがないと思います。しかし、大森が、〈私-世界-現在〉をはるかに超えた「向こう側」を目指していたと考えることは、私にはできません。その著書の明晰な言葉を素直に辿っている限り、大森が「向こう側」を憧れていた形跡すら認めるのは難しい。大森哲学の基底にあると想像される感受性の質を考えると、そのように推定されるのです。
その感受性とは、どのようなものであるのか。自前の未熟な概念になりますが、あえて言うと、存在に対する根源的な〈親和性〉とでも言うべきものです。大森は、確かに、中島の言うように、生の無意味さと不条理性、そして晩年には〈無〉の「奈落」について語っています。しかし、私は、大森は、そのように語っているときでも、存在に対する天与の〈親和性〉から見捨てられることはなかったと考えています。これは少し言い過ぎになるかもしれませんが(つまり撤回する用意もありますが)、こうした感受性を持つ者は、この世の「地獄」にあってさえ、本心から、超越的なものに〈救済〉を求めることは、おそらく、ない。その感受性は、何よりも、大森哲学のなかで最も深い輝きを放っている、「天地有情」論に現れています。
一如として有る〈私-世界-現在〉に映じる天地有情についての、大森の数々の哲学的叙述は、他の哲学には類例のない美しさを持っており、読む者に新鮮な驚きを与えます。それは、私には、ほとんど、松尾芭蕉の「奥の細道」を哲学的叙述として語り直しているようにさえ感じられることがあります。しかし、もちろん、それは詩ではない。一見風変りではあるが、透徹した論理に貫かれたに明晰な散文で語られる哲学なのです。小零さんがこの本を読むきっかけになったと言われている南木佳士の書評をインターネットで読みましたが、そこでも大森哲学における天地有情論の魅力について語られていました。
「無情の風景に情を感じるのではない、風景そのものが既に有情なのである。」(P196)
中島はこの天地有情論や風情論を軽くあしらっていますが、そもそも、天地有情や風情を感じとる感受性を持たずに大森哲学の道筋を辿るのは虚しいと言うほかありません。
そして中島義道の哲学には、この存在に対する〈親和性〉が微塵もない。むしろ、反対に、存在に対する根源的な〈異和〉の感受性のみが露出している。中島は、この本でも、前に読んだ「死を哲学する」でも、サルトルをしばしば引用していますが、ときにほとんど呪詛と言ってよい生への厭悪として表出される、中島のこの根深い存在憎悪は、サルトルの長編小説「嘔吐」の主人公ロカンタンが、マロニエの木の存在に対して感じる吐き気と基本的に同じものです。
存在に対する〈親和〉と〈異和〉。どちらの感受性が優れているということを言いたいのではありません。また、どちらの資質が哲学に向いているというわけでもないでしょう。二つの対照的な個性があるということだけです。
(このコメント続きます 4)
哲学者中島義道は、一体どこに行くのでしょう。先に引用した部分に続けて中島は語ります。
「『空無の実在論』を横目で見ながらそれを回避するのではなく、空無に身をゆだね、科学言語を突き抜けて、『まったく新しい哲学的言語を作成する』道が開かれている…」(P222)
これが何を意味しているのか、私には全くわかりません。そして、正直、わかりたいという気持ちも湧き起こりません。前回のコメントで、中島は、アカデミックな立場としては、基本的には、カントやフッサール等の大陸系の「伝統哲学」の遺産を継承していると書きました。この判断は、それほど外れてはいないと思っています。しかし、伝統哲学であれ「新しい哲学」であれ、およそ哲学的言語で「向こう側」に行くことは決してできません。これは自明です。もしも、中島が、「向こう側」について語りたいのならば、哲学をやめるほかはないでしょう。そもそも、カント研究の業績により職業哲学者として出発した中島に、こんなことを言うのは滑稽きわまる「釈迦に説法」でしょうが。
最後になります。基本的は退屈と言うほかはないこの本で、数少なく味わいがあり深く感銘を受けたのは、これも最終章にある以下の部分です。
「私が、聞きかじりで、あるとき先生に向って『神は世界を創る前に、暇だから地獄を創ったという説があるそうです』と言いますと、先生は軽蔑の眼差しを私に向けて(?)答えました。『ああ、そんなことしなくても、この世界は地獄です』と」(P221)
哲学者について知ろうとするとき、その人生上のエピソードばかりに目を向けるのはあきらかに邪道ですが、それにしてもこのエピソードは含蓄がある。
人によっては、このエピソードを正面から受け止め、大森のような優れた哲学者の言葉であるからには…と妙にうがった考えを汲みだすかもしれません。また、逆に、大森のごとき安楽椅子に座りながら言葉をもてあそぶ哲学者風情から「この世界は地獄」などという言葉を聞きたくはないという人もいるでしょう。私は、いづれでもありません。私は、ここに、大森荘蔵のまぎれもないhumorを感じます。実際、私はこの部分を読んだとき笑いを禁じることができませんでした。humorという点では中島義道も負けてはいない。中島の哲学は本質的に非常に陰鬱なものですが、一方この人は、なかなかhumorの才に恵まれています。哲学書は知らず、ともかく、中島の一般人向けの本がそれなりに売れる一つの理由は、この人が読者の笑いをとるのが上手いところにもあると思います。ともあれ、大森と中島のエピソードとしてこの部分を読むと、「ああ、師弟関係っていいなあ」とちょっとだけ羨ましくなります。
本当に長くなってしまいました。最後までお付き合いいただき、心からお礼申し上げます。
大森荘蔵と中島義道の哲学等について懇切に御案内下さり、真に有難うございます。実に明快に論理的に、かつ論理の周辺にも気配りされながら(いつものことですが)卓越した文章力で書いて下さいましたので、不勉強な私も幾度か読み返すうちに、何個所かを除いて、それなりに理解できた気分になりました。おかげさまで!
さて大森荘蔵が『「奈落」を突き抜けて「向こう側」に至る道をたどること、その可能性を十分に察知していた~』とか、『より強力で確固とした実在論への願望が湧き上がっていた』のではないかという中島義道の想像は、守拙さんの御示唆により、大森荘蔵の肖像としてはあり得ないのだと、私も納得できたように思います。
にも拘らず、この本の中で私が感銘を受けた唯一の箇所が、『先生は~「自分は救われてはならない」と決心していたようなところがある』『~俗衆とともに(?)、最後まで苦しみ抜こうとする覚悟のようなものがある』というあたり(232・222)であることに変わりはありませんでした。大森荘蔵の心中をこのように推測するのは、中島義道自身も呟いているように見当違いだったとしても、読者の(少なくとも私の)胸を打つものがあります。
徒手空拳で徹底的に思索した強靭な知性の哲学者に、このような知られざる内面があった、という説(?)は、浪花節的な出来過ぎた物語として嗤われるべきものでしょうか・・ 私にはどうしても嗤うことが出来ないのです。
中島義道は大森荘蔵の内面について、『<いま・ここ>にいても、かっての戦友たち、かっての青春の風景があまりにも「生き生きと」立ち現われてしまう。それらは抛っておくと<いま>をも支配してしまう力を持っている。これは何であろうか?~<いま>立ち現われている過去が文字通り幸福な過去ではないからなのかもしれません。』とも語っていますよね。
1921年生まれの大森荘蔵は戦争の時代をどう過ごしたのか? 戦地に行ったのか否か、空襲禍を受けたのか否か、私は知らない。しかし、生き残った人々は、たとえ戦争に積極的に加担しなかったとしても、何らかの罪悪感を引きずることになっただろうと思うのです。大森荘蔵のように誠実な人格の人が、このことと無縁である筈はないと思うのです。
一方、守拙さんが深く感銘を受け、そのhumorに笑いを禁じることができなかったという箇所が、『~「神は世界を創る前に、暇だから地獄を創ったという説があるそうです」と言いますと、先生は軽蔑の眼差しを私に向けて(?)答えました。「ああ、そんなことしなくても、この世界は地獄ですよ」』であることは、私にとってあまりにも意外でした。聞きかじりという中島義道の問いにはそれなりのhumorを私も感じますが、大森のこの答え方はあまりにもシニカルで、もし笑うとしても、それはまさにグロテスクと言ってもいいほどのブラックジョークとしてとしか思えないのです。
『~シスターたちやキリスト教信者たちを前に~「私が死ぬと死体が残るだけです」とぶっきらぼうに答えて、講演時間終了の30分も前にすたすた部屋を出てしまった。』という箇所でも、知性的でないもの、宗教的なものに対する大森荘蔵の侮蔑が露わで、気分が悪くなりそうでした。
強靭な知性で徹底的に思索を繋いできた大森荘蔵の哲学は、他の追随を許さない、まさに確固たるものであるのでしょう。大森荘蔵は自身の知性に関して無条件の信を置いていたでしょうし、またそれが許されるだけの見事な知性の持主なのだろうと思います。知性と<私>とはイコールではないのでしょうが、敢えて言えば、大森荘蔵は、<私>への信が出発点であり到着点でもあったのではないか、というのが、不勉強な私の取り敢えずの感想です。
守拙さんによれば、大森荘蔵にとっての<私>と<世界>と<存在>は一如として有り、そして大森荘蔵の感受性には<存在>に対する親和性があるとのことですので、我田引水的になりますが、<私>への信と<存在>への親和性とは一体のものでもあるのかな・・と思う次第です。
自身の思索が覚束ない私は、様々な人々の様々な思索の中から、いわば虎の威を借りるように、自分に適したレディメードの思索を探し出すことに、乏しい知力を振り向けることしか出来ません。
そしてこの本を読み、守拙さんのコメントを拝読した結果、大森荘蔵にも中島義道にも、弱き私の精神には受け入れにくいものを、残念ながらあらためて感じざるをえませんでした。
いずれにしましても、守拙さんのおかげで、不慣れな哲学の世界を少しばかり覗いて、自身の生きる姿を省みる機会を得ることが出来ました。本当に有難うございました。