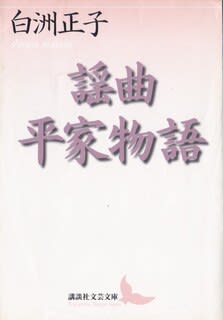自分の本棚を見ていて、何か読もうかと、あれこれ迷った挙げ句、これにしようと取り出した。
倉橋由美子の短編小説集「老人のための残酷童話」(2003講談社)。
第一刷の本だから、初めて読んだのは、20年くらい前と言うことになる。
その頃は、自分をまだ老人とは思っていなかっただろうから、老人との自覚を持つようになった今日、読むのもいいかと思った。
とりあえず、2編読んだ。
「ある老人の図書館」と「天の川」。
小説を読むのは、久しぶりで、とてもおもしろかった。
知識、イメージの広がり・展開、超然としたスタンス、真似してみたいなと思ったが、できないだろうなとも思った。
この一冊には、全部で10編が収められていて、他に「犬の哲学者」、「おいらくの恋」等と読みたくなるタイトルがならんでいる。
とても思い入れのあった本だ。
いつも、持ち歩いていた。
もう、50年以上前のこと。
書名/マルドロールの歌
著者/ロートレアモン
訳者/栗田勇
装幀/粟津潔
発行/現代思潮社 1967年7月15日 新装第8刷
定価/550円
訳者の栗田勇氏は知人の葬儀で会ったことがある。
多くの素晴らしい作品をものにされている方だ。
亡くなった知人の奥さんのお兄さんだった。
「マルドロールの歌」は、次のようにはじまる。
「神よ、願わくば読者がはげまされ、しばしこの読みものとおなじように獰猛果敢になって、毒にみちみちた陰惨な頁の荒涼たる沼地をのっきり、路に迷わず、険しい未開の路を見いださんことえを・・・・・・」
僕は、未開の路を見いだしたかった。
昨日、ショスタコビッチの「死者の歌」を聞いたとき、ロルカ詩集を開いた。
長谷川四郎訳、みすず書房、1967年発行。
かつて読んで、ページのはしを折り曲げたところがある。
そこらをいくつか読んだ。
死がよく登場する。死が散乱している。孤独な死。
死は、神がともにあるように、いつもともにある。
そのイメージを訳をもとに以下、勝手に書きならべてみた。
〈不意打ち〉
街路に胸に短刀をさされた男がころがっていた。
死んでいた。
誰も彼を知らなかった。
〈おとむらいの鐘の音〉
一本道。
「死」が胸に萎れたオレンジ色の花をつけて、歌いながら歩いて行く。
〈騎馬行〉
コルドバの塔のうえから、「死」が僕を見ている。
「死」が僕を待っている。
コルドバに着くことはないだろう。
遠藤公男著/ニホンオオカミの最後/ヤマケイ文庫/2022年11月20日発行/900円
ニホンオオカミに関する本を読んだのは、昨年、手にした「小倉美恵子著/オオカミの護符/新潮文庫/H26.12.1」以来だ。
本屋の棚に、本書を見つけて、即座に入手した。奥付を開くと、文庫版として発行されたばかりのものだった。
著者は、「人々が狼に素朴な信仰を捧げていたことは美しい。狼は恐ろしいものだったが、自然や田畑の守り神でもあった。」と語る。岩手県生まれで、自然を愛し、動物を愛し、ニホンオオカミを愛した著者は、岩手県の公文書に残るオオカミ捕殺の記録を執拗にまで、その事実を追跡調査している。
そして、ニホンオオカミが、絶滅していくありさまが述べられている。
それは、ニホンオオカミの絶滅を通し、明治以降の近代化のなかで、わたしたちが失ってきた大きな大切なものを気づかせてくれる。
「素朴でけがれのないものとの共存を願ってきたご先祖さまたちの魂にふれる。」とも記されている。
狼が人間に牙を剥き、恐ろしい存在となったのは、そんなに古い話ではなさそうだ。いにしえ、狼は、生態系のバランスを守るものとして信仰の対象ともなっている。三峯神社他の存在や日本武尊と狼との伝説が思い出される。
狼という字は、犭ヘンに良と書かれる。オオカミは、大口真神とも言われた。
狼たちは、自然のままに生きたが、人間が変わり、オオカミを恐がり、殺した。
ニホンオオカミを絶滅させたのは、わたしたち日本人なのだ。
土俗信仰に秘められたものをとらえ直さなくてはならないのでないか。
今、人間に牙を剥いているものが何であるか、偏見なしに見つめ直さなくてはならないのでないか。
もう二ヶ月くらい前になるが、国立能楽堂で、能「安達原・黑塚」を観た。
知人からの招待で、とてもいい時間を過ごすことが出来た。
能は観るものであるが、私は、読むのも好きだ。
基本が話し言葉で、ゆっくり読むと、なんとなく理解できるのがいい。
そして、親しむ因となったのが、白洲正子の「能の物語」、「謡曲平家物語」を読んだことだった。
「能の物語」には、「はじめに」に、「お能の主人公はおおむね幽霊で、生前この世に思いを残して死んだ人びとが、夢うつつの間に還ってきて、恋の想い出を語ったり、犯した罪をざんげしたりします。幽霊でない場合でも・・・・・・」とあり、おおいに興味をそそられた。
先日、「謡曲平家物語」で「大原御幸 建礼門院」を読んだが、「能の物語」にもあったはずと「大原御幸」を読んだ。
こちらは、謡曲そのものを知るのにとてもいい。
今朝、電車の中で、「大原御幸」と同時代の出来事を題材としている「俊寛」を読んだ。
どちらも後白河法皇がらみの出来事である。
「俊寛」の話は、小さい頃、子どもの本で読み、絵もついていて、とても印象深いものだった。
この前、テレビで、京都の寂光院の謂われのことなどを取り上げているのを見た。
それに刺激されて、謡曲「大原御幸」を読んだ。
はじめに、有朋堂書店発行の「謡曲集」で、続いて、小学館発行の「謡曲集」で。
前者は、大正七年発行の本で、ハンディだが、字がビッシリで読みにくい。
後者の方が、行換えがしてあったりで読みやすい。
登場人物の解説もあって、より理解できる。
人間関係が分かって、感興もたかまる。
理解を一歩進めるため、白洲正子著「謡曲平家物語」の「大原御幸 建礼門院」も読んだ。かつて、興味深く読んだ本だ。
改めて、白洲著の魅力を感じた。平時子(二院)が娘の徳子(建礼門院)をどう見ていたかにも触れていて、成る程と思った。
もう一度、小学館発行本で、ゆっくり読んでみたい。
空海の「秘蔵宝鑰」を読んだ。
読んだと言うより、字面に視線を走らせたと言った方がよさそうだ。
それに、目を通したと言っても、加藤純隆・加藤精一氏による意訳である。
さらに、頻出する仏教用語の意味が分からず、そこの理解は放棄しての通読である。
この思想書のことは、二十代の頃から知っていて、何度も手にした。
それは、宮坂宥勝氏の訳・解説の本だった。
序文にある詩が好きで、繰り返し、折に触れて読んだ。
しかし、その先は、読み始めてもすぐさま投げ出していた。
その後、角川ソフィア文庫で、加藤純隆・加藤精一訳が出て入手した。
コンパクトな文庫本で、持ち運び便利で、これなら読めるかもと思った。
それも、もう十年以上前のことだ。
時折、読み始めたが、すぐにストップとなっていた。
今回は、どういうのか、この書の全体の構成がつかめた気がして通読となった。
序文の後に、人の心の在りようが十の位階に分けられて記されている。
それは、仏教がとらえる心の高みへと順次向かっていく。
それぞれの位階を知るための仏典も仕分けされ示されている。
位階の第一から第三までは、仏教以前の教えと説明されている。
われわれは、通常、その第一のレベルに生き、あくせくしている。
それに続き、心の平静を求めたり、神聖なるものにあこがれたりする。
そして、第四以降は、仏教の教えとなる。
その内容は、下手に触れると大きく間違えそうで、ここでやめておく。
これまで、全体に目を通すことすら出来なかった「秘蔵宝鑰」に接することができた。
とりあえず、それだけで、満足した。
もし、空海が、ギリシャ哲学、魂の平安を求めたエピクロスなどを知っていたら、どのような位置づけをしたろうかなどと思った。
16世紀を生きた神学者でもある文筆家のエラスムスによる『痴愚神礼讃』(中公文庫)を読んだ。
訳者が、日本語がたくみな沓掛良彦氏で、読んでみようと思った。
はじめに、エラスムスのこと。
宗教改革は「エラスムスが卵を産み、ルターがこれを孵した」と言われる。
エラスムスの書は、汎く読まれ、時代を動かしたのである。
しかし、エラスムスは、あくまで書斎の人・「観照の人」であった。
ルターのように過激な行動に出ることはなかった。
カトリックの中にあっての“体制内改革”を求めた。
それによって、カトリックからも、ルター派からも敵対視されることになった。
『痴愚神礼讃』のこと。
全篇にわたって、痴愚女神による自己礼讃が展開されている。
痴愚こそが、はかない人生を過ごす人間に幸いをもたらしていると。
愚かさやうぬぼれは大切であると力説される。
それによってこそ、生の喜びもあると語られる。
愚かな者、小さい者は祝福されるのが世の実相と指摘される。
もっともらしく、偉そうに、清廉潔白ぶっている者にろくな者はいないと。
そして、人間社会の滑稽さが諷刺される。
権力者が揶揄される。
聖職者の実態が暴かれ、嘲笑される。
世俗権力と堕した教皇が批判・唾棄される。
エラスムスの鋭い目と言説は、諷刺によって、世のありのままの姿を明らかにする。
その語りは、痛快である。
ただ後段になると、いささかトーンに変化がでる。
イエス・キリストの真の教えは何かなどの堅い話が出てくる。
少しまじめになってしまっている。
イエス・キリストは、愚かな羊をめでたことが指摘される。
これはいい。
また、キリスト教徒の幸福は、一種の狂気と痴愚にほかならないと指摘される。
これもいい。
『痴愚神礼讃』の紹介ができればと思ったがが、どうもうまくかけなかった。
以上の、断片から、中味がうまく推察されればと思う。
【本の紹介】
小倉美恵子著/オオカミの護符/新潮文庫/H26.12.1
ここのところ、読書から遠ざかっていた。
コロナで、家での時間があり、モダン・ジャズをCDで聞いてばかりいたが、なんだかあきてきた。
関心の広がりが減速してきた。
それで、手にしたのが、小倉美恵子著の「オオカミの護符」。
本屋で、ページをペラペラめくると、御岳山や三峯神社のオオカミ信仰のことが書かれており、興味をもった。
著者は、川崎市宮前区にある実家の土蔵の扉に貼ってあった「オオカミの護符」への関心を端緒として、そのいわれ、バックグラウンドを調べ、記録に残していく。
多摩川流域での百姓の暮らし、その上流の御岳山とのつながり、そこに成り立つ暮らしぶり、いにしえからのアミニズム的信仰、これらが、取材され、記されている。
例えば、「講」の活動や儀式が具体的に語られる。おそらく、これらは、貴重な文化資料となるのでないだろうか。
多くの取材記録があり、とても興味深く読んだ。
また、一昔前のわれわれの暮らしぶりのことも思い出されて、懐かしかった。
私として、いささかもの足りないと感じたのは、オオカミが信仰の対象となった理由について、もう少し言及があってもいいのでないかということだ。
いまはなき日本狼の生態・習性、人間との関係、山の生態系の中での位置付け、森を守るということと、森から流れ出る川の下流域を守ると言う観点で、さらに述べられれば、「オオカミの護符」への理解がさらに深まるのでないかと思った。
面なの舞
謡曲「定家」を読む。
金春禅竹の作とされ、古くは「定家葛」とも言った。
主人公は、式子内親王の亡霊である。
フィクションでのことではあるが、式子内親王の生涯は、「面なの舞」だったのかと思う。
舞台は、花の都の千本あたり、藤原定家が建てた「時雨の亭」、式子内親王の塚があるあたり。
藤原定家の「邪淫の妄執」が、葛となって、式子内親王の塚にまとわりつくのを、旅の僧が読経をもって慰めるというストーリーである。
「憂き恋せじと御祓せし、・・・」式子内親王であつたが、藤原定家と契りをかわし、死して後も、「御覧ぜよ、身は仇波の立ち居だに、亡き跡までの、苦しみの、定家葛に身を閉じられて、かかる苦しみ隙なき所に、・・・」と言うことであったのである。
やるせない話であり、人の愛の妄なることを思う内容である。
でも、全体として、インパクトが薄い感じがする。
先般、新宿のディスク・ユニオンに書籍コーナーがあることを知った。
そこで、好みの本を見つけた。
「山本容子のジャズ絵本・JAZZING」なるほぼA4版の本。
2006年、講談社からの出版である。
ジャズ・ヴォーカルのスタンダード・ナンバー24曲が、1曲2ページで取り上げられている。
見開きで、左が見て楽しくなる山本容子の絵(版画)、右が、その曲にまつわるエッセイになっている。絵は、曲にちなんで、描かれている。
くつろぎのひとときに、絵と音楽、いいですよ、いかがですか、人に見せたくなる本だ。
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン、センチメンタル・ジャーニー、マイ・ファニー・バレンタイン、セプテンバー・ソング、オータム・リーブス、サマー・タイム・・・・このブログでも一言ふれた曲を改めて聞くことになる。
谷川賢作氏のプロデュースになるCDが付録になっていて、本の24曲の演奏を聞くことも出来る。
さて、「センチメンタル・ジャーニー」をもう一度。
山本氏は、この曲を歌う時、ドリス・ディに変身し、時に、マリリン・モンロー風になって色気を出して、失敗するそうだ。
5年がかりくらいで、本の全体に目を通した。
ほとんどは、意味がしっかりつかめない詩である。
京都大学学術出版会発行の西洋古典叢書「ギリシア詞華集3 沓掛良彦訳」(2016)。
「ギリシア詞華集3」には、以下の三つの巻が収められている。
・第9巻 述懐詩・風刺詩・牧歌・芸術作品などの事物描写詩など
・第10巻 勧告詩・教訓詩など
・第11巻 飲酒詩・風刺詩
読んで、意味が取りやすい詩は、教訓詩や飲酒詩にある。
詩人では、パルラダスのが、分かりいい。
この本の存在は知っていたが、5,000円を超える値がしていて、買うのをためらっていた。
ためらいの因は、そのエッセンス的な詩が集められた「ピエリアの薔薇」(沓掛訳、平凡社)を持っていたこともある。
5年くらい前、入院して、大手術ということがあり、その折、先輩のN氏から、現金でお見舞いをいただいた。
思いがけないお金で、これで買おうと思った次第である。
その入院中に、読みやすい部分は読んだ。
その後、就寝前にポツポツ読むようになり、今般、ようやく全体に目を通すにいたった。
この本を開くたびに、N氏のことを思う。
元気だろうかと。
油井正一編「モダン・ジャズ入門」(1967年11月30日10版 荒地出版社 \400)
ジャズに関心がわいて、初めて手にした本だったと思う。
ペンを執っている人たち。
油井正一、いソノてるヲ、植草甚一、相倉久人、牧芳雄、久保田二郎、岩浪洋三、野口久光、瀬川昌久、河野典生、今井寿恵、和田誠、藤井肇。
藤井肇氏による「モダン・ジャズLP30選」を開く。
持っているLPは、3分の1か。アルバムの名前に変化があったりで、正確には、もっとよく見なくては。
浮かばれぬ重衡の霊が奈良坂にあらわれる。
「あら閻浮恋しや」
閻浮は、この世のこと、現世、娑婆のこと。
「魂は去れども」「魄霊は、なほ木のもとに残り居て、ここぞ閻浮の奈良坂に、帰り来にけり」と言うわけである。
重衡は、首を斬られ、この世の命を失い、魂はあの世に行ったが、魄がこの世に残ったのだ。
魂魄とは今日もよく使うが、「魂」と「魄」が、このように分けられている。
そして、「重衡が、妄執を助け給へや」となる。
重衡の妄執とは、慚愧の念なのか。
神仏への畏れなのか。
この世への未練なのか。
ただ、この世への未練であるなら、このような謡曲がつくられることはなかったろう。
春日野の軍兵の夜の篝火の情景が謡われる。
仏の救いを信じ、求めることになる。
「重衡が、瞋恚を助けて賜び給え。瞋恚を助けて賜び給え」とむすばれる。
昨日、平家物語をぱらぱらとめくった。
南都焼き討ちと重衡生け捕りは、離れた個所に記されていた。
写真は、春日大社の森の梛の木の葉。
確か先月、撮ったものだ。
元雅作と見なされている「笠卒塔婆」。「重衡」との名もあり、さらに「重衡桜」の名もあるようだ。
重衡は、平重衡で、清盛の命で、奈良・南都の焼き討ちを行う。東大寺や興福寺が焼失する。重衡は、己の行ったことに自責の念をもつ。その重衡の心をあつかった作品で、修羅ものである。
謡曲は、旅の僧が、京都で寺社をめぐってから奈良へ、奈良坂にたどり着いたところからはじまる。
「はや奈良坂に着きにけり」と。
奈良に来たのは、「南都七堂に参らばやと存じ候」とのことである。
南都七堂とは、東大寺、興福寺、西大寺、元興寺(飛鳥寺)、大安寺、薬師寺、法隆寺の奈良近辺の大寺である。
ここらの段で、「苦しき老いの坂なれど、越ゆるや程なかるらん」「花は雨の過ぐるによって紅まさに老いたり、栁は風に欺かれて、緑やうやく低れり、寒林に骨を打つ、霊鬼泣く泣く前生の業を恨み、・・・」と、人の宿業にふれて謡われる。
「老いの鶯音も古りて、身に染む色の消えかへり、春の日の影共に、遅き歩みをたどり来て。・・・花の木蔭に着きにけり。・・・」
そこで、旅僧は、里人から、眼下に眺められる仏閣を教えてもらう。いわゆる名所教えである。
東大寺、西大寺、法華寺、興福寺(山階寺)、不退寺、飛鳥寺が教えられる。
そこで、旅僧は、里人から、そこにある墓(しるし)に向かって、「回向をなしておん通り候へ」とすすめられる。
その「しるし」とは、重衡の墓(卒塔婆)。
「さても重衡は一の谷にて生け捕られ、関東下向とありしが、南都の訴訟強きによって、あの木津川にて斬ら給ふ」と説明される。
重衡の南都焼き討ちは、清盛にこそ褒められたが、それだけだったのだ。
多くから、嫌われるというか、その所業によって、人として蔑まれたのだ。
そして、そのことを重衡はおおいに自覚していたという悲劇がそこにある。
「朝に紅顔あつて、世路にたのしむといへども、夕べには白骨となつて、郊原に朽ち果てし、木津川の波と消えて、あはれなる跡なれや」と。
謡曲は、この後、重衡の亡霊の登場となる。