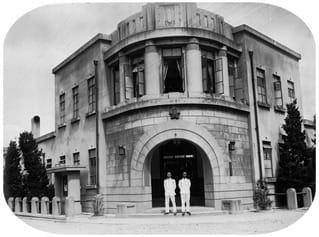朝から雨が降ったり止んだりしてうっとおしい。
池のふちを歩いていると、釣人が置いていったのか、ボートが目に入った。
ぼーっと見ていると、視界の中で一瞬何かが動いた。
目を凝らして集中する。犬か、タヌキか、それとも話題のアライグマか!?
驚かさないように静かにカメラを構える。
だが、距離がありすぎてズームをしてもよく見えない。
ごそごそ動いているが、草の葉でよく見えない。
足音をたてて気付かせた。
ボートの舳先の方に動いて、こちらのようすを見ている。
お互いに固まったように見つめ合う。
タヌキに見える。静かにシャッターを押した。
もう一枚。だが、そこで電池切れの表示が出た。
同時にタヌキはのそのそと草むらに姿を消した。
写真をよく見て、アライグマとタヌキを比べてみましたが、
やっぱりタヌキのようです。
最近、アライグマが出没して畑を荒らすなどの被害が出ています。
アライグマかと思いましたが、顔つきや色などからタヌキのように見えます。
トンボやカエル、ヘビなど自然の生き物がすぐそばにいっぱいです。
池のふちを歩いていると、釣人が置いていったのか、ボートが目に入った。
ぼーっと見ていると、視界の中で一瞬何かが動いた。
目を凝らして集中する。犬か、タヌキか、それとも話題のアライグマか!?
驚かさないように静かにカメラを構える。
だが、距離がありすぎてズームをしてもよく見えない。
ごそごそ動いているが、草の葉でよく見えない。
足音をたてて気付かせた。
ボートの舳先の方に動いて、こちらのようすを見ている。
お互いに固まったように見つめ合う。
タヌキに見える。静かにシャッターを押した。
もう一枚。だが、そこで電池切れの表示が出た。
同時にタヌキはのそのそと草むらに姿を消した。
写真をよく見て、アライグマとタヌキを比べてみましたが、
やっぱりタヌキのようです。
最近、アライグマが出没して畑を荒らすなどの被害が出ています。
アライグマかと思いましたが、顔つきや色などからタヌキのように見えます。
トンボやカエル、ヘビなど自然の生き物がすぐそばにいっぱいです。