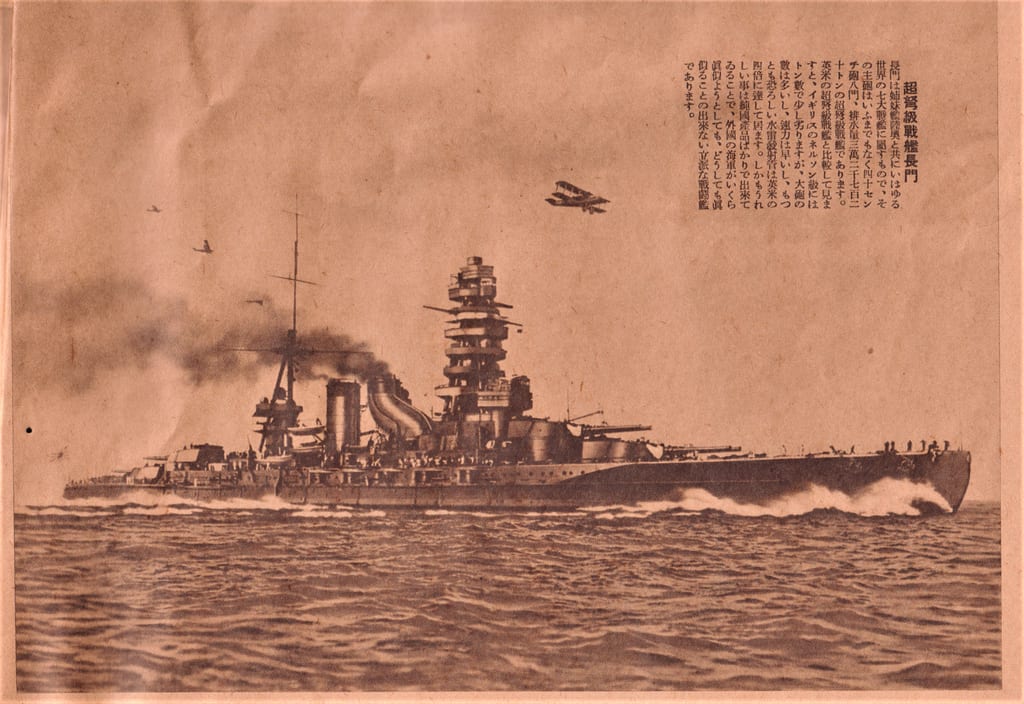28日(火)の朝、田圃の水を見に行き、田中の薬師堂のお堀のハスを見たあと、平池公園(加東市東古瀬)へ足を伸ばしました。
平池公園の大賀ハスが咲いているのは、先週の土曜日に福田小学校の体育館で敬老会が行われた時にデジタルカメラを望遠鏡代わりにしてズームした時に確認していました。その日は時間がなくて見学できず残念でしたが、28日の朝は、写真愛好家と思われる方々が数人居られただけでした。
ちなみに大賀ハスは大賀一郎博士が2000年以上前の弥生時代の遺跡から発掘した種を発芽させたもので、この平池公園の大賀ハスは社町時代に鳥取県農業試験場から譲り受けた15粒の種を発芽させ繁殖させたものです。一時は大賀ハスが一面に咲くことで知られるようになり、観光バスで遠方から見学に来られる盛況ぶりでしたが、ザリガニの被害に遭うなど維持管理に苦労もあったようです。今はハス池の一角に大賀ハスがピンク色の美しい花を咲かせていますが、少なくなりました。
芝生広場を挟んでハス池があり、そこには様々な種類のハスが植えられ花を咲かせていました。この芝生広場では、地元の福田地区の皆さんによって、毎年7月の20日頃に「平池まつり」が行われ、盆踊りや小学生、保育園児の歌や器楽演奏、兵庫教育大学の学生らのよさこい踊りや外国人留学生の歌、地元女性コーラスグループや銭太鼓グループも出演する賑やかな催しが続けられていました。池の中央や周りには多くの露天が並び、打ち上げられた花火が水面に映える賑やかなまつりでした。平池まつりが加東の夏の到来を告げるシンボル行事になっていましたが、何年か前にその幕が閉じられました。
2000年の時を超えて咲く大賀ハスを眺めながら、心がふわっとなっていくような静かな一時でした。