COLKIDが日々の出来事を気軽に書き込む小さな日記です。
COLKID プチ日記
夜に映画

Z9 + NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
大きな画像
急に映画を観に行くことになった。
Mrs.COLKIDが行かないかというのだ。
あまり気が進まなかったが、仕事が終わってから、夜の回を観に行った。
劇場には観客は数人しかいなかった(笑)
「ゴヤの名画と優しい泥棒」という作品だ。
ほとんど知識なしで見た。
予想していなかったが、かなり出来が良かった。
なかなかの傑作だと思った。
英国のコメディであるが、実話だというから驚く。
キャストが抜群だし、演出もあの時代(ちょうど僕の生まれた頃)を意識したスマートなもの。
疲れていたので、眠くなるかと心配していたが、最後までまったく眠くならなかった。
大人向けの作品である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ミッドウェイ

Z7 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
大きな画像
先週末に近所の映画館に「ミッドウェイ」を観に行ってきた。
夕方の回であったが、映画館はガラガラであった。
観客は我々二人を入れて8人くらい。
コロナで隣り合わせには座れず、映画館の中央に1席おきに8人が座っているという、何だか不思議な光景であった。
映画の方は今時珍しいほどの「純」戦争映画であった。
三流のラブロマンスを軸にした「おとぼけ戦争もの」ではなかった。
今の時代に一方的な正義で描いた戦争映画など通用しないと、ローランド・エメリッヒ監督自身が言っている。
ドイツ人の監督が第三者的な目で見た日米の戦争映画で、内容は比較的日本にも気を遣ってくれている。
やっとそういう時代が来たのかな・・という気もした。
戦争の当事者や関係者が少なくなり、孫、ひ孫の代になり、影響力も薄れてきたのであろう。
ただ中国資本がほとんどのハリウッド映画で、今後日本をどう描いて行くのであろうという疑問は残る。
そもそもハリウッドに手を伸ばしたのは、人民の操作が可能なメディアの掌握が目的であろう。
関係が悪くなれば、残虐な日本人の描写が強められるであろうことは想像に難くない。
ところでエメリッヒ監督はこの企画を20年間もあたためてきたという。
言われてみればミッドウェイ海戦は、情報の分析力や作戦ミスといったいくつかの要因で日本が逆転負けした、米国にとっては世にも面白い戦いなのだ。
それを双方の考え方をある程度公平に描き、男同士の壮絶な戦いとして作れば、映画としては見応えのあるものになる。
この映画で興味深いのは、連戦連勝であった日本を、米国の兵士が鬱気味になるほど恐れていることで、勝てるわけがない・・と考えていることだ。
確かに現場で実際に戦うものにとってはそうだったのかもしれない。
戦後に生まれた我々にしてみれば、これだけ国力が違うのだから最初から日本が勝てる戦いでは無かったという思いがある。
太平洋戦争後半の戦況が悪くなってからの日本の印象が強く、日本を恐れる米国人を見るのは不思議にも感じた。
個人的に疑問であったのは、戦闘機である零戦がドーントレスに簡単に落とされるところだ。
敵の戦闘機でさえ落とすことが出来なかった当時の零戦を、急降下爆撃機で互角の旋回性能で戦ってみせ、後部銃座からの射撃で何機も落とすなんてことが本当にあったのだろうか。
やはり映画は観客へのサービスを入れないと、興業が成り立たなくなるということであろうか・・・
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
妖星ゴラス

Z7 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
大きな画像
アマゾン・プライムで映画でも見ようかと思い、画面に表示される作品のリストを見た。
無料で見られるものは、正直なところいまひとつの作品が多く、なかなかこれぞというものに行き当たらない。
結局リストを見るだけで、作品は何も見ないで終わることも多い。
まあプライム対象の全作品をチェックすれば、いいものもあるのかもしれないが・・・
で、すごく見たいというわけでもなかったが、前から気になっていた「妖星ゴラス」を見てみることにした。
プライムで無料で見られる作品のリストに入っていたのだ。
ところがこれが意外に面白くて、結局最後まで一気に見てしまった。
僕の生まれた年に公開された古い作品である。
とにかく発想があまりに凄くて驚かされる。
初めて見る人なら呆気にとられるであろう。
お金をかけた大作ではあるが、その特殊性ゆえに、むしろカルト映画として有名であろう。
僕は子供の頃に一度テレビで見て、そのストーリーの凄さにビックリしたのを覚えている。
子供ながらに、これでいいのか??と思った(笑)
今でもいくつかのシーンが明確に記憶に残っているほどだ。
今回はそれを久々に確かめてみたい・・という気持ちもあった。
1962年公開の作品であるが、物語の舞台は1980年前後である。
すなわち当時としては近未来の世界を描いた作品なのである。
すでに人類は定期的に宇宙と地球を行き来しており、地球の周囲には各国の宇宙ステーションが浮いている・・という設定になっている。
街の作りや服装、メカなども、それなりに未来をイメージして作ったのだろうが、それがどうも素っ頓狂にも見えて、何とも言えない味を出している。
一番凄いのはやはりストーリーである。
太陽系に向かって進んでくる謎の黒色矮星ゴラスが発見されるが、大きさが地球の4分の3程度しかないのに、質量が6000倍もあり、周りのものをどんどん吸い寄せて破壊していく。
地球と衝突する軌道上にあり、このままでは地球が滅亡してしまう。
この危機を脱するには、ゴラスを破壊するか、あるいは地球が移動するか・・という2択しかない。
しかし破壊が無理なことが分かり、では地球を動かしてしまおう・・ということになる。
具体的には南極に巨大なロケット推進装置を建造して、その推力で地球を動かし、軌道から外してゴラスを避けようというのだ。
これは人類共通の危機であり、国同士が対立している時ではなく、互いに持つ技術をすべて出して協力し合うしかない。
国連で各国が議論を交わし、全人類が共同で南極の噴射装置の建設に挑む。
巨大な敵を前にして、人類が結託して立ち向かおうという話である。
ストーリーも壮大であるが、俳優陣も豪華で大物のオンパレードである。
何でも専門家に科学的考証のアドバイスを受けながら作り上げたそうで、細かい部分の理論が妙に凝っている。
アイディアがあまりに荒唐無稽なのに、大真面目に作られており、どこまで本気なのか分からないところがあり(笑)、それが作品を特殊なものにしている。
ハリウッドを始めその後の作品に与えた影響も大きいと思われる。
残念なのは南極で怪獣が出てきてしまうところだ。
噴射の熱で太古の巨大生物が目覚めてしまい、大切な噴射口を破壊してしまう。
商業的なものを考えた会社側が、怪獣を出せと要請したようだが、これで一気に映画の質が落ちてしまった。
派手な破壊シーンを期待して見に来た観客が、小難しい理論だけでは納得しないと考えたのだろう。
何でも海外版では怪獣の登場場面はカットされているそうなので、そちらを見てみたいものだと思う。
見ていて興味深かったのは、登場人物たちの考え方や生き方である。
当時は戦争が終わってまだ10数年しか経っておらず、演じている人たちの多くは、あの戦いで都市が焼け野原になり、大勢の人が死ぬのを目の当たりにしている。
そのため肝が据わっているというか、ゴラスが来たと聞いてもそれほど慌てない。
都市が津波で水没しても(我々は現実にそういう場面に遭遇しショックを受けたわけだが)あまり驚く様子が無く、残った東京タワーから周りを見ながら、また皆でいちから作り直そうなどと言う。
やはり戦争を体験しているだけあり、死ぬならそれはそれで仕方がないじゃないか・・という達観した考え方が随所に感じられる。
若者たちは、上に向かって歯向かったり、飲んで騒いだりと血気盛んである。
あの熱さは現代の日本人には無い。
すぐに皆で歌い出してしまうところなどは、どこか今の北朝鮮に近いノリを感じさせるし、現代の若者が見れば違和感があるだろうが、まあカラオケで歌うのとそう変わらないだろう。
その頃生まれた僕としては、昔はああいう熱い雰囲気があったよなあ・・と懐かしさを覚えた。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
荒野の誓い

Z7 + NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
大きな画像
日曜日に新宿に「荒野の誓い」という映画を観に行った。
なかなか見応えのあるいい作品だった。
久々の本格派西部劇である。
しかしいわゆる勧善懲悪の娯楽作品ではなく、リアリティを追求した現代ウエスタンである。
シリアスで深い作品なので、娯楽を要求するだけのファンだとついていけないかもしれない。
原題はHOSTILES、「敵意を持つ人」の複数形である。
主人公のジョー・ブロッカー大尉は、かつてウンデッドニーの虐殺にも関わった経歴を持つ軍人である。
退役間近のある日、癌を患い死期の近いシャイアン族の首長イエロー・ホークを、故郷のモンタナまで護送するという命令を受ける。
しかしイエロー・ホークは、彼の親友たちを殺した宿敵でもあった。
不当に土地を奪われ虐殺されてきたインディアンと、親友を殺された軍人・・・
それぞれの正義に基づき生きるがゆえ、憎み合い、殺し合いが終わらない。
途中コマンチ族に家族を皆殺しにされ放心状態となっていた婦人ロザリーを保護し、一行はさらに過酷な旅を続ける。
凶暴なコマンチ族の急襲を受け、やがて彼らは協力して戦わなければ生き残れないところに追い込まれる。

肌の色の違う者同士が、どう向き合い、共存していかなければならないかをテーマとした作品で、まさに現代アメリカが抱える大きな問題への問いかけになっている。
過酷なオールドウエストの世界がリアルに描かれており、その中で必死に生きていく人たちの姿が克明に描写される。
美しい自然に囲まれた世界が、一転して凄惨な血にまみれた現場となり、誠実に生きる人たちがいとも簡単に殺されていく。
配役が素晴らしく、それぞれの登場人物を丁寧に描写しているところが、この作品を傑出したものにしている。
説明を最小限にして、映像から判断させる演出もいい。
誰もが重く暗い過去を背負っており、それが必ずしも正義に基づいたものと言い切れない。
しかしそれでも人は生きていかなければならない。
子供じみたCGを使わない正統派の映像で撮られた作品である。
男っぽさと暴力という、オーソドックスな西部劇の形を取りながらも、今までのウエスタンとは違うところにまで踏み込んでおり、新しい時代の幕開けを感じさせる。
これはアメリカという国を理解するためにも重要な作品と言えるだろう。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
運び屋

Z7 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
大きな画像
日曜日に床屋に行こうとした。
ところが既に予約でいっぱいで、今からだと2時間後になるという。
どうも日曜日の午後はお客が集中するようだ。
2時間も無駄にぶらぶらするのも嫌なので、今週は床屋に行くのは止める事にした。
ちょうど日本橋にいたので、そのままiPhoneで近くの映画館の次の回のチケットを予約した。
イーストウッドの「運び屋」である。
なかなかいい映画であった。
イーストウッド監督作品らしく、例によって「弱い人間」を描くことにこだわっている。
映像もいつも通り一発撮りの自然さを優先させ、無駄なシーンは排除した簡潔なものでる。
キャストはかなりの演技派が揃っている。
しかし力まず淡々と流していることと、イーストウッドの役柄が突出しているために、それ以外の人たちは必要以上に前に出てこない。
インタビューを見るとイーストウッドと競演出来ることだけで感激してしまった人がほとんどのようだ。
神様的存在の人が、そのまま自分に近い年齢の年寄りを演じている。
仕事に熱中し過ぎて家族から恨まれ見放された孤独な老人。
過去の自分の罪を償おうとする男であり、もがきながら更なる罪を犯していく。
そのよろよろの年寄りが若い世代を翻弄し、多くの人たちの心に何かを残していく。
ところで一連のマカロニ作品やハリー・キャラハンで育った世代には、弱いイーストウッドというのがどうにも受け入れがたい。
だが今回のイーストウッドは、さすがに当人の年齢が年齢であるし、役柄も90歳の「爺さん」で最初から相手を力で倒すような能力は無い。
そのためか、かえって素直に見ることが出来た。
ああ、イーストウッドもこんなに皺くちゃになったんだなあ・・という寂しさも感じた。
晩年の父親を見る思いであった。
ところが実際には当人は至って元気だそうで、この映画の中のよたよた歩くイーストウッドは演技なのだそうだ。
ブラッドリー・クーパーによると「椅子からカンガルーのように飛び出す」ほど元気だそうで、イーストウッド自身も「養鶏場にいた祖父を思い浮かべながら演技した」という。
どうやら御大はまだまだ健在のようだ。
それを聞いて少し安心した。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
ミッション

D850 + AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
大きな画像
お盆休みにトム・クルーズの「ミッション:インポッシブル フォールアウト」を観た。
映画はかなり楽しめる質のいい活劇に仕上がっていた。
今までのシリーズの総決算のような作品である。
しかし気になったのはトム・クルーズの体の方である。
スタントのシーンも自身で演じているという。
年齢が僕と変わらないことを考えると、そうとう無理をしているのではないか。
そっちの方が気になってしまう。
今回も自らヘリコプターを操縦し空中戦を繰り広げる場面があった。
撮影のために操縦をいちから習ったのだという。
それで山々の間でヘリで追いかけっこをする。
他のシーンならまだ命綱のような危険回避の仕組みを取り付けることは出来る。
しかし本人が操縦するシーンではそれが出来ない。
操縦ミスをしたらそれまでなので、撮影関係者は凄い緊張であったという。
ハリウッドはそういうことにはかなり気を遣い、危険なことは基本的にやらせないのかと思っていたが、やはり一か八かのアクションがあるのだ。
確かに観客をハラハラドキドキさせるには効果的ではあるが、映像作品にここまで危険の伴った撮影が必要なものであろうか?
全精力を傾けている当人にしてみれば、たとえ自分の身に何が起きても本望なのだろうが・・・
だが愛されるキャラクターであるが故に、無茶はほどほどにして欲しいと思った。
もしかすると、CGとの違いを強調するために、危険なスタントをせざるを得ない状況が生まれているのではないか・・とも感じたのだが・・・
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
記憶から消えた映画

テレビで「メン・イン・ブラック」という映画を放映していた。
ぼんやりとしながら見たが、一度劇場で見ているにもかかわらず、内容を「まったく」覚えていない。
最後まで記憶しているシーンに巡り合わなかった。
こういう映画も珍しい(笑)
たしか当時トミー・リー・ジョーンズが来日してニュース・ステーションに出ていたが、何でこんな映画が大ヒットしたのか理解できない・・という顔をした久米宏氏が、多少失礼とも思える態度でインタビューをしていた。
映画の内容はまったく覚えていないのに、インタビューの様子は覚えているというのも、またおかしな話ではある(笑)
たしかにくだらない映画であるが、ぼけっとしながらテレビで見るには、程よい感じの映画だった(笑)
トミー・リー・ジョーンズも缶コーヒーのCMで有名になったが、やはりベストフィルムはロンサム・ダブのウッドロウ役だろうと思う。
あれほどの役は二度と巡ってこないのではないか?
D2Hs + Nikkor-HC Auto 50mm F2.0
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
ポニョ

「崖の上のポニョ」を見てきた。
母親とMrs.COLKIDの三人で、夜9時から11時までの回に行ったが、お客の入りはまあまあで、100人近かったのではないかと思う。
70歳代と40歳代という異例の「親子連れ」で鑑賞した(笑)
作品は素晴らしかった。
傑作といっていい出来であったが、評価は分かれるかもしれない。
登場人物たちは、今までの作品と共通した宮崎ワールドの常連であるが、絵とストーリーを単純化したことが効いていて、今までになく有機的にバランスがとれており納得がいく。
意図的に水平線の高さをあやふやにしているところも面白く、夢の中のような非現実的な世界に引き込まれてしまう。
人間が自らの手を使い作品を描くということが、これほどのエネルギーと価値を持つのだということを認識させられた。
文化の成熟とはそういうものなのだろう。
これを見て一番衝撃を受けるのは、今や食傷気味ともいえるCGで作られたアニメーションの製作者たちかもしれない。
彼らに、これだけのものがその手を使って作れるか?と問いたくなる。
作品を見た子供たちが、考えていたところで反応してくれなかったと、宮崎氏がガッカリしている記事を読んだが、海という強大でグロテスクな存在が、恐怖感を与えている可能性は高い。
トトロのように、大地を中心としてストーリーが展開するような、安心して見ていられる世界の話ではない。
一方、特有の非現実的なストーリー展開は、リアリストの女性陣にはさっぱり理解できない面もあったようだ(笑)
Mrs.COLKIDの評価「角が丸まっていて目が疲れない映画だった」
母親の評価「金魚の話」
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
おじさん

BSで放送されていた「ギャラクシー・クエスト」を、つい最後まで見てしまった。
オタクがオタクのために作ったような楽しい作品で、日本で公開した時は小規模で、小さな劇場に見に行ったのを覚えている。
今回何気なく見ていて「名探偵モンク」のトニー・シャルーブが出ているのに驚いた。
テレビでモンクを見ている時は、どこかで見た顔とは思っていたが、ギャラクシー・クエストのあの異性人と結ばれる無愛想な博士には結びつかなかった。
一見特徴の無い普通のおじさんなので記憶に残りにくい。
モンクを含めちょっと特殊な役柄が多いから、性格俳優と呼べるのかもしれない。
経歴を見てみると、意外にいろいろな作品に顔を出している。
しかもやはり癖のある役が多い(笑)
日本ではモンクで一気にお茶の間に浸透したが、あのように特徴の無い風貌の俳優さんをよくぞ主役に抜擢したものだと思う。
監督からすれば使いやすいような使いにくいような・・・(笑)
実際にはあの役でエミー賞やゴールデン・グローブ賞を受賞している実力派なのだ。
こういうおじさん系俳優さんは逆に熱心なファンが付きやすい。
僕も今は亡きチャック・コナーズやビル・ビクスビーのファンだし、マンクーゾのロバート・ロジアなんかも好きなのだが、知っている人は少ないだろう(笑)
D2X + Ai AF Micro Nikkor ED 200mm F4D(IF) + PN-11
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ザ・マジックアワー
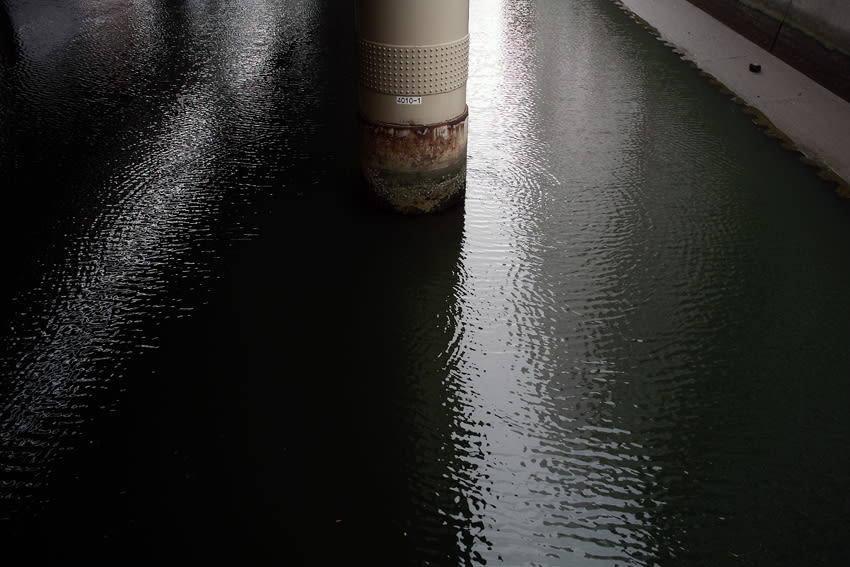
書く時間が取れないのでとりあえず更新。
などと言いながら先程までBSで名探偵モンクを見ていた(笑)
土曜の夜に「ザ・マジックアワー」を見てきた。
初日とはいえ、レイトショーなのに100人近い観客数は、三谷人気をうかがわせるもの。
今までの三谷作品の中で一番まとまりが良く、ある完成度にまで達した印象を受けた。
またストーリーが実際に面白く、場内で観客が声を出して笑う場面が非常に多かった。
短時間しか出演しない人を含めて、役者の顔ぶれが凄く、それを楽しむのもこの映画の醍醐味のひとつになっている。
映画界が特殊な世界であることが伝わってくる映画だ。
Mrs.COLKIDは疲れていて最初のうち居眠りしていたので、レディスデイにでも、もう一度見に行くそうだ(笑)
SIGMA DP1
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ジャンパー

またレイトショーを見にシネコンに行き、真夜中過ぎに帰って来た。
「ジャンパー」という公開してからかなり経つ映画で、しかも一番遅い回で、どれだけのお客さんが入るのかを見てみようと思ったのだ。
実を言うと映画よりそちらの方に興味があった。
もしかすると観客は我々夫婦二人だけかも?と思っていたのだが、意外にも十数人のお客さんが来ていた。
帰りは0時過ぎるというのに、女性一人で来ているお客さんもいて、大丈夫なのかと心配になった。
ちょっと特殊な客層が集まっているようにも思えた(笑)
映画は予想通りのもの(笑)
悪評が多いが、期待していなかった分、僕はけっこう楽しめた。
お金もかかっているようだし、(好きではないのだが)サミュエル・L・ジャクソンといった有名どころも出ている。
母親役のダイアン・レインはなかなかいい味出していたが、この方とても自分より年下とは思えない(笑)
個人的に最大の問題は東京で撮影されたシーンで、銀座の交差点と渋谷の交差点をごちゃ混ぜにして同じ場所のように使うので、それが気になって映画どころではなくなってしまった。
いつも歩いている場所だけに、こういう使い方をされると辛い。
そのままジャンプして家に帰りたい気分になった(笑)
Mrs.COLKIDの感想:「疲れた・・・」
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
クローバーフィールド

「クローバーフィールド/HAKAISHA」を見てきた。
9時過ぎのレイトショーだったが、けっこうお客が入っていた。
まあ公開初日なのだから当然ではあるのだが、理由はそればかりでなく、企画そのものに高い集客性があったのだろう。
予告編やCMを見ただけで、多くの人が「見たい」と思ったに違いない。
主人公の回すビデオカメラの映像・・それだけで最初から最後まで押し通す。
良く考えたら、悪名高き「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」と同じ手法ではあるが(笑)、それにしても奇抜で面白そうだ。
お客は予告編を見て、すぐにその内容を察して、これは見てみたいと思っただろう。
この映画は興行的にはけっこう成功しているのではないか?
宣伝はそればかりではなく、インターネットを巧妙に使い、想像をかき立てるような情報を少しずつ提示して、公開のかなり前から人々の関心を集めていたのだそうだ。
しかも映画を見ても謎は完全には解明されておらず、どうやらネットの情報が補完する形で、全体像が見えてくる仕掛けになっているようだ。
その新しい手法に感心するが、一方で宣伝の旨さばかりが目立っているようにも感じられる。
映画の持つ雰囲気については、予告編で既に想像しているから、実際に映画を見てもそれほど驚きはない。
素人の撮ったビデオという設定だから、独特の生々しさはあるのだが、画面がグラグラと揺れるので気持ちの悪くなる人が続出するだろう(笑)
で、生々しいわりに、主人公の行動に共感が持てないのは問題だ。
ニューヨークに住む主人公ロブは、仕事で副社長として抜擢されて、日本に旅立つことになる。
その送別会が開かれ、ビデオカメラでパーティを記録している最中に、突然得体の知れない怪物が街を襲う。
後は逃げ回るだけだ。
はやく日本に行っていればよかったのに・・と誰もが思うだろう(笑)
しかし主人公たち一行は、恋人を助けるためにあえて逆方向に進み、その間ビデオを回し続ける。
映画は、街が壊滅された後に、セントラルパーク跡地から発見されたそのビデオを再生している・・という設定。
悪夢のような独特の恐怖を味わえる。
しかし奇抜な手法が足かせになり、常に一人称的な表現になるので、視点を変えた大きな展開が出来ない。
結果的には目新しさだけがすべて、の作品になってしまったように思う。
怪物のデザインも古臭いし、あれだけ攻撃されて傷ひとつ負わないのは不自然だ。
それ以前に、今時怪獣が街を破壊する映画?という疑問が残る(笑)
Mrs.COLKIDの評価:
「テレビゲームのやり過ぎの人たちが作ったのではないか?」
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ノーカントリー

いつもネタばれにならないよう気をつけて書いている。
しかしこの映画の場合、見る前になるべく知識をつけない方がいいかもしれない。
白紙の状態で見たい人は、以下を読まない方がいいと思う。
アカデミー賞主要4部門を受賞した話題の映画。
早速近所のシネコンに見に行ってきた。
ストーリーは非常に単純でわかりやすい。
舞台は1980年代のテキサス。
ベトナム帰りのルウェリン・モス(ジョシュ・ブローリン)が、荒野でひとりハンティングを楽しんでいると、麻薬取引に関するトラブルで撃ち合いのあった現場に行き当たる。
死体だらけの中に大金を見つけたモスは、ちゃっかりそれをいただいてしまう。
しかしそれが彼の運命を変えた。
組織に雇われて追ってきた殺し屋シガー(ハビエル・バルデム)は怪物のような殺人鬼。
事件のほぼ全容を知るエド・トム・ベル保安官(トミー・リー・ジョーンズ)は、モスを助けようと動くが・・・
このストーリーがそのまま進んだら、典型的なアクション映画になってしまい、オスカーを取るほどの作品に仕上げるのは厳しいだろう。
ところがモスと殺し屋シガーの戦いが実に丁寧に描かれており、非常に見応えがあるため、この後どうなるのだろうと、見るものにそうとうの期待を抱かせる。
中でも殺し屋シガーのキャラクターは傑出しており、独自の価値観に基づいて冷徹に動く、まるで悪魔のような絶対的存在の人物。
自分と何らかの接触を持った人物を、それが一般の人であろうとなかろうと、容赦なく全員殺してしまう。
一方逃げるモスの方もなかなかの実力と頭脳を持つ人物で、戦争の殺し合いの中をくぐり抜けた者特有の行動力を持っており、シガーの凄まじい追撃を何とかかわしてみせる。
この二人の戦いは抜群に面白い。
ペキンパーを思わせる演出は、当時のテキサスの雰囲気を生々しいほどに感じさせる。
ところがそれが実は観客を陥れる罠なのである。
これはいうなれば観客の心理をもてあそぶような作品だ。
わかりやすいストーリーが、いきなり難解なものへと変わる。
これは小説的な展開をする作品といえる。
映画の公式をぶち壊しており、ある意味革新的ともいえるだろう。
しかし、こういう演出のやり方が「あり」だというならば、それこそ何でもありになってしまうのも事実だ。
観客は狐につままれたような気分になり、鳩が豆鉄砲を食らったような顔で劇場から出てくる(笑)
たしかに非常にユニークで見事な作品である。
だがこのやり方を何度も続けられては堪らない。
出来れば今回限りにして欲しいと思う(笑)
正直言うと正攻法でストーリーを進めた作品も見てみたかった。
原作通りだとはいえ、この映画の製作は、一種の賭けであったような気もする。
結果はご存知の通り、ラッキーコインだったわけだが・・・
ところでトミー・リー・ジョーンズはミスキャストではないか?
(1980年代の時点で)時代の変化に取り残されつつある彼ら年配者たちのぼやきが、実は映画のテーマになっている。
しかし保安官の心理描写が不十分だし、何よりトミー・リー・ジョーンズは存在感がありすぎる。
彼なら何かやってのけなければおかしい・・という思いが残ってしまう。
その違和感が狙いと言われればそれまでなのだが・・・
Mrs.COLKIDの評価
「私はアメリカ人ではないので、この映画はよくわからない」(笑)
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
また行ってきた。

夜になって近所のシネコンに話題の「ノーカントリー」を見に行ってきた。
こんなのありかよ!っていう感じの映画だった(笑)
先週の「バンテージ・ポイント」といい、通常の枠に当てはまらない問題作が続くね(笑)
D3 + AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
バンテージ・ポイント

この映画の評価は賛否両論に分かれるようだ。
個人的には非常に面白かったが、Mrs.COLKIDは物足りないという意見だった。
単にストーリーを追うだけなら、たしかに深みが無くて物足りないかもしれない。
これは実験的な作品といえる。
大統領が演説の最中に狙撃され、大勢の人が集まっている広場が爆破される。
その事件の23分程前から、狙撃後の大混乱までの出来事を8回繰り返す。
たったそれだけの作品なのだが、その繰り返しの中でストーリーを展開し、ちゃんと完結させるシナリオは、書くのがなかなか大変だったろうと思う。
だんだんと謎が解明されていく形をとっているが、謎自体は大したものではないので、そこに価値を見出そうとするなら、この作品はまったくの駄作になってしまう。
実際このストーリーで普通に撮ったなら、これはかなり辛い作品になったであろう。
視点を変えて同じ時間を8回繰り返すだけで物語を完結させるという、特殊な制約の中で話を進めなければならないため、展開上どうしてもご都合主義になっている部分もある。
要するにこの映画は、その演出形式としての面白さを楽しむことが出来るかどうかがポイントとなる。
爆発により大勢の人が亡くなるシーンを、何度も何度も繰り返すわけだから、最初から最後まで緊張しっぱなしで気が緩む瞬間が無い。
90分という最近の作品としては上映時間が短いこともあり、全編を通じて無駄を感じさせない。
時間を短くしたことは、成功していると言ってよく、爽快でさえあった。
カーチェイスのシーンも、CGをほとんど使っていないためリアリティがあり、まるで自分が運転しているようで楽しい(?)
こういうシーンはどういうわけかアメリカで撮影すると大味になりがちだが、舞台はスペイン(撮影はメキシコシティ)で、なかなか密度感のあるものに仕上がっている。
これは監督の力量だろうと思う。
俳優陣は特に突出した人はいなかったが、特殊な映画なので、それでいいのかもしれない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




