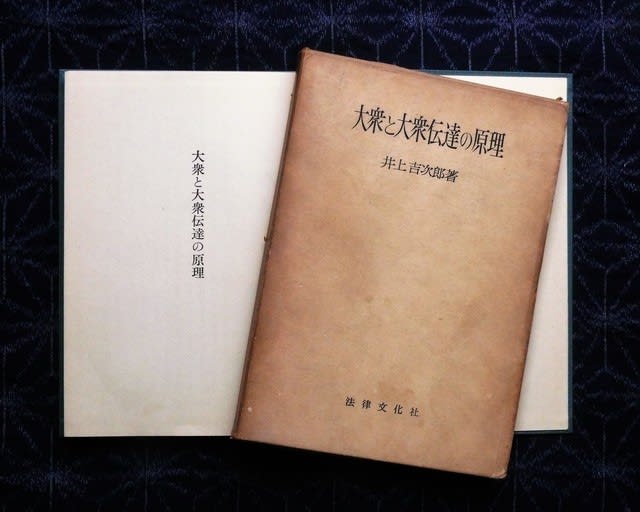<2567> 余聞、余話 「時代の変遷 ~ネット社会の出現~」
知と感のあまた行き交ふ現代のこの世観なる一個のこの身
手許に一冊の本がある。昭和三十六年(一九六一年)に出された『大衆と大衆伝達の原理』(井上吉次郎著)という二〇〇ページほどの、社会学的考察によるマスコミュニケーション論と言ってもよいか、約半世紀前、マスコミュニケーション論が華々しく展開されていたころの、言わば、この筋の本としては古典に属するものと言ってよかろう、私には学生時代に読んだ本である。
何故この古い本を本棚の隅から引っ張り出し、読み返す気になったか。それは当時のマスコミュニケーションとほぼ同時に出現して来た大衆の時代から今まさにインターネットの双方向性の伝達方式によって出現して来たネット社会の大衆時代が来て、それに傾斜しつつあることによる。つまり、マスコミュニケーションの伝達方式とともにあった大衆見参の社会からインターネットの双方向性の伝達方式によって生まれたネット社会への変革を考えてみたかったからである。
この本は、語彙的にかなり難しい本であるが、マスコミュニケーションとほぼ同時に出現した大衆社会を論じ、次にマスコミュニケーションが大衆社会の出現に果たした役割について見ている。そして、これに加え、マスコミュニケーションのあり方に話を進めている点もあげられる。まず、はじめに、社会の概念から入り、社会が交通によって成り立っているという点に着目し、そこから論は始められている。
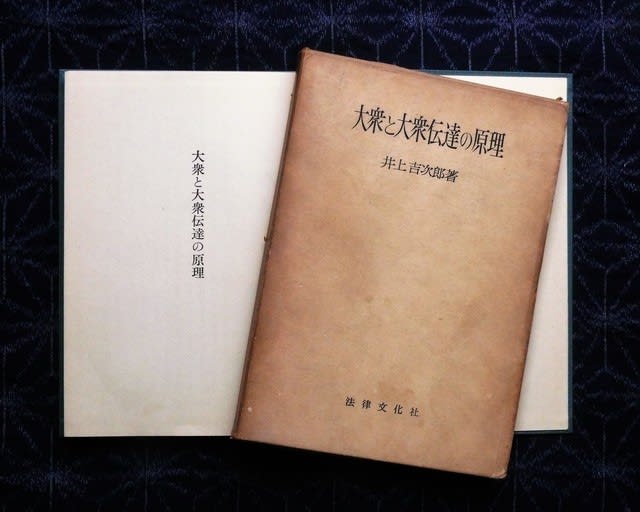

社会というのは交通を必要条件とし、交通がなければ社会は成り立ち得ないという点に基づき、論の展開に入っている。まず、交通とは互いが関係することで、物流のみならず、精神的な意識交通も重要な要素と捉え、この本では後者の意識交通の方に焦点を当て、言葉や映像の重要性を認識に置きながら意識交通であるコミュニケーションの影響において展開してゆく社会を考察している。
社会は人と人との交通によって暮らしの中に生じて来たが、その後、交通手段が発達し、大量交通が可能になるに従い、社会も大きくなり、当然のことコミュニケーションの量も増大し、その伝達方法にも変化を来たし、所謂、マスコミュニケーションの時代を迎えるに至るわけである。新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどがマスコミュニケーションの大量に及ぶ意識交通の役目を担うようになったことに論及は進む。
マスコミュニケーションのマスはmassで、massは大量を意味する。そして、マスコミュニケーションによる大量の情報によっていよいよ見参を明らかにしたのがmasses、即ち、大衆であるという。この大衆が作り上げたのが大衆社会で、その大衆の内実の反映をして語られるのが大衆文化ということになる。このmassesの大衆の時代は物流にも現れ、大量生産、大量消費に反映され、資本主義の影響もあり、大家族制から小家族の核家族化が社会において進んだのと軌を一にしている。
で、massesの大衆というのは、老若男女はもとより、地位や貴賤にかかわらず、人種、民族、国家、団体等、また、思想、信条などにも左右されることのない性質を有する大多数を意味し、それは群集、公衆、民衆、庶民、国民といった概念では括れない社会の大多数の心理的要素によってなるものと考えられ、その実態は掴みどころのない従順と計り知れない性質を内在しているものであると認識された。
こうした大衆を導き育てる役目を果たして来たのがマスコミュニケーションで、その大衆の内実の様相をして大衆文化と捉え、一億総白痴化という言葉や世論という言葉を生み、その言葉などにも言及している。ここで重要なのは、この伝達方式がほぼ一方通行の状況にあったことで、その伝達方式が大衆を大きく左右したと見ていることである。
で、大衆はマスコミュニケーションの伝達方式によって従順な上に寡黙にならざるを得ない環境状況に浮遊し、マスコミュニケーションの送り手であるマスメディアの権威を高め、あるはオピニオンリーダーなどという言葉も発せられて来るという認識が生じ、こうした状況において、この本ではマスメディアの責任にも論を展開している。
そこで言われるのが、大量の意識交通(今でいう情報伝達)の担い手であるマスメディアの重要性で、マスコミュニケーション(報道)における送り手の公正、信憑性、良識、平等、中立、客観性、公序良俗などが求められ、新聞社においては新聞綱領、テレビにおいては倫理規定などが定められ、この良心の方向性を見失うことのないようにした。言わば。これらの課題は一方通行の送り手側のマスメディアの責任として委ねられ、マスメディアの良心によって受け手である大衆との信頼関係を構築し、マスコミュニケーションの方式を可能ならしめたということになる。ときに信頼を欠くような出来事も生じ、この点におけるトラブルがなかったわけではないが、それは特異例としてその都度処理され、概ねその信頼関係は崩れることなく保たれ、現在に至っているという次第である。
このマスコミュニケーションと大衆社会の関係性について、著者は『大衆文化』という別の本において「十人の子をもつ家が、ドブ池へ行って、ランニング・シャツを一ダース買い、男の子も女の子も無しゃ別に着せる、という話を聞いた。これが現代マス・コミ受手各戸の受信方式だ」と大阪の繊維問屋街のドブ池を例に示して言及している。マスコミュニケーション全盛の時代において大衆はこの方式下で概ね満足し、了解していた。
また、受け手である大衆の信頼を得るための送り手側の心構えについても、二十世紀前半のイギリス人記録映画制作者ジョン・グリア―ソンの言葉を引いて啓蒙の言葉とし論じている。「Observe and analyse know and build Out of research poetory comes」というのがその言葉で、命令形であるのが意味深長なところ、直訳すると、「観察し、そして、分析せよ」「知れ、そして、構造(構築)せよ」「(こうした)調査から詩が生まれ来る」となるが、この言葉は送り手側の立場にあるジョン・グリア―ソン自身が自分に向けて発し、言い聞かせた戒めの言葉であり、自分を鼓舞している言葉と理解出来る。そして、それはマスメディアの送り手側の全てに共通して発せられるに等しい言葉として受け取れる言葉になっているのがわかる。
Poetory(詩性)とは、新聞で言えば、記事のReality(真実性)に当たり、優れて信頼される記事はこの言葉に込められたような努力がなくてはならないと言っているわけで、情報の送り手側にある者は、このようにあらねばならないということを示していると受け取れる。これはマスコミュニケーションの伝達方式の図式において、送り手のマスコミ人が影響力を持ち、あるはオピニオンリーダーとして一種の権威のようになって大衆社会をリードする立場にあり、送り手自らにその厳しさを課すことによってその関係性が保たれるという認識があったからで、その一つの例としてあげているわけである。
こうしたマスコミュニケーションのほぼ一方的大量の伝達方式に進化(あるいは変革)を加えたのが、パソコンの普及とインターネットの構築による二十一世紀の花形として登場して来たネットの存在であり、『大衆と大衆伝達の原理』から話を進めれば、その存在における享受者として出現したのがネット社会のネット大衆ということになるわけである。グローバルに及ぶ双方向性の意識交通を可能にしたインターネットの方式によるネットはマスコミュニケーションが作り上げて来た大衆社会に溶け込むと同時に、その特質をもってマスコミュニケーションが有する大衆社会の大海に入り、双方向性という大きく鋭い銛を無数に撃ち込み、衝撃を与え、今に及んでいるという次第である。
そのもっとも顕著な変化は、日常坐臥における表立たない心情的な変化にある点、気づき難いところがあるが、それはマスコミュニケーション論の中で言われて来た大衆が有する性質に当面して来たことで、まさに大衆の変化ということに行き着く。言わば、ネットの双方向の伝達方式によって獲得した大衆個々の権利、つまり、個々人が自由に支障なく発言(発信)出来るその発言が大多数の大衆みんなに、それも即応して伝え得るようになったことである。この状況はマスコミュニケーションの時代とは明らかに異なる情報授受であり、同じ大衆でも異なる大衆をネットは生み出したということになるわけである。言わば、大衆における抑制の開放がネット社会には、良しにつけ悪しきにつけ、見られるようになったのである。
つまり、ネット社会では個々人誰もがネットを介してみんなと繋がることが出来、自分の意志を発することが出来る。別の言葉で言えば、自己主張ということになるだろう。そこには大衆個々の意志が反映され、ネットはその可能性を秘めて常にあるという状況を構築しているということになる。これはマスコミュニケーションの伝達方式の時代には考えもつかなかったことで、この状況の変化は各方面に既に現れているが、これは個人主義の深化という点にあると言える。例えば、マスコミュニケーションの全盛時代には一種のブランド商法に大衆の迎合が見られたが、ネットの双方向性の伝達方式の時代は顧客個々の個性に対応し、直接の繋がりが持てるに至り、顧客の欲求を商品に反映させるZOZOTOWNのような商法が成り立ち成功しているのである。これはまさに双方向性の伝達方式に負うところで、個人主義の深化をより促していると言える。言葉を変えて言えば、より進化した多様性の顕現に通じる。
マスコミュニケーションの時代もアメリカの個人主義(自由、平等)の精神が先導し、日本においても社会的状況が資本主義の考え方と連動し、個人主義的家族制である核家族化を進め、大衆というものを重んじて来た。「消費者は神様」とか「消費者は王様」というような言葉が聞かれたのはマスコミュニケーション全盛の時代で、その時代には申し分のない言葉であった。所謂、massesの大衆を意識に置いた言葉である。しかし、この状況になお個人主義の立場はもの足りず、次の段階であるネットの双方向性の方式を、科学技術の向上によって生み出したのが今般のネット社会と言える。
このネットの伝達方式は、自由平等の個人主義を理念に掲げる国民性の国アメリカの属性で、究極の方法であると言えるが、この個人主義の理念においてネットがアメリカに発したことは、これまでの経緯を顧みるに、必然的精神性に基づくものであると受け取ることが出来る。これは余談になるが、アメリカのトランプ大統領はネットをよく活用している。これに対し、中国の習近平国家主席はネットに否定的で、ネットの情報を遮断する措置に出たりしている。これは社会主義国と個人主義に基づく自由主義国の立場の違いが出ているが、このネットの用いられ方を見ると、良し悪しは別にして、ネットが個人主義的自由平等な特質を有していることをよく表していると捉えることが出来る。
そして、ネットにおける大衆はものの言えない大衆からものが言えてその意志を発言乃至発信出来る大衆に変貌し、直接ものが言えなかったマスコミュニケーション時代の大衆を性情的に変えたということになるわけである。で、ネットの時代になって大衆の個々人はみんなに向かって発言し、自己の開放を始めたのである。こうした大衆の変化の状況は従来の方式の上に成り立って、それが常識のようになっていた大衆社会を変えずには置かず、大衆社会に動揺をもたらすに至った。それが、良しにつけ悪しきにつけ、ネットの生みの親の足許であるアメリカにおいて展開されているのが、ネット派のトランプ大統領と従来のマスメディアとの対立の構図である。この対立はネットが十分に認知されるまで当分続くのではないかと思われる。
日本では最近外国人旅行者の急増する喜ばしい状況が現出している。この状況にはいろんな要因が絡んでいるとは考えられるが、ネットの普及が大きく貢献していることは明らかで、ネットなくしてこの状況は生じ得なかったと言っても過言ではなかろう。マスコミュニケーションが主役の時代には、この間亡くなった兼高かおる女史が世界各地に赴き、その旅先を紹介してお茶の間に届け、話題になり、彼女のキャラクターとともに人気を博した。まさにマスコミュニケーション全盛時代の象徴的テレビ番組の一コマであるが、ネットの双方向性の伝達方式による昨今の状況は兼高女史が数え切れなく大衆の中にいるという風になっているのである。
こうした状況は、新聞、テレビのニュースにも反映され、言ってみれば、大衆の中に記者や報道カメラマンが紛れ込んでいるのと同じで、あの掌サイズのスマートフォンさえ携帯していればその場の情報をいち早く捉え送ることが出来る。それも知らず知らずのうちにそうなっているという状況にある。新聞はラジオやテレビの出現によって速報性を奪われて久しいが、インターネットの普及により、速報性を武器にしていたラジオやテレビでさえスマートフォンの威力には及ばない、ネットの時代になっているというのが最近の傾向としてうかがえる。
これは当事者(actor)イコール観察者(observer)イコール媒体(media)という図式が成り立っていることを示すもので、ネットの最も特徴的なところと言ってよい。マスコミュニケーションの立場において、この実情は無視出来ず、マスメディアはこの状況を凌ぐために一種の権威をもって対抗している面が記事内容や番組制作に表面化しているのが見て取れる。言わば、速報性は捨て、その出来事の内実を掘り下げて伝える専門家を交えた解説報道や調査報道、情報番組が多くなっていることである。何かやるせないような感じであるが、今般はこういう状況に傾斜している。
しかし、ネットに喜ばしいことばかりはなく、その状況は、科学の進展にも言えるごとく、功罪が認められるところで、すべてがOKとはいかない点も考えなくてはならないところにある。第一にあげられるのは、マスコミュニケーションにおけるマスメディアが自らに課した信頼性を確保するための良心の行使が、個々人が発信者のインターネットによるネット社会では難しく、フェイクニュースなども多くなる欠点があることである。
次に、インターネットの情報は短く、深い考察の出来る状況にない点の見られるところもあげられる。短くてなおインパクトのある言葉や画像にみんながとびつき、意識し、執着する。その執着の結実数であるフォロワー数がネットを支えるのであるが、短いものは概ね知性には訴え難く、情緒に流されるということになり、それは受け手の喜怒哀楽に繋がり、社会的パニックを引き起こすことになるところがある。最近の若者に読書離れが見られ、本が売れないというのも、ネット時代を象徴しているように思われる。
また、インターネットの双方向性のやり取りにおいては容易に友達や仲間を作り上げる作用がその短い言葉や画像によって可能になることから、直接対面して接触することなく友達や仲間をつくる気楽さに陥り、トラブルに巻き込まれたりすることが生じる。これは個人、組織を問わず起きる傾向にあり、最近、アメリカを中心に、白人ファーストの自国中心主義の偏りが見られるようになっているのもネットの双方向性が影響していると見て取れる。グローバル化を進める一方でこうした現象も起きている。テロ組織のISが世界から兵士を募ったのもインターネットであり、そこが問われたことも功罪の罪にあたることが言える。
また、他人を誹謗中傷する所謂ヘイトスピーチなどにも利用されるようになった。デモの呼びかけがネットで行われるという社会の事態が出現しているのも事実で、これらを考えるに、それはマスコミュニケーションのメディアによる影響力がネットによって弱体化している一面としてあるようにも思われる。
一方、個人主義の徹底がネット社会に浸透する中で、個人主義の一面である孤独の捉え方にも考察が必要になって来たことが指摘出来る。双方向性の伝達方式であるネットの両極面を考えるに必然のことであることは、マスコミュニケーションの大衆社会が押し進めて来た時代において核家族が進行し、その結果として少子高齢化の状況に陥ってしまったことに重なる点が思われて来たりする。
そして、また、一つには、インターネットによるコマ切れの情報が有するインパクトによって一躍話題になり、持て囃される御仁が現れたりする反面、多量に及ぶ次々に押し寄せる情報によってその御仁は速やかにかき消され、ピコ太郎がよい例で、あっという間に忘れ去られ過去のものになるという刹那主義が社会に投影され、そのインパクトをわが物にするねらいなどで、軽薄な情報を送り出すという族も現われるという具合になったりしていることが言える。これはネットの弊害であるが、匿名性の可能による功罪なども見え隠れしているのがネット社会の現状として捉えられる。
以上、これらを総合的に考え、双方向性という観点からして言えば、マスコミュニケーションの時代からは明らかに革新しているわけで、マスメディアにすれば脅威にほかならないと言える。若い世代に新聞離れが言われて久しいが、半世紀後には一層の変貌を来たし、新聞の戸別配達制なども危うくなるのではないかと想像されたりする。テレビやラジオにしても言えることであろう。そういう一面を考えさせながら時代は移り、時代は変貌しつつあるということが言える。 写真は『大衆と大衆伝達の原理』(左)と『大衆文化』(右)。