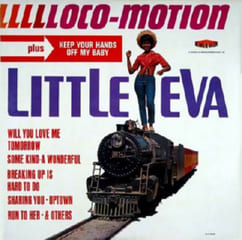先日 shoppgirl 姐さんからいただいたコメントの中に “My 80's Best 3” というのがあって、ポリスの「見つめていたい」、バングルズの「胸いっぱいの愛」、そしてREOスピードワゴンの「涙のフィーリング」を挙げられていた。いつもながらの選曲センスの良さに改めて感銘を受けるとともに、“My 80's Best 3” という発想そのものがめっちゃ気に入ってしまった。私はかなりの気分屋でしかも優柔不断ときているので “Best 3” はおろか、“Best 20” でも悩むかもしれないし、下手をすると日替わりで首位が変わる可能性も十分だ。しかし上記の3曲は確実に入ってくるだろう。あと、シャーリーンの「愛はかげろうのように」と、シカゴの「素直になれなくて」も外せない。ティファニーの「思い出に抱かれて」もエエなぁ... などと、80'sへの想いはどんどん膨らんでいく。あかん、とりあえず “Best 50” ぐらいから始めよう(笑) shoppgirl 姐さんは私の音楽人生に新たな楽しみを付け加えて下さった恩人だ(^o^)丿 それとREOスピードワゴン、最近ご無沙汰気味だったので昨日久しぶりに聴いてみたらこれがもう最高に懐かしくって涙ちょちょぎれる展開に... これは当ブログで取り上げないわけにはいかない。
アメリカの古い消防自動車からグループ名をとったREOスピードワゴンは1971年にデビューした後、売れない下積みの10年間を過ごし、“アメリカで最も売れていないが、長続きしているバンド。傑出した作品もなく、ワンパターンで永久にヘッドライナーにはなれない。”(←そこまで言うか!)などど酷評されていた。まぁ70年代後半のミュージック・シーンを考えてみれば、一番ワリを食うのがこの手のバンドというのは火を見るよりも明らかだった。
しかし80年代に入ってシーンは再び「歌の時代」へと回帰した。オーディエンスはもう70年代後半の無味乾燥な音楽に飽き飽きしていたのだ。ちょうどその頃、ヴォーカルのケヴィン・クローニン(←本名です!そりゃ苦労するわな...)は “バラッドの中にエネルギーを込める” 唱法を体得、バンドもエネルギッシュなロックンロール一辺倒からメロディーに重点を置いた音作りをするようになっていた。ついに時代の欲求とバンドのサウンドがピッタリ合致したのだ。その結果、1980年の終わりにリリースされた11枚目のアルバム「ハイ・インフィデリティ」は翌81年に15週連続全米№1を続け、アメリカだけで900万枚を売り上げるモンスター・アルバムとなった。
アメリカでこのアルバムが大ヒットしていた頃、私はちょうど大学に入学したところで、ここに収められた楽曲群を聴くと今でも新生活のスタートで燃えていた自分を思い出してしまう。特に私がハマッていたのが②「キープ・オン・ラヴィング・ユー」で、まさにグループの歴史を象徴するかのように16週間かけてゆっくりとチャートを上がっていき、ついに全米№1に昇りつめた、ロッカ・バラッドの王道を行く名曲だ。実はこの曲、日本ではキャッチーな④「涙のレター」(いくら何でもREOの邦題は「涙の...」が多すぎ。「涙のレター」→「涙のフィーリング」→「涙のドリーム」→「涙のルーズ・ユー」って... エピックソニーは洋楽ファンをナメてんの?)のB面に収められていたので知名度は低いが、この重厚なサウンドをベースにしてそこにこれ以上ないくらい素晴らしい歌詞を乗せたのが4年後の大名曲「涙のフィーリング」なんじゃないかと思う。他にも歯切れの良い痛快なロックンロール①「ドント・レット・ヒム・ゴー」や泣きのギター・ソロがたまらない⑤「テイク・イット・オン・ザ・ラン」など、“歌心溢れる”ナンバーが目白押し。そのポップなハーモニーの多用といい、ダイナミックでスリリングなサウンド展開といい、このアルバムはアメリカン・ポップスの原点を見事に描写した作品であり、今まさに花開かんとする80'sポップスの出発点だったのだ。
Keep On loving You - REO Speedwagon (HQ Audio).flv
アメリカの古い消防自動車からグループ名をとったREOスピードワゴンは1971年にデビューした後、売れない下積みの10年間を過ごし、“アメリカで最も売れていないが、長続きしているバンド。傑出した作品もなく、ワンパターンで永久にヘッドライナーにはなれない。”(←そこまで言うか!)などど酷評されていた。まぁ70年代後半のミュージック・シーンを考えてみれば、一番ワリを食うのがこの手のバンドというのは火を見るよりも明らかだった。
しかし80年代に入ってシーンは再び「歌の時代」へと回帰した。オーディエンスはもう70年代後半の無味乾燥な音楽に飽き飽きしていたのだ。ちょうどその頃、ヴォーカルのケヴィン・クローニン(←本名です!そりゃ苦労するわな...)は “バラッドの中にエネルギーを込める” 唱法を体得、バンドもエネルギッシュなロックンロール一辺倒からメロディーに重点を置いた音作りをするようになっていた。ついに時代の欲求とバンドのサウンドがピッタリ合致したのだ。その結果、1980年の終わりにリリースされた11枚目のアルバム「ハイ・インフィデリティ」は翌81年に15週連続全米№1を続け、アメリカだけで900万枚を売り上げるモンスター・アルバムとなった。
アメリカでこのアルバムが大ヒットしていた頃、私はちょうど大学に入学したところで、ここに収められた楽曲群を聴くと今でも新生活のスタートで燃えていた自分を思い出してしまう。特に私がハマッていたのが②「キープ・オン・ラヴィング・ユー」で、まさにグループの歴史を象徴するかのように16週間かけてゆっくりとチャートを上がっていき、ついに全米№1に昇りつめた、ロッカ・バラッドの王道を行く名曲だ。実はこの曲、日本ではキャッチーな④「涙のレター」(いくら何でもREOの邦題は「涙の...」が多すぎ。「涙のレター」→「涙のフィーリング」→「涙のドリーム」→「涙のルーズ・ユー」って... エピックソニーは洋楽ファンをナメてんの?)のB面に収められていたので知名度は低いが、この重厚なサウンドをベースにしてそこにこれ以上ないくらい素晴らしい歌詞を乗せたのが4年後の大名曲「涙のフィーリング」なんじゃないかと思う。他にも歯切れの良い痛快なロックンロール①「ドント・レット・ヒム・ゴー」や泣きのギター・ソロがたまらない⑤「テイク・イット・オン・ザ・ラン」など、“歌心溢れる”ナンバーが目白押し。そのポップなハーモニーの多用といい、ダイナミックでスリリングなサウンド展開といい、このアルバムはアメリカン・ポップスの原点を見事に描写した作品であり、今まさに花開かんとする80'sポップスの出発点だったのだ。
Keep On loving You - REO Speedwagon (HQ Audio).flv