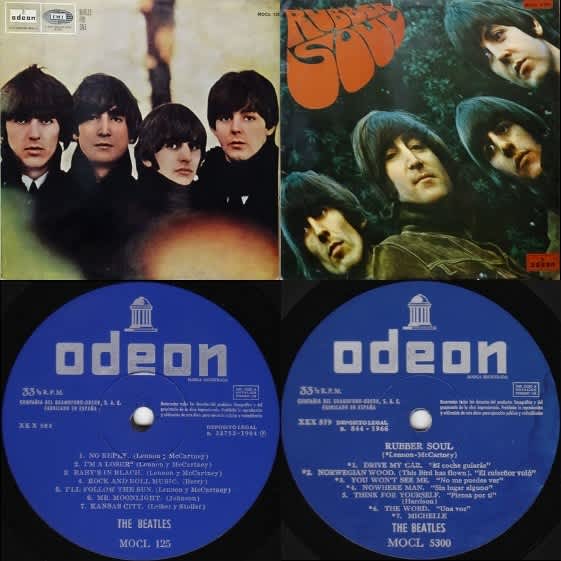先週だったか、吉本ばななの名を騙って生成AIで作ったフェイク作品がアマゾンの電子書籍で販売されたという詐欺事件がニュースになっていた。そもそも電子書籍などというわけのわからんもんとは無縁の私には対岸の火事のようなものだったが、よくよく考えてみると音楽の世界でも十分にありえることなので、自分には全く無関係な事件と切って捨てるわけにもいかない。実際、YouTube上ではビートルズを素材とした “AI カバー” が我が物顔で跋扈しており注意が必要だ。
ただ、何でもかんでもAIが悪いというのではなく、その出自をはっきりさせたうえで “よくできたフェイク作品” と割り切って楽しむ分には(権利関係とか難しい話は横に置いといて)何の問題もないのではないか。例えるなら優秀なカバー・バンドみたいなモンで、 “本物とは違う土俵でやっますよ” と明言してくれればファンとしても楽しみが増えて大歓迎だ。
で、その “AI カバー” だが、本家ビートルズの作品に関してはハッキリ言ってイマイチ。私が注目したのはメンバーのソロ曲で、“もしもジョンがポールの、あるいはポールがジョンの曲に参加していたら、一体どんな感じになっていただろう?” という、いわゆるひとつの “What if” 系の作品だ。今日はそれらの中からいくつか傾聴に値するものを取り上げようと思う。
まず最初は「Egypt Station」に入っていた名バラッド「I Don’t Know」だ。この曲はアルバム中でも一二を争う愛聴曲なのだが、そんな名曲をAIが換骨奪胎して “架空のジョンとポールの共演作” としてリメイクしたのがこのヴァージョン。ポールの声もオリジナルより少し若返り補正されているように聞こえて面白いが、何と言っても1:28から(AIが作った)ジョンの声が入ってくるところが一番の聴きどころ。これ、めっちゃエエやん! 改めてジョンとポールの声の組み合わせって人類史上最高最強なんだということを思い知らされる。2:50から入ってくるバック・コーラスもビートリィな薫りが横溢で、AI否定派のビートルズ・ファンにも一度は聴いてほしい1曲だ
Paul McCartney & John Lennon I Don't Know
「I Don’t Know」を聴いて “こんなん他にもあるんちゃうか...” と思った私がYouTubeで検索をかけまくってみたところ、ピンからキリまで一杯出てきてビックリ。まさに “AIビートルズ玉石混交” の状況を呈しており、何じゃこりゃ?みたいな “石” も一杯出てくるが、そんな中からお気に入りの “玉” を探すのが楽しいのだ。そんなこんなで見つけたのがこの「NEW」で、ここでもやはり0:45からジョンそっくりの声が何の違和感も感じさせずに “We can do what we want~♪” と滑り込んでくるところがたまらない(≧▽≦) 「Sgt/Pepper’s」~「Magical Mystery Tour」期のビートルズ作品に紛れ込ませても全く遜色のない逸品に仕上がっているところが凄いと思う。
Paul McCartney ft. John Lennon - NEW (Lyrics Subtitulado en español)
次に見つけたのは「Real Love」だ。「Now And Then」が発表された時は “いかにしてジョンの声をピアノの音と分離してクリアーに抽出するか” というテクノロジー面においてAIが大活躍したわけだが、この「Real Love」はテンポを上げて曲想までガラリと変えてしまうという大胆不敵な行為にまで踏み込んでいる。ビートルズ・ファンの中では賛否両論がわき起こりそうだが、私はこのトラックが大好き。まず聴いててとても気持ち良いし、原曲のメロディーの良さを殺さずに、しかもそこかしこにビートリィなフレイバーを織り交ぜながら(←エンディングのテープ逆回しwww)、これだけの作品に仕上げてしまったところに脱帽だ。
The Beatles - Real Love - 1967 Version [ AI cover]
「Real Love」を作ったTimmySeanという人は他にもいくつかこの手の作品をアップしているが、中でも私が気に入ったのが「Wonderful Christmastime」だ。ほとんどのAIカバーが見落としがちなリンゴのドラム・サウンドに焦点を当てているのがポイントで、「1967 Version」と謳うだけあって「Magical Mystery Tour」期あたりのサウンドを見事に再現している。1967年のファンクラブ向けクリスマス・レコードに入れたらぴったりハマりそうな仕上がりだ。
The Beatles - Wonderful Christmastime - 1967 Version [ Paul McCartney song A.I. cover ]
最後はジョンの全作品中でも屈指の名旋律に涙ちょちょぎれる「Grow Old With Me」をビートリィにアレンジしたヴァージョンだ。実際に聴いてもらうしかないが、ハッキリ言ってこれ、超凄くないですか? 0:58からジョンのリード・ヴォーカルに優しく添い寝するバックのコーラス・ハーモニーはビートルズそのものだし、1:43から “Spending our lives together~♪” のラインをポールの声が歌うところなんてもう2人の蜜月時代を彷彿とさせる完成度で、不覚にも目頭が熱くなってしまった。このAI、めっちゃヤバいわ。これでリンゴのドラムが本物に近かったら(←ヴォーカルやアレンジの素晴らしさに比べるとさすがにちょっとショボすぎる...)私的には100点満点をあげたいくらいだ。
The Beatles - Grow Old With Me - Lyric Video (AI Cover)
【おまけ】感動的な「Grow Old With Me」の後にこれはないやろと言われそうだが、同じAI繋がりということで気にせず紹介。AIを駆使してフレディー・マーキュリーに「おジャ魔女カーニバル」を歌わせようという発想も凄いが、まるで本当にクイーンが超満員のウェンブリー・アリ-ナでこの曲を演っているかのように錯覚させるくらい見事な動画編集技術にはもう感心するしかない。特に口の動きと歌声の合い方なんかもう我が目と耳を疑うレベルだ。権利関係とか色々ややこしいことがあるのかもしれないが、こういう使い方こそがAIの活かし方ではないかと思わされる笑撃のケッ作だ。
QUEEN - おジャ魔女カーニバル!! (LIVE) AI COVER