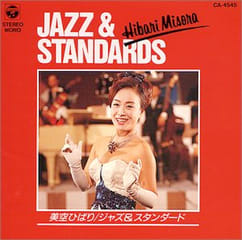2月の半ばから約1ヶ月にわたって続けてきた “ポールのスタンダード特集” も今日で最終回。通常盤に入っている中で特集可能な曲はすべてやり尽くしたので、今日は16曲入りのUK盤に収録されていたボーナス・トラックの1曲、「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ」でいこう。
この曲はロシアのクラシック作曲家アントン・ルビンシュタインという人の「ロマンス」という曲にインスパイアされて1953年にロバート・メリンが作詞、ガイ・ウッドが作曲した美しいラヴ・ソング。 “あなたを想うだけで私の心は歌い出す... あなたの手が触れただけでまるで天国にいるような気分... あなたへの想いで胸が一杯... あなたのキスの一つ一つが私の心に火をつける... 私は喜んですべてを捧げよう... 私のただ一人の愛しい人よ” という激甘な歌詞からも、ポールのナンシーさんへの熱い想いがヒシヒシと伝わってくる選曲だ。
スタンダード・ナンバーとしての人気・知名度はまさにA級と言ってよく、ヴォーカル物では最初にレコーディングしたフランク・シナトラ(1953)を皮切りに、ジョニ・ジェイムズ(1955)、リタ・ライス(1955)、ジョー・ムーニー(1957)、リタ・ローザ(1957)、ジューン・クリスティ(1958)、ディオン(1961)、バリー・シスターズ(1961)、エラ・フィッツジェラルド(1962)、ジョニー・ハートマン(1963)、キャロル・スローン(1982)、リッキー・リー・ジョーンズ(1991)、ジャネット・サイデル(1998)、ロッド・スチュワート(2005)、ソフィー・ミルマン(2009)と挙げていけばキリが無い。まるでこの曲の美しいメロディーに魅せられたかのように我も我もと吹き込んでいるのだ。
インスト物ではサックス、ピアノ、ギターに集中していて、ビリー・テイラー(1953)、アート・テイタム&ベン・ウェブスター(1956)、リッチー・カミューカ(1957)、ペッパー・アダムス(1957)、コールマン・ホーキンス(1958)、グラント・グリーン(1961)、オスカー・ピーターソン(1964)、ウェス・モンゴメリー(1965)、ケニー・バレル(1980)、アリ・リャーソン(2007)らの演奏があり、ジプシー・ジャズ系でもロマーヌ(2003)、イズマエル・ラインハルト(2006)、スウィング・アムール(2006)、ビレリ・ラグレーン(2008)とまさに引っ張りだこ状態である。ドラマチックな歌詞と美しいメロディー・ラインを持ったこのバラッド曲はある意味ごまかしがきかないというか、シンガー/プレイヤーとしての力量が試されるところがあり、そういう意味でも色々なアーティストを聴き比べて楽しめる1曲と言える。
このように多くのアーティスト達が取り上げている中、ヴォーカルではシナトラかハートマン、インストはテイタム&ウェブスターがこの曲の決定版というのが一般的な世評だろう。確かにそのどれもが “王道” という言葉がふさわしい名唱・名演だとは思うが、ここでは敢えて shiotch7認定 “裏名演” 3ヴァージョンをピックアップしてみた。
①Doris Day
元々この曲の歌詞は男性の立場で歌うように書かれたものだが(←“君は僕の腕の中”とか、“君は頬を赤く染める”とか...)、あまりの名曲故か、上に挙げたように女性シンガーもよく歌っており、そんな中でも一番気に入っているのがドリス・デイのヴァージョンだ。アンドレ・プレビン・トリオの伴奏でドリス・デイのヴォーカルが楽しめるジャジーなアルバム「デュエット」(1962年)に入っていたもので、彼女のほのかな色香の薫るハスキーな歌声と歌伴マイスターであるプレビンのツボを心得たピアノの相性もバッチリだ。甘い曲想をキリリと引き締めるレッド・ミッチェルの重低音ベースが絶妙な隠し味として効いており、文句なしの名演と言っていいだろう。ポピュラー・ソング、映画主題歌、そしてジャズのスタンダード・ナンバーと、どんな曲を歌っても彼女は決して期待を裏切らない。まさに “ドリス・デイに駄盤なし” だ。
Doris Day and Andre Previn My One and Only Love
②Benny Carter
この曲のテナー・サックスによる決定版が「テイタム・ウェブスター」ならアルトはコレ! 1954年にリリースされた「ベニー・カーター・プレイズ・プリティ」というデヴィッド・ストーン・マーチンによるイラスト・ジャケで有名な10インチ盤に入っていたもので、ラヴ・ソングばかりを集めてカーターのメロウで芳醇なアルトの音色で楽しめるという悦楽盤だ。後に12インチ盤「ムーングロウ」として再発されているが、美女が佇むそっちのジャケも雰囲気抜群で甲乙付け難い。演奏の方も素晴らしく、豊かな歌心でロマンチックなメロディーを朗々と歌い上げるカーターの優美で流麗なソロがこの曲の素晴らしさを極限まで引き出している。大切な人と特別な時間を共有したい時の BGM にピッタリの名演だ。
Benny Carter - My One And Only Love
③キヨシ小林
この曲は原曲のメロディーを崩さずにスロー・テンポのバラッドとしてしっとりと歌い上げるのが定石だが、そんなバラッドの名曲をジャンゴ・スタイルで見事にスイングさせているのが日本が世界に誇るマヌーシュ・ギタリスト、キヨシ小林のこのヴァージョン。アルバム「ジャンゴ・スウィング」には「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ」のスロー・ヴァージョンとこのアップテンポ・ヴァージョンが2曲続けて収められており、本人の曲目メモによると、 “ここでは欲張ってスローとハイテンポでレコーディングしちゃいました。” とのことだが、テンポを上げてスイングさせるという発想そのものが素晴らしい。特に後者のザクザクと刻むギター2本とベース1本のトリオ演奏という最小限のユニットが放つ絶妙なスイング感がたまらなく耳に心地良い。やっぱりジプシー・ギターはエエなぁ... (≧▽≦)
キヨシ・コバヤシ
この曲はロシアのクラシック作曲家アントン・ルビンシュタインという人の「ロマンス」という曲にインスパイアされて1953年にロバート・メリンが作詞、ガイ・ウッドが作曲した美しいラヴ・ソング。 “あなたを想うだけで私の心は歌い出す... あなたの手が触れただけでまるで天国にいるような気分... あなたへの想いで胸が一杯... あなたのキスの一つ一つが私の心に火をつける... 私は喜んですべてを捧げよう... 私のただ一人の愛しい人よ” という激甘な歌詞からも、ポールのナンシーさんへの熱い想いがヒシヒシと伝わってくる選曲だ。
スタンダード・ナンバーとしての人気・知名度はまさにA級と言ってよく、ヴォーカル物では最初にレコーディングしたフランク・シナトラ(1953)を皮切りに、ジョニ・ジェイムズ(1955)、リタ・ライス(1955)、ジョー・ムーニー(1957)、リタ・ローザ(1957)、ジューン・クリスティ(1958)、ディオン(1961)、バリー・シスターズ(1961)、エラ・フィッツジェラルド(1962)、ジョニー・ハートマン(1963)、キャロル・スローン(1982)、リッキー・リー・ジョーンズ(1991)、ジャネット・サイデル(1998)、ロッド・スチュワート(2005)、ソフィー・ミルマン(2009)と挙げていけばキリが無い。まるでこの曲の美しいメロディーに魅せられたかのように我も我もと吹き込んでいるのだ。
インスト物ではサックス、ピアノ、ギターに集中していて、ビリー・テイラー(1953)、アート・テイタム&ベン・ウェブスター(1956)、リッチー・カミューカ(1957)、ペッパー・アダムス(1957)、コールマン・ホーキンス(1958)、グラント・グリーン(1961)、オスカー・ピーターソン(1964)、ウェス・モンゴメリー(1965)、ケニー・バレル(1980)、アリ・リャーソン(2007)らの演奏があり、ジプシー・ジャズ系でもロマーヌ(2003)、イズマエル・ラインハルト(2006)、スウィング・アムール(2006)、ビレリ・ラグレーン(2008)とまさに引っ張りだこ状態である。ドラマチックな歌詞と美しいメロディー・ラインを持ったこのバラッド曲はある意味ごまかしがきかないというか、シンガー/プレイヤーとしての力量が試されるところがあり、そういう意味でも色々なアーティストを聴き比べて楽しめる1曲と言える。
このように多くのアーティスト達が取り上げている中、ヴォーカルではシナトラかハートマン、インストはテイタム&ウェブスターがこの曲の決定版というのが一般的な世評だろう。確かにそのどれもが “王道” という言葉がふさわしい名唱・名演だとは思うが、ここでは敢えて shiotch7認定 “裏名演” 3ヴァージョンをピックアップしてみた。
①Doris Day
元々この曲の歌詞は男性の立場で歌うように書かれたものだが(←“君は僕の腕の中”とか、“君は頬を赤く染める”とか...)、あまりの名曲故か、上に挙げたように女性シンガーもよく歌っており、そんな中でも一番気に入っているのがドリス・デイのヴァージョンだ。アンドレ・プレビン・トリオの伴奏でドリス・デイのヴォーカルが楽しめるジャジーなアルバム「デュエット」(1962年)に入っていたもので、彼女のほのかな色香の薫るハスキーな歌声と歌伴マイスターであるプレビンのツボを心得たピアノの相性もバッチリだ。甘い曲想をキリリと引き締めるレッド・ミッチェルの重低音ベースが絶妙な隠し味として効いており、文句なしの名演と言っていいだろう。ポピュラー・ソング、映画主題歌、そしてジャズのスタンダード・ナンバーと、どんな曲を歌っても彼女は決して期待を裏切らない。まさに “ドリス・デイに駄盤なし” だ。
Doris Day and Andre Previn My One and Only Love
②Benny Carter
この曲のテナー・サックスによる決定版が「テイタム・ウェブスター」ならアルトはコレ! 1954年にリリースされた「ベニー・カーター・プレイズ・プリティ」というデヴィッド・ストーン・マーチンによるイラスト・ジャケで有名な10インチ盤に入っていたもので、ラヴ・ソングばかりを集めてカーターのメロウで芳醇なアルトの音色で楽しめるという悦楽盤だ。後に12インチ盤「ムーングロウ」として再発されているが、美女が佇むそっちのジャケも雰囲気抜群で甲乙付け難い。演奏の方も素晴らしく、豊かな歌心でロマンチックなメロディーを朗々と歌い上げるカーターの優美で流麗なソロがこの曲の素晴らしさを極限まで引き出している。大切な人と特別な時間を共有したい時の BGM にピッタリの名演だ。
Benny Carter - My One And Only Love
③キヨシ小林
この曲は原曲のメロディーを崩さずにスロー・テンポのバラッドとしてしっとりと歌い上げるのが定石だが、そんなバラッドの名曲をジャンゴ・スタイルで見事にスイングさせているのが日本が世界に誇るマヌーシュ・ギタリスト、キヨシ小林のこのヴァージョン。アルバム「ジャンゴ・スウィング」には「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ」のスロー・ヴァージョンとこのアップテンポ・ヴァージョンが2曲続けて収められており、本人の曲目メモによると、 “ここでは欲張ってスローとハイテンポでレコーディングしちゃいました。” とのことだが、テンポを上げてスイングさせるという発想そのものが素晴らしい。特に後者のザクザクと刻むギター2本とベース1本のトリオ演奏という最小限のユニットが放つ絶妙なスイング感がたまらなく耳に心地良い。やっぱりジプシー・ギターはエエなぁ... (≧▽≦)
キヨシ・コバヤシ