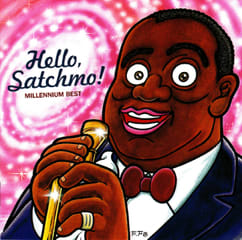待ちに待った B'z の最新ライヴDVDが届いた。アマゾンでかなり前に予約しておいたもので、運良く発売日前日のフラゲに成功だ(^.^) タイトルは「B'z LIVE-GYM 2010 “Ain't No Magic”at Tokyo Dome」で、 昨年末に発売されたアルバム「マジック」を引っ提げて彼らが今年の1月~3月に行った全国ツアーの中から最終日の東京ドーム公演の模様を約2時間半に亘って収録したものだ。今回は普通のDVD版とブルーレイ版の2種類が同時発売されたが、ブルーレイ・プレイヤーもハイヴィジョン・テレビも持っていない私は当然DVD版。そもそもブルーレイってそんなに普及してるんかね??? 普通のパソコンとの互換性もないし、画質にそれほどこだわりの無い私は今のDVDで十分満足だ。
私は彼らのDVDは必ず買うことにしているが、とにかくそのライヴ・パフォーマンスの完成度の高さには毎回感心させられる。ロックの黄金時代だった1970~80年代、英米のハードロック系バンドはまずファンに凄いライヴを見せつけ、感激したファンがレコードを買い、また次のライヴにも足を運ぶというのが活動形態の基本であり、特にブリティッシュ・ロックの世界ではそれが小さな会場で行われていたためにバンドのカリスマ性をより増幅させる要因となっていたように思うのだが、B'z はその原始的とも言えるロック・バンドの基本的な方法論をこの21世紀に、ドーム級の巨大スタジアムで実践し続けているのである。これはもう凄いとしか言いようがない。
彼らのライヴの魅力、それは稲葉さんのカリスマ性とシャープな動き(←ホンマにカッコエエわ...)、松本さんの音楽監督としての比類なき才能に加え、ハイ・クオリティーな楽曲の波状攻撃、ズバ抜けて高い演奏力、度肝を抜くようなアイデア満載のステージ・セット、と挙げていけばキリがないが、何よりもバンドが一体となって生み出す途方も無いエネルギーの奔流が5万人を超える大観衆を圧倒するのだ。
以下、今回のライヴの簡単な感想です;
・いきなり①「DIVE」、②「Time Flies」とテンション上がりまくり。稲さんのグラサン+金ピカ・スーツ姿がめっちゃカッコエエわ(^o^)丿
・お二人同時の “B'z の LIVE-GYM にようこそ!” に至るまでの絶妙なやり取り、特に松ちゃん面白すぎ...(^.^) ファンは必見でしょう。
・上記の “ようこそ!” から間髪を入れずに我が愛聴曲③「MY LONELY TOWN」のイントロへとなだれ込む瞬間がタマランo(^-^)o
・バックの巨大スクリーンの3つの円がスティッチに見えるのは私だけ?
・④「今夜月の見える丘に」のイントロが何と「ムーン・リヴァー」だった... 松ちゃん、ニクイ演出やねぇ... (o^-')b
・④「今月」、⑤「PRAY」、⑥「TIME」、⑦「TINY DROPS」、⑧「OCEAN」という怒涛の歌い上げ系バラッド5連発はさすがにキツイ(>_<) 個人的には「夢の中で逢いましょう」とかを挟んでチェンジ・オブ・ペースを考えても良かったのでは?と思う。
・⑪「Mayday!」で、演奏しながらアリーナ席頭上を縦断するフライングステージは圧巻! B'z のライヴはスケールが違うわ(゜o゜)
・メンバー紹介時の松ちゃんの“サンシャイン60も スゴクイイケド、ココからの眺め もっとサイコーデス” 発言にはワロタ☆('-^*)/
・⑭「LOVE IS DEAD」に行く前に松ちゃんとサポメンが繰り広げるジャジーなセッション「JAZZY BULLETS」がめっちゃエエ感じ。このメンバー、ジャズもバリバリに上手いやん(o^-')b
・⑰「だれにも言えねぇ」の間奏で何故か「ゴッドファーザー愛のテーマ」をつま弾く松ちゃんとカメラ目線の稲さんのツーショット...役者やのぉ(^∇^)
・パワー・スポット “だれにも言えねぇ井戸” ネタが最高!松ちゃんのオトボケも絶好調やし、稲さんの井戸を覗き込む後ろ姿にも大爆笑。B'z のお二人面白すぎるわ。とにかく今回はいつも以上にリラックス・ムードが伝わってきて楽しいなったら楽しいなヽ(^o^)丿
・⑱「MOVE」の炎のリフ攻撃めっちゃカッコエエ(´∀`) 血湧き肉躍るとはまさにこのこと。
・⑳「long time no see」での稲さんの喋りにグッときた。この人いつもホンマにエエこと言うね... (;´Д`)ノ
・(21)「愛まま」で5万人のCメロ大合唱のシーンがタマラン!
・(22)「イチブトゼンブ」のバラッドverから通常verへの流れが絶妙!
・エンドロールで東京の夜景をバックに流れる「PRAY」がこれまた鳥肌モノ(≧▽≦)
とまぁ印象に残ったパートをサッと書き出してみたが、これまでのライヴとの一番の違いはとにかくユーモアたっぷりの演出で “自然と笑わせてくれる” 遊び心満載のステージに尽きると思う。それでいてキメるところはビシッとキメるのだから、ライヴであれDVDであれ十分に元を取ったという満足感で一杯だ。私にとって B'z のライヴはリアルタイムで体験できる “最高のロック・ショー” なのだ!!!
※今回のツアー映像はまだアップされてないようなので、過去のライヴ映像に音声をシンクロさせた【MAD】ヴァージョンで。この B'zMONSTER21 っていう職人さん、なかなかエエ仕事してまんなぁ...
B'z LIVE-GYM 2010 _Ain't No Magic_ at TOKYO DOME
【MAD】 Introduction ~ DIVE / B'z
【MAD】 PRAY / B'z
私は彼らのDVDは必ず買うことにしているが、とにかくそのライヴ・パフォーマンスの完成度の高さには毎回感心させられる。ロックの黄金時代だった1970~80年代、英米のハードロック系バンドはまずファンに凄いライヴを見せつけ、感激したファンがレコードを買い、また次のライヴにも足を運ぶというのが活動形態の基本であり、特にブリティッシュ・ロックの世界ではそれが小さな会場で行われていたためにバンドのカリスマ性をより増幅させる要因となっていたように思うのだが、B'z はその原始的とも言えるロック・バンドの基本的な方法論をこの21世紀に、ドーム級の巨大スタジアムで実践し続けているのである。これはもう凄いとしか言いようがない。
彼らのライヴの魅力、それは稲葉さんのカリスマ性とシャープな動き(←ホンマにカッコエエわ...)、松本さんの音楽監督としての比類なき才能に加え、ハイ・クオリティーな楽曲の波状攻撃、ズバ抜けて高い演奏力、度肝を抜くようなアイデア満載のステージ・セット、と挙げていけばキリがないが、何よりもバンドが一体となって生み出す途方も無いエネルギーの奔流が5万人を超える大観衆を圧倒するのだ。
以下、今回のライヴの簡単な感想です;
・いきなり①「DIVE」、②「Time Flies」とテンション上がりまくり。稲さんのグラサン+金ピカ・スーツ姿がめっちゃカッコエエわ(^o^)丿
・お二人同時の “B'z の LIVE-GYM にようこそ!” に至るまでの絶妙なやり取り、特に松ちゃん面白すぎ...(^.^) ファンは必見でしょう。
・上記の “ようこそ!” から間髪を入れずに我が愛聴曲③「MY LONELY TOWN」のイントロへとなだれ込む瞬間がタマランo(^-^)o
・バックの巨大スクリーンの3つの円がスティッチに見えるのは私だけ?
・④「今夜月の見える丘に」のイントロが何と「ムーン・リヴァー」だった... 松ちゃん、ニクイ演出やねぇ... (o^-')b
・④「今月」、⑤「PRAY」、⑥「TIME」、⑦「TINY DROPS」、⑧「OCEAN」という怒涛の歌い上げ系バラッド5連発はさすがにキツイ(>_<) 個人的には「夢の中で逢いましょう」とかを挟んでチェンジ・オブ・ペースを考えても良かったのでは?と思う。
・⑪「Mayday!」で、演奏しながらアリーナ席頭上を縦断するフライングステージは圧巻! B'z のライヴはスケールが違うわ(゜o゜)
・メンバー紹介時の松ちゃんの“サンシャイン60も スゴクイイケド、ココからの眺め もっとサイコーデス” 発言にはワロタ☆('-^*)/
・⑭「LOVE IS DEAD」に行く前に松ちゃんとサポメンが繰り広げるジャジーなセッション「JAZZY BULLETS」がめっちゃエエ感じ。このメンバー、ジャズもバリバリに上手いやん(o^-')b
・⑰「だれにも言えねぇ」の間奏で何故か「ゴッドファーザー愛のテーマ」をつま弾く松ちゃんとカメラ目線の稲さんのツーショット...役者やのぉ(^∇^)
・パワー・スポット “だれにも言えねぇ井戸” ネタが最高!松ちゃんのオトボケも絶好調やし、稲さんの井戸を覗き込む後ろ姿にも大爆笑。B'z のお二人面白すぎるわ。とにかく今回はいつも以上にリラックス・ムードが伝わってきて楽しいなったら楽しいなヽ(^o^)丿
・⑱「MOVE」の炎のリフ攻撃めっちゃカッコエエ(´∀`) 血湧き肉躍るとはまさにこのこと。
・⑳「long time no see」での稲さんの喋りにグッときた。この人いつもホンマにエエこと言うね... (;´Д`)ノ
・(21)「愛まま」で5万人のCメロ大合唱のシーンがタマラン!
・(22)「イチブトゼンブ」のバラッドverから通常verへの流れが絶妙!
・エンドロールで東京の夜景をバックに流れる「PRAY」がこれまた鳥肌モノ(≧▽≦)
とまぁ印象に残ったパートをサッと書き出してみたが、これまでのライヴとの一番の違いはとにかくユーモアたっぷりの演出で “自然と笑わせてくれる” 遊び心満載のステージに尽きると思う。それでいてキメるところはビシッとキメるのだから、ライヴであれDVDであれ十分に元を取ったという満足感で一杯だ。私にとって B'z のライヴはリアルタイムで体験できる “最高のロック・ショー” なのだ!!!
※今回のツアー映像はまだアップされてないようなので、過去のライヴ映像に音声をシンクロさせた【MAD】ヴァージョンで。この B'zMONSTER21 っていう職人さん、なかなかエエ仕事してまんなぁ...
B'z LIVE-GYM 2010 _Ain't No Magic_ at TOKYO DOME
【MAD】 Introduction ~ DIVE / B'z
【MAD】 PRAY / B'z