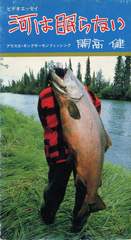| 火怨〈上〉―北の燿星アテルイ (講談社文庫)高橋 克彦講談社このアイテムの詳細を見る |
吉川英治文学賞受賞作。
時は奈良から平安へと移り変わろうとする末法の世。恐々とする都人。天皇は大仏建立を成就せんがため、それにほどこす金箔を陸奥の黄金に求めた。
東北地方の朝廷支配の最前線多賀城を中心に搾取が行われ、蝦夷の人々は謂れのない差別を受けなければならなかった。
朝廷支配に対し、それまでも近隣の蝦夷たちは小さな抵抗を続けていたが、伊治(現在の築館)の鮮麻呂の反乱をきっかけに、胆沢(現在の奥州市)の阿弖流為(アテルイ)を中心に奥六郡の蝦夷が結束する。物部氏の後ろ盾を得て、阿弖流為は朝廷軍に対抗すべく組織的軍隊を作り上げていった。大軍を繰り出してくる朝廷軍の執拗な攻撃に対して、阿弖流為たちは20年の長きに及ぶ抵抗を繰り広げる。阿弖流為の右腕となって働いた母礼(モレ)の策略もあり、最後まで負けることはなかったが、繰り返される戦で疲弊していく農民たちの姿に耐えられず、阿弖流為は自分の首と引き換えに、陸奥六郡の平和を手にすることを選んだ。
謂れのない偏見からの解放、戦のない世の中を夢見て阿弖流為たちは戦った。そしてその思いは時を経て、安倍貞任、藤原経清、清衡らに引き継がれて、奥州藤原文化として開花するのである。
内容はザッとこんな感じではないかと思うが、これは東北人高橋氏から見た歴史観であり、史実に多少の脚色がほどこされているものの、同じ東北人としてひじょうに共感出来る作品であり、胸が熱くなる思いであった。自分にも、この人たちの血が流れていると思うと、今まで以上にこの土地が愛おしくなり、そして郷土のことをもっと知りたくなるのである。