高野ムツオ(1947~)著 「語り継ぐいのちの俳句」(朔出版 2018)を、県立図書館から借りて読んだ。

この本の構成は、第1章 震災1000日の足跡、第2章 1000日以後、第3章 震災詠100句 自句自解 から成っている。
著者自身の震災体験記と震災詠には、圧倒的な訴求力と感慨深さがあると思う。
ここでは、第2章中の『「自然」と「人間」はどう詠われてきたか』から、特に心に響いた箇所を取り上げたい。
荒海や佐渡によこたふ天の河 芭蕉
芭蕉にとっての自然とは、この句のあり方が象徴的に語っていると言ってよい。それは、自然とは、まずもって悠久の存在であるということだ。
さらに、人間の営みもまた、その自然のサイクルの中に生ずる一現象に過ぎないという認識も明確だった。
そういう視点が、荒波の中の佐渡に象徴される人間世界やその上に懸かる天の川の無窮性を発見し得たと言ってよい。
芭蕉の句の凄さを再認識させられる。
明治になって俳句に写生説を主張したのは正岡子規であった。
病篤い子規にとっての緊急課題は、まず子規という人間の表現にあった。これは明治という近代意識そのものでもある。だから、子規にとっては、自然は自らの命と関わる事象事物として存在していたとも言える。
いくたびも雪の深さを尋ねけり 子規
近代俳句の自然観の成熟は、子規の継承者である高浜虚子の「花鳥諷詠」によって、さらに推し進められた。
花鳥諷詠と申しまするのは(中略)春夏秋冬四時の遷り変りによって起る天然界の現象並びにそれに伴う人事界の現象を諷詠する謂であります。(「ホトトギス昭和4年2月号」より)
ここには、自然を詠い上げることが、実はそのまま自分自身を詠い上げることになるという認識が横たわっている。そして、俳句形式と、そこに表現される自然への十全の信頼感が芭蕉同様に横たわっている。
遠山に日の当たりたる枯野かな 虚子
この句について虚子は、次のように述べている。
自分の好きな自分の句である。
どこかで見たことのある景色である。
心の中では常に見る景色である。
遠山が向うにあって、前が広漠たる枯野である。その枯野には日が当っていない。落莫とした景色である。
唯、遠山に日が当たってをる。
私はこういう景色が好きである。
わが人世は概ね日の当たらぬ枯野の如きものであってもよい。寧ろそれを希望する。ただ遠山の端に日の当たっておる事によって、心は平らかだ。
虚子の「写生」は、実景の写生ではなく、心象風景の写生だったのだ。かねてからの疑問が解けた感がある。
虚子はさらに芭蕉の「乾坤の変は風雅のたね也」という言葉を踏まえながら、その概念をより強く反映した自然現象、つまり諷詠すべき現象を「季題」と呼んだ。
しかし、芭蕉の「造化にしたがひて四時を友とす」という態度と、虚子の季題という認識方法には相違がある。芭蕉の姿勢には、変転極まりない世界そのものを、あらゆる方法で捉えていこうというダイナミズムの裏付けがあった。
それに対して、虚子の季題説は自然現象を表現契機の素材として、あらかじめ限定することから成り立つものである。その限定は、事象の季感を詠うという俳句の固有性を一段と明確化することにつながった。さらには、一見硬直化しがちな対象の限定という方法は、限定された素材の世界の豊かさを発見することにも通じた。
しかしこの限定は、同時に俳句の他の可能性を閉じてしまう危険性をも伴っていたことを否定するわけにはいかない。
虚子が季題をことさら強調したのは、明治・大正の自由律俳句や昭和の新興俳句が無季に走り、俳句の固有性が揺らぐ危険性を感じたせいである。俳句を初心者に分かりやすく説くという指導者としての啓蒙的要請もあっただろう。しかし、この方法は、リアリズム本来の持つ自然把握の仕方とは相矛盾するものであった。
言葉は新しい見方や感覚によって更新されることで生きて働くものだが、その言葉をあらかじめテーマとして意識することは、その言葉の美意識や情趣が、表現以前に作者の感性そのものに、既成認識のフィルターをかけてしまう危険を併せ持っていたからである。
そのことが、季題の力に頼るだけの概念的かつ没個性的な俳句が量産される、もう一つの傾向を生むことにもつながったのだった。
なるほど、確かに・・
昭和になって、俳句は水原秋桜子の「自然の真と文芸上の真」の主張を境に、多様な展開を見せ始める。
主体の表現意識から発想される俳句とは、本来は季題の束縛からも自由でなければならない。秋桜子は、この論で季題については一言も言及してはいないが、(中略)つまるところは、季題を表現契機としない俳句の可能性へ至る道筋にあった。秋桜子に始まった新興俳句が、叙情や表現の新しさの追求のみでなく、しだいに人間探究派と呼ばれる中村草田男や加藤楸邨の方法へと展開し、さらに新興無季俳句へ進んでゆく必然性は、この「文芸上の真」自体にもともと内包されていたのである。
鰯雲人に告ぐべきことならず 加藤楸邨
この句の「鰯雲」は、もはや季題ではなく季語と呼ぶべき位相にある。なぜなら、この句は、決して「鰯雲」から発想されたものではないからだ。
作者という個の心的有り様が、自然の諸相を見出しているのである。そのことが「鰯雲」の象徴効果をいっそう際立たせている。
こうした作り手の人間存在としての心的有り様を起点にして自然の諸現象を捉えてゆく方法は、自然の一現象としての人間よりも、人間社会の一現象としての人間の表現へと意識が傾斜していく。これは方法上の変化ではあるが、当時の社会的な情勢やそこで生きる人間の在り方と必然的なつながりを持っていた。楸邨のこの句は、日本が戦争へと突入してゆく時代のものである。「自分が何を求め、如何に生きるか」を、楸邨一人ではなく多くの若者が、自らの生死を表裏にしながら考えていた時代と言っていい。こうした人間そのものへの関心が無季俳句へと進んでいったのは、必然的な流れであったと言えよう。
戦争を詠むとは、とりもなおさず人間そのものを表現することであり、季題や季語を詠むことが第一義ではなくなる。さらには季題や季語を詠むことが自己矛盾を引き起こす。
戛々(かつかつ)とゆき戛々と征くばかり 富澤赤黄男
いっせいに柱の燃ゆる都かな 三橋敏雄
いわゆる「新興俳句」や「無季俳句」について、私の脳内にこびりついていた既成概念が剝がされていく感じがした。
もちろん自然そのものを詠う俳句も戦中に作られ続けたが、そこで生まれた作品もまた戦争という出来事とまったく無縁であったのではないと私は考えている。戦争は自然の捉え方にも、直接ではないが、さまざまに影響を及ぼしたのではないだろうか。その一例として私は虚子の小諸(虚子の疎開先)での作を挙げたい。
爛々と昼の星見え菌(きのこ)生え
虚子が戦後、新聞や雑誌の記者からの「戦争の俳句に及ぼした影響、又戦後の俳句は如何なるか」という質問に対して「私は俳句に限ってちっとも変化はない、従来の俳句の道を辿って行く許り(ばかり)である」と答えたのは有名な話だが、これは俳句形式の存亡と俳句に向かう作者の態度としての答えであって、虚子自身が受けた影響への言及ではない。実際、虚子は、この文で終戦の詔勅を聞く前の思いとして、「戦に負けて此の美はしい山川はどうなることであらうと考へた」と述べている。
いわば、花鳥諷詠という思想自体が、近代の反措定として存在していたということになる。
得体の知れない巨大な怪物のような「虚子」という人とその俳句を、少しばかり理解することが出来たような気がする。
(俳句に見られる自然観に)共通していたのは、戦争俳句や戦争をきっかけとした虚子の自然破壊への不安などを別にすれば、悠久不変である自然への全面的な信頼であったと言っていい。しかし平成二十三年に起きた東日本大震災という出来事は、自然と人間との関わりにこれまでとは異質の大きな変化をもたらした。
もう、芭蕉の時代のように自然の悠久さやその恩恵を受容するだけでは生き難い時代を生きているのである。俳句もまた、自然の運行にただ従うだけでは、時代を捉え、その時々の人間を表現する文芸として、この先も生き続けるとは思えない。俳句が本当の意味で自然とともに在り続けるためには、俳句も俳人も未来を見据えた世界観、自然観を模索していかなければならない。
しかし、大震災の教訓は既に風化へ傾斜している。原発は既に10基が再稼働しており、国は更に7基を再稼働させる方針を出した。
敗戦の教訓はもうすっかり風化し、ウクライナ問題にかこつけて軍国主義体制へまっしぐら。
野放図な経済と消費の「文明」とやらは、地球環境を破壊し尽くしている。
俳句が「生き続ける」どころか、人類が絶滅の危機に瀕している。生きものは必ず絶滅する宿命にあるが、人類は自ら、その絶滅の時を急がせているのだ。
そんな時代に生きているのだけれども、それでも「俳句」は、人が生きようとしているときの「いのち」の証しの一つになり得る、と思う。
まさにこの本のタイトル通り、「語り継ぐいのちの俳句」として。

この本の構成は、第1章 震災1000日の足跡、第2章 1000日以後、第3章 震災詠100句 自句自解 から成っている。
著者自身の震災体験記と震災詠には、圧倒的な訴求力と感慨深さがあると思う。
ここでは、第2章中の『「自然」と「人間」はどう詠われてきたか』から、特に心に響いた箇所を取り上げたい。
荒海や佐渡によこたふ天の河 芭蕉
芭蕉にとっての自然とは、この句のあり方が象徴的に語っていると言ってよい。それは、自然とは、まずもって悠久の存在であるということだ。
さらに、人間の営みもまた、その自然のサイクルの中に生ずる一現象に過ぎないという認識も明確だった。
そういう視点が、荒波の中の佐渡に象徴される人間世界やその上に懸かる天の川の無窮性を発見し得たと言ってよい。
芭蕉の句の凄さを再認識させられる。
明治になって俳句に写生説を主張したのは正岡子規であった。
病篤い子規にとっての緊急課題は、まず子規という人間の表現にあった。これは明治という近代意識そのものでもある。だから、子規にとっては、自然は自らの命と関わる事象事物として存在していたとも言える。
いくたびも雪の深さを尋ねけり 子規
近代俳句の自然観の成熟は、子規の継承者である高浜虚子の「花鳥諷詠」によって、さらに推し進められた。
花鳥諷詠と申しまするのは(中略)春夏秋冬四時の遷り変りによって起る天然界の現象並びにそれに伴う人事界の現象を諷詠する謂であります。(「ホトトギス昭和4年2月号」より)
ここには、自然を詠い上げることが、実はそのまま自分自身を詠い上げることになるという認識が横たわっている。そして、俳句形式と、そこに表現される自然への十全の信頼感が芭蕉同様に横たわっている。
遠山に日の当たりたる枯野かな 虚子
この句について虚子は、次のように述べている。
自分の好きな自分の句である。
どこかで見たことのある景色である。
心の中では常に見る景色である。
遠山が向うにあって、前が広漠たる枯野である。その枯野には日が当っていない。落莫とした景色である。
唯、遠山に日が当たってをる。
私はこういう景色が好きである。
わが人世は概ね日の当たらぬ枯野の如きものであってもよい。寧ろそれを希望する。ただ遠山の端に日の当たっておる事によって、心は平らかだ。
虚子の「写生」は、実景の写生ではなく、心象風景の写生だったのだ。かねてからの疑問が解けた感がある。
虚子はさらに芭蕉の「乾坤の変は風雅のたね也」という言葉を踏まえながら、その概念をより強く反映した自然現象、つまり諷詠すべき現象を「季題」と呼んだ。
しかし、芭蕉の「造化にしたがひて四時を友とす」という態度と、虚子の季題という認識方法には相違がある。芭蕉の姿勢には、変転極まりない世界そのものを、あらゆる方法で捉えていこうというダイナミズムの裏付けがあった。
それに対して、虚子の季題説は自然現象を表現契機の素材として、あらかじめ限定することから成り立つものである。その限定は、事象の季感を詠うという俳句の固有性を一段と明確化することにつながった。さらには、一見硬直化しがちな対象の限定という方法は、限定された素材の世界の豊かさを発見することにも通じた。
しかしこの限定は、同時に俳句の他の可能性を閉じてしまう危険性をも伴っていたことを否定するわけにはいかない。
虚子が季題をことさら強調したのは、明治・大正の自由律俳句や昭和の新興俳句が無季に走り、俳句の固有性が揺らぐ危険性を感じたせいである。俳句を初心者に分かりやすく説くという指導者としての啓蒙的要請もあっただろう。しかし、この方法は、リアリズム本来の持つ自然把握の仕方とは相矛盾するものであった。
言葉は新しい見方や感覚によって更新されることで生きて働くものだが、その言葉をあらかじめテーマとして意識することは、その言葉の美意識や情趣が、表現以前に作者の感性そのものに、既成認識のフィルターをかけてしまう危険を併せ持っていたからである。
そのことが、季題の力に頼るだけの概念的かつ没個性的な俳句が量産される、もう一つの傾向を生むことにもつながったのだった。
なるほど、確かに・・
昭和になって、俳句は水原秋桜子の「自然の真と文芸上の真」の主張を境に、多様な展開を見せ始める。
主体の表現意識から発想される俳句とは、本来は季題の束縛からも自由でなければならない。秋桜子は、この論で季題については一言も言及してはいないが、(中略)つまるところは、季題を表現契機としない俳句の可能性へ至る道筋にあった。秋桜子に始まった新興俳句が、叙情や表現の新しさの追求のみでなく、しだいに人間探究派と呼ばれる中村草田男や加藤楸邨の方法へと展開し、さらに新興無季俳句へ進んでゆく必然性は、この「文芸上の真」自体にもともと内包されていたのである。
鰯雲人に告ぐべきことならず 加藤楸邨
この句の「鰯雲」は、もはや季題ではなく季語と呼ぶべき位相にある。なぜなら、この句は、決して「鰯雲」から発想されたものではないからだ。
作者という個の心的有り様が、自然の諸相を見出しているのである。そのことが「鰯雲」の象徴効果をいっそう際立たせている。
こうした作り手の人間存在としての心的有り様を起点にして自然の諸現象を捉えてゆく方法は、自然の一現象としての人間よりも、人間社会の一現象としての人間の表現へと意識が傾斜していく。これは方法上の変化ではあるが、当時の社会的な情勢やそこで生きる人間の在り方と必然的なつながりを持っていた。楸邨のこの句は、日本が戦争へと突入してゆく時代のものである。「自分が何を求め、如何に生きるか」を、楸邨一人ではなく多くの若者が、自らの生死を表裏にしながら考えていた時代と言っていい。こうした人間そのものへの関心が無季俳句へと進んでいったのは、必然的な流れであったと言えよう。
戦争を詠むとは、とりもなおさず人間そのものを表現することであり、季題や季語を詠むことが第一義ではなくなる。さらには季題や季語を詠むことが自己矛盾を引き起こす。
戛々(かつかつ)とゆき戛々と征くばかり 富澤赤黄男
いっせいに柱の燃ゆる都かな 三橋敏雄
いわゆる「新興俳句」や「無季俳句」について、私の脳内にこびりついていた既成概念が剝がされていく感じがした。
もちろん自然そのものを詠う俳句も戦中に作られ続けたが、そこで生まれた作品もまた戦争という出来事とまったく無縁であったのではないと私は考えている。戦争は自然の捉え方にも、直接ではないが、さまざまに影響を及ぼしたのではないだろうか。その一例として私は虚子の小諸(虚子の疎開先)での作を挙げたい。
爛々と昼の星見え菌(きのこ)生え
虚子が戦後、新聞や雑誌の記者からの「戦争の俳句に及ぼした影響、又戦後の俳句は如何なるか」という質問に対して「私は俳句に限ってちっとも変化はない、従来の俳句の道を辿って行く許り(ばかり)である」と答えたのは有名な話だが、これは俳句形式の存亡と俳句に向かう作者の態度としての答えであって、虚子自身が受けた影響への言及ではない。実際、虚子は、この文で終戦の詔勅を聞く前の思いとして、「戦に負けて此の美はしい山川はどうなることであらうと考へた」と述べている。
いわば、花鳥諷詠という思想自体が、近代の反措定として存在していたということになる。
得体の知れない巨大な怪物のような「虚子」という人とその俳句を、少しばかり理解することが出来たような気がする。
(俳句に見られる自然観に)共通していたのは、戦争俳句や戦争をきっかけとした虚子の自然破壊への不安などを別にすれば、悠久不変である自然への全面的な信頼であったと言っていい。しかし平成二十三年に起きた東日本大震災という出来事は、自然と人間との関わりにこれまでとは異質の大きな変化をもたらした。
もう、芭蕉の時代のように自然の悠久さやその恩恵を受容するだけでは生き難い時代を生きているのである。俳句もまた、自然の運行にただ従うだけでは、時代を捉え、その時々の人間を表現する文芸として、この先も生き続けるとは思えない。俳句が本当の意味で自然とともに在り続けるためには、俳句も俳人も未来を見据えた世界観、自然観を模索していかなければならない。
しかし、大震災の教訓は既に風化へ傾斜している。原発は既に10基が再稼働しており、国は更に7基を再稼働させる方針を出した。
敗戦の教訓はもうすっかり風化し、ウクライナ問題にかこつけて軍国主義体制へまっしぐら。
野放図な経済と消費の「文明」とやらは、地球環境を破壊し尽くしている。
俳句が「生き続ける」どころか、人類が絶滅の危機に瀕している。生きものは必ず絶滅する宿命にあるが、人類は自ら、その絶滅の時を急がせているのだ。
そんな時代に生きているのだけれども、それでも「俳句」は、人が生きようとしているときの「いのち」の証しの一つになり得る、と思う。
まさにこの本のタイトル通り、「語り継ぐいのちの俳句」として。












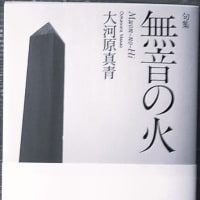

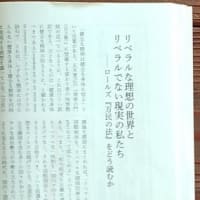
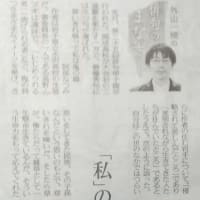
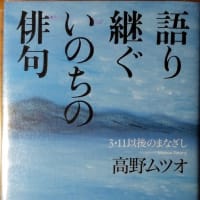
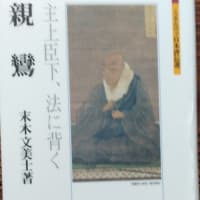


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます