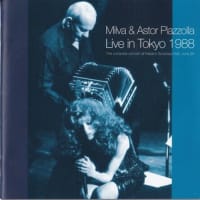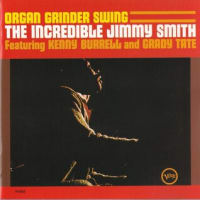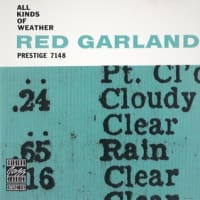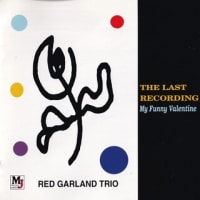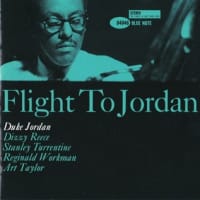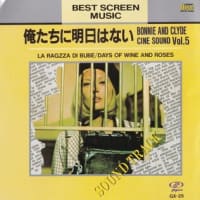●梨花と春雨
白居易の詩に、「梨花一枝、春、雨を帯びたり」とある。楊貴妃の美しさを「梨の花が春雨にけむっているようだ」とたたえている。
梨は、桜などと同じバラ科の樹木で、春に、白い五弁の花をつける。シンプルで美しい。
知り合いに、梨花という名前の美女がいる。今度会ったら、その名のいわれを尋ねよう。
●和梨の盛衰
梨の花は春に咲く。そして、暑い季節に実をつける。
梨は、和梨と洋梨とか、赤梨と青梨と言うように分類される。
わたしが子どもの時分には、洋梨を見かけることはまずなかった。
和梨の長十郎とか二十世紀と呼ばれる梨をよく口にした。
今では、これらは、店頭での主役ではなくなってしまった。幸水とか豊水という梨の人気が高まり、多く生産され、よく食されるようになった。
梨の世界にも、時の移ろいによる盛衰がある。
ここでは、脇役となるつつある梨のことをしっかり記憶にとどめておきたいと思う。
わたしは、長十郎のかための実でザラザラした食感もいいと思ったが、暑い季節には、なんともみずみずしく、そのさっぱり感、風味もいい二十世紀梨が好きだった。
それもそのはず、二十世紀梨の水分は、なんと八十九パーセントで、解熱にも効力を発揮する。
●二十世紀梨の出自
その二十世紀梨のことである。
時は十九世紀、一八八八年、千葉県松戸のゴミ捨て場で、一人の少年によって、偶然に発見されたのである。
少年は、その木を父の農園に移植し、十年の時を経て実が結ばれるようになったと言う。
その実には、それまでにないみずみずしさと甘みがあった。
来世紀の代表的な梨になるようにとの期待のもと、二十世紀梨と命名された。
そして、期待どおりに二十世紀の売れっ子になった。
ただ、二十世紀梨には、「自家不和合性」という性質がある。同じバラ科の染井吉野もそうなのだが、同じ木の花粉では受粉しないのである。それは、多様な子孫を残し、種を存続させるために大切な性質ともいえるが。
そのうえ、ほとんど自然交配をしないそうだ。と言うことは、実をつけさせるためには、他の品種の花粉を手間隙かけて人工受粉させなくてはならない。
つまり、二十世紀梨の味を守り、増やすには、接ぎ木、接ぎ木で同じ遺伝子をもつものを増やし、手間のかかる受粉作業をしなくてはならいと言うことになる。
生産量がおちているにのは、その栽培のやっかいさも一因しているようである。
時節柄、美女と一緒に梨を食べる機会もあるだろう。そんな時の話題に、こんな豆知識が役に立つこともあるかも。
●老いし小野小町
謡曲「鸚鵡小町」に、老いた小野小町の霊が現れる。若き日、男たちの胸を焦がらせた女とされる小町だが、衰えたわが身の姿をこう語る。
昔は芙蓉の花たりし身なれども
今は藜藋の草となる
顔ばせは憔悴と衰へ
膚は凍梨の梨のごとし
「時、人を待たぬ」。誰しも、いつしか老い、「あら恋しの昔やな」と。
凍った梨のような膚とは、なんとも無惨だが、老いれば、それも現実。
ゆえに、みずみずしいうちに、それゆえに得られる愉悦をと。
(月刊誌「改革者」1918年8月号)
白居易の詩に、「梨花一枝、春、雨を帯びたり」とある。楊貴妃の美しさを「梨の花が春雨にけむっているようだ」とたたえている。
梨は、桜などと同じバラ科の樹木で、春に、白い五弁の花をつける。シンプルで美しい。
知り合いに、梨花という名前の美女がいる。今度会ったら、その名のいわれを尋ねよう。
●和梨の盛衰
梨の花は春に咲く。そして、暑い季節に実をつける。
梨は、和梨と洋梨とか、赤梨と青梨と言うように分類される。
わたしが子どもの時分には、洋梨を見かけることはまずなかった。
和梨の長十郎とか二十世紀と呼ばれる梨をよく口にした。
今では、これらは、店頭での主役ではなくなってしまった。幸水とか豊水という梨の人気が高まり、多く生産され、よく食されるようになった。
梨の世界にも、時の移ろいによる盛衰がある。
ここでは、脇役となるつつある梨のことをしっかり記憶にとどめておきたいと思う。
わたしは、長十郎のかための実でザラザラした食感もいいと思ったが、暑い季節には、なんともみずみずしく、そのさっぱり感、風味もいい二十世紀梨が好きだった。
それもそのはず、二十世紀梨の水分は、なんと八十九パーセントで、解熱にも効力を発揮する。
●二十世紀梨の出自
その二十世紀梨のことである。
時は十九世紀、一八八八年、千葉県松戸のゴミ捨て場で、一人の少年によって、偶然に発見されたのである。
少年は、その木を父の農園に移植し、十年の時を経て実が結ばれるようになったと言う。
その実には、それまでにないみずみずしさと甘みがあった。
来世紀の代表的な梨になるようにとの期待のもと、二十世紀梨と命名された。
そして、期待どおりに二十世紀の売れっ子になった。
ただ、二十世紀梨には、「自家不和合性」という性質がある。同じバラ科の染井吉野もそうなのだが、同じ木の花粉では受粉しないのである。それは、多様な子孫を残し、種を存続させるために大切な性質ともいえるが。
そのうえ、ほとんど自然交配をしないそうだ。と言うことは、実をつけさせるためには、他の品種の花粉を手間隙かけて人工受粉させなくてはならない。
つまり、二十世紀梨の味を守り、増やすには、接ぎ木、接ぎ木で同じ遺伝子をもつものを増やし、手間のかかる受粉作業をしなくてはならいと言うことになる。
生産量がおちているにのは、その栽培のやっかいさも一因しているようである。
時節柄、美女と一緒に梨を食べる機会もあるだろう。そんな時の話題に、こんな豆知識が役に立つこともあるかも。
●老いし小野小町
謡曲「鸚鵡小町」に、老いた小野小町の霊が現れる。若き日、男たちの胸を焦がらせた女とされる小町だが、衰えたわが身の姿をこう語る。
昔は芙蓉の花たりし身なれども
今は藜藋の草となる
顔ばせは憔悴と衰へ
膚は凍梨の梨のごとし
「時、人を待たぬ」。誰しも、いつしか老い、「あら恋しの昔やな」と。
凍った梨のような膚とは、なんとも無惨だが、老いれば、それも現実。
ゆえに、みずみずしいうちに、それゆえに得られる愉悦をと。
(月刊誌「改革者」1918年8月号)