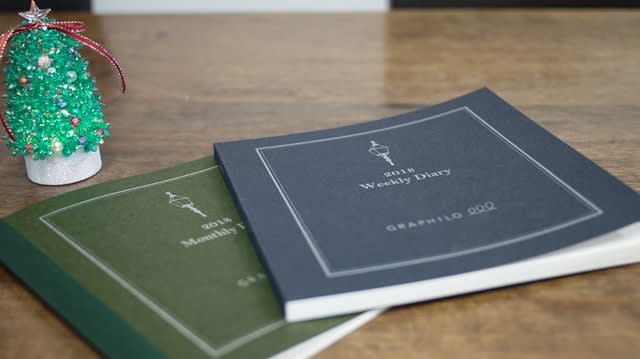一昨日の垂水区
あれから7年も経つと思うと、申し訳ないけれどのうのうと生きてきてしまった私にはその時間の流れはとても早く感じられる。しかし、被災して生活を立て直さなければならなかった人には時間の経過が遅く感じられる長い7年間だったと思います。
津波に流されて亡くなった方は、さぞ怖くて冷たい想いをしたと思うし、帰らぬ家族を待つ人はどうやって前を向けばいいのだろう。
人災と言われている原発事故で自分の町に住めなくなって今までの生活を送れなくなっている人はさぞ無念な想いをしているだろうと思う。都会で大量に消費する電力に対してのリスクをなぜ地方の人が負わないといけないのだろう。
私のような薄っぺらい人間に被災された方々にかける言葉は見つからず、その心中を想像して、理不尽なことに怒りを覚えることしかできない。
息子の引っ越しで横浜に行ってきた。
東京は行くことがありますが、横浜で降りることはほとんどなく、その辺り大阪までは来るけれど、神戸まで行くことがないとよく言われることによく似ている。
息子がマンションを借りた南区も、ブルーラインという地下鉄も初めてでここはどんな街なのかと2日間探りながらいましたが、横浜はとても大きな街だということしか分からなかった。
横浜駅周辺は密度の高い都会で、行き交う人も非常に多かったし、息子のマンションの周辺は人の姿をあまり見かけませんでしたが、高い建物ばかりが立ち並んでいました。
元々は1戸建てや商店が建っていたけれど、それらが老朽化して、どんどん取り壊されて新しい建物に建て替わっていっているようでした。
こんな都会の片隅に神戸から行かなければいけない理由とは何だろうと思う。
もちろん神奈川県の教員採用試験に受かったから横浜に来たのだけど、息子は兵庫県に残りたいと思っていた。
地元に残りたいと思っている若者が、仕事の口がなく、仕方なく首都圏に出て行く。典型的な日本の構図が我が家でも描かれるとは思ってもみなかった。
横浜はたしかに神戸から近く、垂水からだと3時間くらいで行けてしまう。
交通網の発達は地方を活性化させるという側面もあるのかもしれないけれど、それ以上に地方からの人口の流出を招いているのかもしれません。でもそれはどうしようもない世の中の流れなのかもしれない。
移動時間が短くなって、狭い日本がより狭くなって、各地域の独立性はとっくに失われていて、それは江戸時代にとっくに終わっていたのかもしれません。
それぞれの地域が東京と同じような役割をすることはナンセンスで、首都圏は仕事をする場所、地方はたまに帰る場所、遊びに行くところになっているような気がします。
地方を首都圏の従属的な立場として考えることは、神戸という地方を元気にしたいと思っている私にとって、とても悲しいことだけど、世の中の流れはそうなっている。
息子が横浜に住むという話から、思わぬ方向に話が向いてしまったけれど、人一人が新たに生活を始めるのに、こんなにも必要なものがあるのかと改めに思いました。
考えてみたら3人で住んでいると、3人で生活用品を共用しているけれど、一人だからそれが少なくて済むわけではなく、同じ数だけのものがいるから当然なのかもしれない。
横浜で新しい生活を始めた息子とマンションで別れてきたけれど、私たち夫婦も二人だけの新生活を軌道に乗せないといけないと思っている。