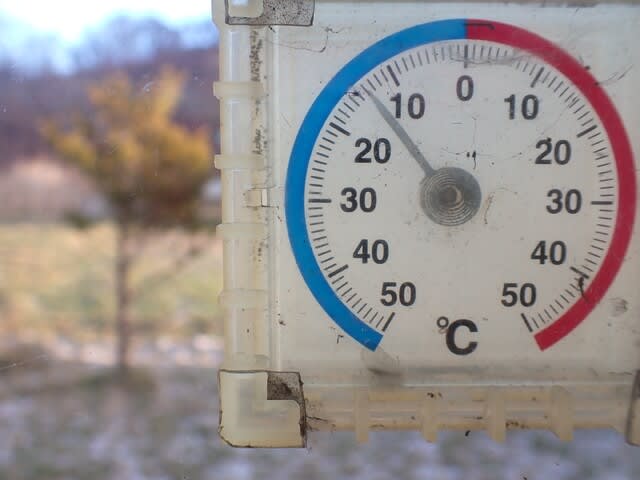恩師一条先生が亡くなられた。
那須に居るときに研究室の後輩が連絡をくれた。
ー
私は一条先生を獣医師としての自分の父とも思い過ごしてきた。
奇しくも同居している父と一条先生は同い年。昭和4年(1929年)の生まれ。
先生の教えを受けなければ今の自分はなかったと思う。
ー
研究室の教授と一学生だったので、親しくお話しできるような関係ではなかった。
卒業してからも電話をするにも緊張した。
お忙しいかも、と思いながら電話すると、「はい、一条です」と暗い声で出られる。
「higです」と名乗ると、
「お~、hig君、元気かい」と、急に声のトーンが明るくなる。
いつも、なんだか嬉しくなった。
ー
学生の頃から、ご自身の臨床への情熱も何度も語って下さった。
「もっと臨床をやりたい気持ちもあったんだけどね」
帯広市街にあった家畜病院分院の閉鎖も残念がっておられた。
閉鎖されたのは昭和45年(1970年)の話。
「臨床家は腰が軽くなきゃだめだ」ともおっしゃっていた。
面倒がらず、自分で診に行き、自分で調べてみること、やってみることの重要性を教えて下さった。
ご自身では、臨床と研究をつなぐ研究を進められ、多くの論文を書かれていた。
ー
私が研究室に所属していた頃でも、
白筋症の研究で、微量元素セレニウムを測定していたし、
液体クロマトグラフィーでヴィタミンEを測定も測定していたし、
大脳皮質壊死症の研究で、ヴィタミンB1を測定していたし、
イヌとネコのパルボウィルスの感染実験をしていて、骨髄検査もしていたし、
電子顕微鏡で感染病理も調べていた。
それでいて、一条先生のところにはあちこちから難症例の相談が来るので、
それらが来院したり、ときには往診することもあった。
ー
だからその当時の帯広畜産大学内科学教室に居ると、
ヴィタミン欠乏症、微量元素欠乏症、小動物、ウィルス感染症、血液病、骨髄穿刺、神経病、皮膚病、真菌症、などなどなど、
今から思えば、信じられないような多彩な症例を診て、多岐にわたる勉強をすることができた。
そして、一条先生は馬の経験も豊富な先生で、
馬の扱い、眼結膜の観察の方法や、重種馬を枠場に入れて肢を平打ち縄で固定する方法などを、手際よく見せてくださったりした。
ー
多くの委託研究も受けられていたので、ホル牡㸿の農場を回って抗菌剤の効果の試験をしたり、実験馬を集めてイベルメクチンの駆虫試験をしたりもした。
それらの手伝いをしながら、学生たちは多くのことを学ぶことができた。
ー
全道の農業共済組合の家畜診療所に教え子、卒業生、知合いが居るので、研究調査の依頼ができたり、
学生の臨床実習を頼んでくださったりもした。
私も大学院生のとき、「馬の診療を見てみたいんですけど・・・・」と言ったら、
「あ~それなら電話しといたげる」となって、三石へ実習に行くことになった。
ー
日高地区農業共済組合に就職が内定していたころ、
「hig君、挨拶に行こう」
と、組合長をはじめ組合に一緒に挨拶に出向いてくださった。
忙しい1日を割いて、卒業生ひとりのために。
修士論文のテーマとして取り組んだ子馬の白筋症の調査が良い結果が出たので、
就職してすぐになるが、春の日本獣医学会で発表させてやってほしい、と頼む目的もあったようだ。
ー
「hig君、早く論文にまとめろよ」と急かしてもくださった;笑
「学会発表だけじゃあダメなんだ。何も残らない。書かないと価値がない」と何度もおっしゃった。
私が、臨床をやりながら、少しずつでも調査研究論文を書いてきたのは、先生の教えによる。
evidenceとか、EBMなどという言葉さえなかった時代だが、一条先生もまたその先駆者のお一人だった。
教授になると、ろくに研究せず、教育にも情熱を失っているのが学生にもわかる教官もいる時代だった。
ー
私に、大学の教官に来ないかという話があったとき、一条先生のお宅を訪ねて相談した。
「昔から10年以上勤められるなら大学へ移ったら良い。それより短期ならヤメテおいた方が良い、って言うんだ。
君ならまだ十分時間があるから、やったらいい」
と勧めてくださった。
大学の仕事に慣れ、まとまった仕事をするためには10年かかるという、長く大学に勤め、自らだけでなく多くの教授たちを見てきた一条先生のアドバイスだった。
諸事情で私は大学に勤めることはなかったが、貴重なアドバイスだったと思っている。
ー
一条先生が定年退官された平成5年(1993)に刊行された「四十三年の回想」。
当時、帯広畜産大学の定年退官は63歳になった翌年3月ということだった。
研究業績目録によれば、論文が196編。
著書が12冊。
翻訳書が2冊。
総説その他が51編。
学会発表が207題。
修士論文と卒業論文が41編。
ー
この序文に、内科学教室で勉強し、酒を酌み交わした「多くの未来ある学生」との出会いが最も強い印象であった、と書いておられる。
臨床と、研究と、大学人としての業務と、いそがしい中で教官、教育者としての覚悟を持った先生であった。
ー
「ボクらがしっかりしないと、卒業生が肩身の狭い思いをするんだからね」
と何度もおっしゃっていた。
臨床と大学をつなぐ仕事をされ、卒業生とのつながりを大切にされた先生でもあった。
ー
ご経歴の賞罰で、二度だけ北海道獣医師会長賞が記されている。
「私は教育者で大学で研究をしているのだから、他の獣医さんと同じように賞をもらうわけにはいかない」
と、獣医師会の学会での受賞はいつも辞退されていた。
学会発表の内容や態度についても、いくつも厳格な視点をもっておられた。
それでいて、「あそこでボクが手を挙げてコメントすると萎縮させるから遠慮したんだ」
と優しい配慮をされる先生でもあった。
ー
私は善い師に出会えて幸せだった。
ー