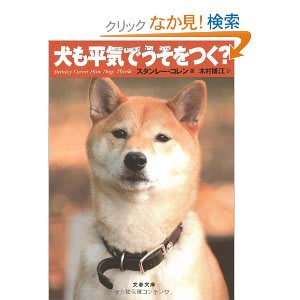ほとんどの動物には「ヤコブソン器官」あるいは「鋤鼻器」と呼ばれる匂いを感じるもうひとつの器官が発達している。
鼻腔と口腔の間にあって・・・などと言われるが、ヒトには感じられることがないせいかイメージしにくい。
(イメージも「画像」だ。匂いについて「イメージする」に相当する言葉はないか・・・・)
そもそも鋤鼻という名前のもとは何か?
-
頭は、頭蓋骨と下顎骨の2つ。としてしまえれば楽なのだけれど、
実は、切歯骨、鼻骨、頬骨、涙骨、上顎骨、口蓋骨などの顔面骨と、前頭骨、側頭骨、後頭骨、頭頂間骨、蝶形骨、篩骨、などの狭義の頭蓋骨からなっている。
(その中に神経や血管が通っている孔があちこち開いているし、
動物種によって頭蓋骨の形はひどく異なるので、
「とっても覚えられないヤ」と獣医解剖学の最初の大きな関門だった;笑
今、眼窩上孔や眼窩下孔や頤(オトガイ)孔に針を刺すようになるとは可笑しなものだ。)
その数多くの頭の骨の中に鋤(スキ)骨がある。
-
(左)
たしかに鋤なんて言われても、実際に使うことや見ることはもうないだろう。
(右図19)
たしかに鋤の形だ。
(左図11)
切歯骨に孔が開いていて、鼻腔と口腔がつながっていることにも注意。
本来、ほとんどの動物で鼻腔と口腔はつながっていて、口腔から匂いを嗅ぐための器官が鋤鼻器なのだ。
ヘビやトカゲは、チョロチョロと舌を出しているが、あれは舌で匂いを鋤鼻器へ運んでいるらしい。
-
(左図5)
馬の鋤鼻器は発達しているとは言えず、
盲端になっていて口腔へも開いてはいない。
(右)
-
さて、この鋤鼻器。
多くの動物でフェロモンを嗅ぎ取る器官として重要らしい。
よく馬の笑い顔として、フレーメンをしている顔が紹介されるが、
あれはこの鋤鼻器に多くの香りを取り込んで、匂いを感じようとしている顔らしい。
発情がある雌馬や、交配前の種牡馬がしばしばフレーメンをするのはそれが理由なのだ。
(ネコのフレーメンはしかめっ面に見えるのだそうだ。イヌはフレーメンをしない。なぜ?)
-
人でも化粧品メーカーや香水会社はヒトに効果があるフェロモンを一生懸命探しているし、
実際にいろいろなものを混ぜているようだが、
ヒトを初め霊長類の鋤鼻器は痕跡が残っているだけで、嗅細胞もなく、神経細胞も脳へつながっておらず、脳の嗅球にも他の動物種に認められるような特殊領域はないそうだ。
ふつうに匂いを感じる部分でフェロモンに反応している可能性はあるらしいが・・・・
私のように鼻が利かない者にはさっぱり。笑