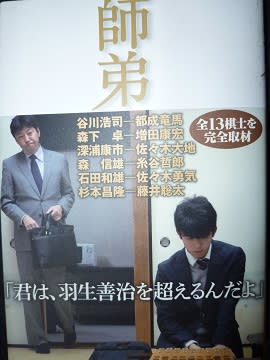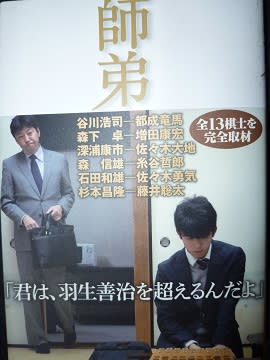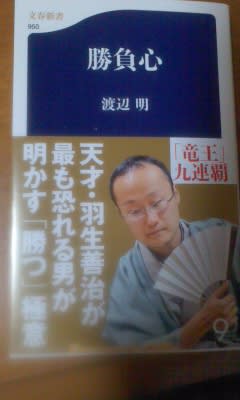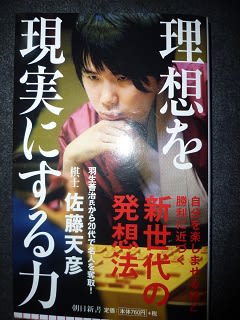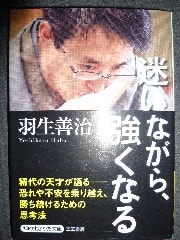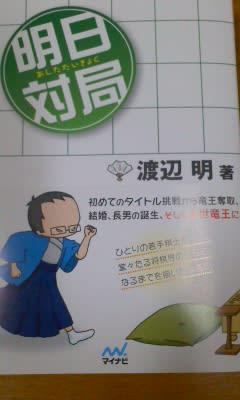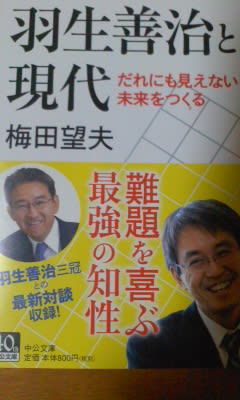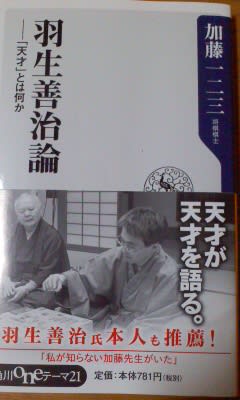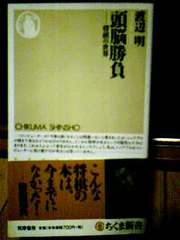スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
久しぶりに将棋の本を紹介します。これが8冊目です。一昨年の6月30日に光文社から発刊された野澤亘伸の「師弟 棋士たち魂の伝承」です。第二部定理四四系二 の,永遠の相の下に quadam aeternitatis specieというスピノザの記述を意識していました。アンチクリスト Der Antichrist 』には確かに蜘蛛の比喩が出てくるのですが,スピノザ自身が蜘蛛に喩えられているとはいえない面があります。むしろその比喩の対象は,神だと解せそうです。
昨年度の将棋大賞 は1日に発表されました。渡辺明三冠 。棋聖に挑戦 ,奪取 。A級優勝で名人挑戦。棋王を防衛 。王将を防衛 。日本シリーズに優勝 。昨年度,最も活躍した棋士なので当然の受賞。2012年度 以来,7年ぶり2度目の最優秀棋士賞受賞。挑戦 ,奪取 。この奪取の一局が名局賞に選出されています。昨年度の実績はこれだけですが,史上最年長でタイトルを獲得したことが評価されることになりました。特別賞は初受賞。挑戦 ,奪取 。叡王に挑戦 。銀河戦に優勝 。実績的には渡辺三冠と甲乙つけ難いところがあります。タイトルをひとつ防衛していれば,逆になったかもしれません。優秀棋士賞は初受賞。奪取 。王座に挑戦 ,奪取 。実績的にはナンバー3で,これも当然の受賞。敢闘賞は初受賞。記録部門の連勝賞も15連勝で獲得しました。挑戦 。タイトル戦出場までいったのが大きく評価されました。ただ真価を問われるのはこれからだと思います。奪取 。初代清麗を獲得 。倉敷藤花を防衛 。女流名人を防衛 。女流棋士だけが受賞の対象なので当然でしょう。2009年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2012年度,2013年度 ,2015年度 ,2016年度 ,2017年度 ,2018年度 に続き5年連続10回目の最優秀女流棋士賞受賞。挑戦 。女流棋士の中での実績はナンバー2です。ただ該当者なしもあり得るところだったと思います。2017年度以来,2年ぶり2度目の優秀女流棋士賞受賞。記録部門の女流最多対局賞も受賞しました。第四局 。名局賞特別賞は王将戦の挑戦者決定リーグの最終戦で,広瀬章人竜王(当時)が藤井聡太七段を破って挑戦を決定した一局。最終盤での逆転でした。カヴァイエス Jean Cavaillèsやゲルー Martial Gueroultは自身の政治的な立場をスピノザの哲学によって基礎づけようとはしなかったということの対比で記述しています。しかしこのようにいってしまうと,スピノザの哲学においては排除されるべき主体 subjectumという概念notioが入り込んできてしまうのです。ですから,それが事実であるかどうかの見解の相違は別として,もしもこのことを主張しようとするのであれば,アルチュセールがドゥサンティ Jean-Toussaint Desantiを批判した文脈,ドゥサンティの思想のうちには実存主義の残骸が含まれていて,意味によって自我すなわち主体を基礎づけているという部分との比較でいう方が,スピノザの哲学との関連の中ではよいのではないかと僕には思えます。
2018年度の将棋大賞 は1日に発表されました。挑戦 ,奪取 。王位挑戦 ,奪取 。A級順位戦優勝。もとより力がある棋士ということは分かっていましたが,昨年度は飛躍の一年となりました。2017年度 の敢闘賞で最優秀棋士賞は初受賞。渡辺明二冠 。王将挑戦,奪取 。棋王防衛 。記録部門の連勝賞も受賞。勝ちまくった棋士のひとりで,最優秀棋士賞でもおかしくないところでした。2005年度 ,2008年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2015年度 に続き3年ぶり6度目の優秀棋士賞。広瀬章人竜王 。竜王挑戦 ,奪取 。棋王挑戦 。記録部門の最多対局賞も受賞。こちらも勝ちまくりましたが,今年に入ってやや失速。棋王戦は優秀棋士賞の争いでもあったことになります。2010年度以来8年ぶり2度目の敢闘賞。優勝 。新人王戦を優勝した藤井聡太七段が,昨年度の新人賞ということでこちらに回ってきました。初受賞。防衛 。女流王座防衛 。倉敷藤花防衛 。女流名人防衛 。マイナビ女子オープン挑戦 。これは当然。2009年度 ,2010年度,2011年度,2012年度 ,2013年度 ,2015年度,2016年度 ,2017年度に続き4年連続9度目の受賞。奪取 (挑戦決定は2017年度内)。第一人者からタイトルを奪取したのですからこちらも当然でしょう。日本将棋連盟主催の賞ですが,所属団体は無関係のようです。初受賞。女流王位戦五番勝負は4局全体で女流名局賞に選出されました。神 Deusが超越論的な神であるなら,神学は集合論を支える形而上学になり得ると僕は予想します。もちろん僕は,外延と内包というのが集合論においてどういった概念notioであるのかが分からないということは何度もいっている通りですが,上野のいい方はスピノザは内包を認めないというもので,これは外延なら認めると受け取ることができることは説明しました。よってこの説明は,集合論における外延の形而上学的位置は,スピノザの哲学における神に該当するというように僕は読解するのです。僕自身は,スピノザの形而上学は,外部と内部という区分自体を認めないというものだと考えますから,もし上野がいっていることが僕の読解の通りであるなら,この考え方には同調はしません。ですがもし外延を神学における神であると解するなら,外延の形而上学的位置が,神学における神の形而上学的位置に一致すると思います。そして上野の説明の仕方からは,そうである可能性が高いだろうと思うのです。なのでたぶん集合論というのは,神学と一致する形而上学的背景を有する論理なのではないでしょうか。
将棋関連の書籍のレビューはこれが7冊目。2017年4月に発売された佐藤天彦の『理想を現実にする力』です。第一部公理三 とか第一部公理四 は,佐藤が物事を考える上での基軸になっています。おそらく佐藤はスピノザの哲学のことなどは何も知らないでしょうし,スピノザという名前さえ知らないかもしれません。しかしスピノザの哲学が実践 を伴うものであり,かつスピノザの思想に則した実践を行う者こそがスピノザ主義者なのだというのであれば,佐藤はたぶんスピノザ主義者です。そして佐藤に限らず,この種のスピノザ主義者というのは,数多くではないにしても,確かにこの世界のうちに存在しています。たとえその人がスピノザを知らないのだとしても。従兄 の葬儀でした。式場は同じ瀬谷ですから,僕は相鉄で瀬谷に向い,そこから歩きました。その後,マイクロバスで北部斎場に行き,そこで従兄を火葬しました。北部斎場は僕の父を火葬した斎場です。その後で再び瀬谷の式場に戻り,初七日の法要を執り行いました。前日の夜と同様に,この日も僕は父のすぐ上の兄に自動車で二俣川まで送ってもらいました。合併症 の検査の日でした。医師は診察のときには僕に対してみっつの検査を指示しましたが,その日の会計を済ませたときに同時に出てくる次回の診察の予約票によれば,実際に行われる検査はよっつありました。それらの検査は予約時間があり、最も早いものが自律神経の検査で,午前11時となっていました。ただ,前日の雪の影響が残ってバスがやや遅れてしまったため,僕が病院に着いたときにはその時刻を少しばかり過ぎていました。中央検査室 で行われます。なので予約票を所定の機械から印字したら中央検査室に直行しました。すると窓口の担当者が,超音波の検査はすぐできるので,まず最初にそれを受診するようにと指示しました。これは本来の予約時間では午後2時半になっていたものです。これは頸動脈に超音波を当てて血管を調べる検査です。11時25分にはこの検査は終了しました。
2日に2017年度の将棋大賞 が発表されました。防衛 ,竜王挑戦 ,奪取 ,名人挑戦。堅調な成績とはいい難いのですが,竜王を奪取したことにより現時点で可能なタイトルのすべての永世ないしは名誉の称号を獲得し,国民栄誉賞を受賞したことも考慮に入れられたものだろうと思います。1988年度,1989年度,1992年度,1993年度,1994年度,1995年度,1996年度,1998年度,1999年度,2000年度,2001年度,2002年度,2004年度,2005年度,2007年度 ,2008年度 ,2009年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2014年度 ,2015年度 に続き2年ぶり22度目の最優秀棋士賞。挑戦 ,奪取 。王位戦で羽生竜王を圧倒したことが評価の対象となったものでしょう。同じように王座を奪取した中村太地王座より勝利数や勝率で上回っていた分,こちらが選出されたということだと思います。初受賞。優勝 。藤井六段は記録四部門の最多対局賞,最多勝利賞,勝率1位賞,最多連勝賞をすべて受賞。最優秀棋士賞でもよかったと思いますが,すぐに獲得することになるのだろうと思います。当然ながらいずれも初受賞。防衛 ,女流王将防衛 ,倉敷藤花防衛 ,女流王座防衛 ,女流名人防衛 。これは当然の受賞。2009年度,2010年度,2011年度,2012年度 ,2013年度 ,2015年度,2016年度 に続き3年連続8度目の受賞。挑戦 (決定は昨年度),女流王将挑戦 ,倉敷藤花挑戦 ,女流名人挑戦。いずれも跳ね返されてしまいましたが,こちらも当然の受賞でしょう。初受賞。女流最多対局賞も初受賞となっています。竜王戦第四局 。そうそうお目にかかれない寄せの手順と僕自身が書いた将棋なので納得です。第四部付録第二四項 においては,憤慨が否定される理由として興味深いことが示されていますので,これも検討しておきましょう。第四部定理四五 で憎しみodiumは善bonumではないといった後,その直後の備考 Scholiumで憎しみを人間に対する憎しみに限定すると明言しています。これを踏まえて第四部定理四五系一では次のようにいわれています。ねたみ,嘲弄,軽蔑,怒り,復讐その他憎しみに属しあるいは憎しみから生ずる諸感情は,悪である 」。
将棋関連の書籍のレビューの6冊目は,2016年7月に講談社現代新書より発売された,観戦記者としても活躍中の大川慎太郎が書いた『不屈の棋士』です。タイトルからイメージするのは難しいかもしれませんが,トップ棋士へのインタビュー集で,そのインタビューの内容は,コンピュータの将棋に特化しています。つまり棋士がコンピュータの将棋にどのように対応しているのかを大川が質問しているということです。不安 metusあるいは恐怖metusに関しては,アルベルト Albert Burghは植え付けられてしまったのであり,この意味では被害者です。書簡七十六 でスピノザはアルベルトに厳しいことばも述べていますが,そのことは理解していたと思います。ただ,植え付けられた不安あるいは恐怖がアルベルトにとってはあまりに強大なものであったがゆえに,それはすべての人間に共有されるべき感情affectusとみなされました。第四部定理六三備考 で,この場合でいえば不安あるいは恐怖を植え付けた側の迷信家が,ほかの人びとをも不幸にしようとしているといわれているのには,このような意味も含まれていると解しておくのがいいでしょう。この結果,アルベルトは書簡六十七 をスピノザに送り付け,スピノザに対する排他的感情および排他的思想を露にしたのです。
3月31日に2016年度の将棋大賞 が発表されました。叡王戦優勝 。最優秀棋士賞は初めての受賞です。棋聖防衛 ,王位防衛 ,王座防衛 。羽生三冠は最優秀棋士賞の常連で,優秀棋士賞は2006年度 ,2012年度 ,2013年度 に続き3年ぶり4度目になります。奪取 ,A級へ再昇級。2000年度と2008年度 に受賞があり,8年ぶり3度目の受賞。朝日杯将棋オープン優勝 。将棋大賞初受賞です。2015年度 に続く連続受賞です。女流王位防衛 ,女流王座挑戦 ,奪取 ,女流王将防衛 ,倉敷藤花防衛 ,女流名人防衛 。2009年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2012年度,2013年度,2015年度に続き2年連続7回目の受賞。マイナビ女子オープン挑戦 。2012年度以来4年ぶり2度目の受賞。2007年度 と2010年度に受賞していて3度目,佐藤九段は2009年度に受賞があり2度目の受賞となります。第二部定理四九証明 の内容から,ふたつのことが理解できます。意志作用 volitioというということです。つまりスピノザの哲学でいう意志voluntasとは,精神mensをして何かを希求させたり忌避させたりするような決意のことをいうのではありません。観念が観念である限りにおいて必然的に含んでいなければならないような,何事かを肯定しまた否定する力potentiaのことが意志といわれるのです。知性 intellectusと意志 もまた同一であるいうことが帰結します。よってスピノザは第二部定理四九系 としてこのことを示しているのです。これはその証明 Demonstratioにもあるように,知性というのが個々の観念の集積であり,意志というのが個々の意志作用の集積であるということから明白だといえるでしょう。したがって,人間の精神mens humanaが自動機械 automa spiritualeであるということと,知性と意志が同一であるということは,個別の事柄を示しているようでいながら,何ら関係を有していないというわけではないことになります。
久しぶりに将棋関係の書籍を紹介します。5冊目は羽生善治の『決断力』です。スぺイク はおそらく日々の生活に追われ,スピノザの哲学的思想を詳しく知ろうとする欲求をもつ余裕がありませんでした。そしてスピノザは自身の哲学的見解を多くの人びとに伝えようとすることについて禁欲的であったと思われます。よっておそらくスピノザが自身の思想をスぺイクに対して詳しく語ることはしなかったと推定されます。そもそもスピノザはフェルトホイゼン Lambert van Velthuysenに対する反論の中で,自分の生活態度をみれば無神論者 でないことをフェルトホイゼンは理解するだろうといっています。スぺイクは実際にそれを見る立場にあったのですから,自分が無神論者ではないということをスぺイクは分かっているとスピノザは思っていたでしょう。そして実際にスぺイクはスピノザのことをそのように認識し,それによってスピノザを敬愛し尊敬もしたのだと僕は解します。要するに自分の思想が無神論に至るものではないということをスピノザはその思想を詳しく語らずとも,態度によってスぺイクに対して示すことができたのであり,スピノザにとってはそれで十分であったのだろうと僕は思います。リュカス Jean Maximilien Lucasの伝記の場合にも同様なのですが,リュカスがスピノザの生活態度がキリスト教の教えと相容れるものであったということについてはほとんど説明していないのに対して,スぺイクがそのような説明もしている理由は,取材者がコレルス Johannes Colerusであったということに起因しているのではないかと僕は思うのです。リュカスが自身の手による伝記の読者をどのような人と推定していたのかは分かりませんが,少なくともルター派の説教師であったコレルスのような,宗教色あるいはキリスト教色の強い人間だけを想定していなかったということだけは確かだと思えます。対してスぺイクは,自身で伝記を書いたのではなく,コレルスの取材に対して証言したのです。つまりスぺイクはコレルスだけを念頭に話しているのです。
竜王戦 の挑戦者変更の一件に関して,僕が何をどう判断し,また何を判断しないかについて明らかにしておきます。プラド Juan de PradoはアムステルダムAmsterdamのシナゴーグから慈善金を受け取っていました。これはプラドが経済的に困窮していたことの証といえます。一方,スピノザは,年によって金額の上下がありますが,税金を納めています。正確にいえばある時点まではスピノザの父親が納めていて,父親の死後は貿易商を継いだスピノザが支払うようになったというべきかもしれません。裕福であったとまでは確定できないまでも,暮らしていくために余裕がなかったということはあり得ないとみることができます。イエレス Jarig Jellesとかシモン・ド・フリース Simon Josten de Vriesとは,スピノザが破門される以前から友人であったと思われます。また,これはオランダ人とはいえませんが,ファン・デン・エンデン Franciscus Affinius van den Endenとも同様です。そしてファン・ローン Joanis van Loonもまた,親しく交際していたとはいえないまでも,間違いなく知り合いでした。
第29期竜王戦挑戦者決定戦三番勝負 は三浦弘行九段が丸山忠久九段を2勝1敗で降しました。しかし三浦九段は今年の7月以降の対局で終盤での離席が目立ち,指し手の決定にコンピュータの援助を受けているのではないかという疑惑が浮上。今月11日に日本将棋連盟常務会による聴取が行われました。三浦九段は援助を否定したものの,常務会は納得いく説明が得られなかったと結論。三浦九段は疑惑を受けては将棋を指せないので休場を申し出,連盟側は翌12日午後3時までに休場届の提出を要求。しかしそれが提出されなかったため,連盟は12月31日まで三浦九段に出場停止の処分を科しました。それが援助によるものなのか,離席すなわち援助を疑わせる行為によるものなのか,それとも休場届の不提出によるものなのかは判然としません。再調査は行わないそうですから,三浦九段の出方にもよりますが,処分はとりあえず最終的なものと理解しておいてよいでしょう。第25期 以来4年ぶりです。シモン・ド・フリース Simon Josten de Vriesからの資金援助を辞退しています。また,フリースの死後,フリースが遺言で命じておいたスピノザに対する年金は受け取りましたが,フリースが命じた額より減額しています。また,ハイデルベルク大学教授 への就任を打診されたとき,いわれるままに哲学正教授 の座に就いていたなら,名誉だけでなくそれなりの収入も約束された筈ですが,それも断っています。ですからスピノザは金銭に対する欲望cupiditasはさほど大きくなかったとみることができます。第三部諸感情の定義一 にみられるように,受動状態における人間の現実的本性 actualis essentiaです。ですから第三部定理五一 により,それはそのときどきに応じて変化するものであるということは考慮に入れておかなければなりません。しかしスピノザの姿勢が一貫したものであったとみる限りにおいては,年金を送るというシナゴーグサイドからの和解案にスピノザが応じなかったというのはひどく不合理な話ではないといえます。そしてそれは史実であったと僕は判断します。スピノザ 実践の哲学 Spinoza : philosophie pratique 』では,ラビたちは和解の成立を望んでいたらしいけれども,スピノザは悔悛することを拒絶し,自身の側からシナゴーグとの訣別を求めたのだとされています。ある哲学者の人生 Spinoza, A Life 』では,ユダヤ人共同体の指導者たちが,スピノザをシナゴーグに踏みとどまらせるために粘り強い説得をしなかったということは高い確率で考えられないとされています。年金はそういう手段のひとつであったと考えておくべきでしょう。
1日に2015年度の将棋大賞 が発表されました。棋聖防衛 ,王位防衛 ,王座防衛 ,王将挑戦,朝日杯将棋オープン優勝 。タイトル数を増やすことこそできなかったものの,保持していたものは完全防衛で当然の受賞。1988年度,1989年度,1992年度,1993年度,1994年度,1995年度,1996年度,1998年度,1999年度,2000年度,2001年度,2002年度,2004年度,2005年度 ,2007年度 ,2008年度 ,2009年度 ,2010年度 ,2011年度 ,2014年度 に続き2年連続21回目の最優秀棋士賞。渡辺明竜王 。竜王挑戦 ,奪取 ,棋王防衛 。実力からすると物足りない気がしないでもないのですが,羽生名人に次ぐ活躍だったのは間違いないと思います。2005年度,2008年度,2010年度,2011年度に続き4年ぶり5度目の優秀棋士賞。王座挑戦 ,棋王挑戦 ,名人挑戦。記録部門の最多対局賞,最多勝利賞,連勝賞を獲得。王座か棋王を獲得できていれば,優秀棋士賞の可能性もあったかと思います。記録部門を除くと2009年度の新人賞以来2度目の将棋大賞受賞。挑戦 ,奪取 ,女流王将挑戦 ,奪取 ,倉敷藤花挑戦 ,奪取 ,女流名人防衛 。休場からの復帰で復活の年になりました。2009年度,2010年度,2011年度,2012年度 ,2013年度 に続き2年ぶり6度目の最優秀女流棋士賞。マイナビ女子オープン挑戦 を決め,女流最多対局賞も受賞しました。将棋大賞初受賞。第二種の認識 cognitio secundi generisによって神が存在することを知ったというだけでなく,第三種の認識によって神が存在すると認識したのではないかと思えます。すなわちスピノザが第五部定理二三備考 で,知性によって理解する事柄を想起する事柄と同等に感じるといっていることの意味は,第二種の認識によって認識した事柄を,第三種の認識によっても認識するということではないかと思うのです。
1日に第42回将棋大賞 が発表されました。棋聖防衛 ,王位防衛 ,王座防衛 ,棋王挑戦 。朝日杯将棋オープン優勝 。2014年度の実績は断然で,当然の選出でしょう。現行制度になった第33回以降では,33回 ,35回 ,36回 ,37回 ,38回 ,39回 に続き3年ぶり7度目,それ以前も含めると20度目の最優秀棋士賞獲得です。竜王挑戦 ,奪取 。棋界最高峰のタイトルを獲得したのですから,これも順当といえるでしょう。優秀棋士賞は初受賞。奪取 。新たにタイトルを獲得したのが羽生名人と糸谷竜王のほかには郷田王将だけということを考えれば,これも妥当でしょうか。現行制度下では第39回以来3年ぶり2度目,通算では5度目の敢闘賞。王位リーグ紅組優勝 ,順位戦昇級,昇段。棋戦優勝はなかったのですが,受賞しておかしくない戦績であるとはいえると思います。女流王位防衛 ,倉敷藤花防衛 。一般棋戦でも2勝しています。女流棋士の中から選出されるということであれば,当然でしょう。初受賞。女流王将防衛 。一般棋戦では3勝。こちらも女流棋士の枠内での選出なら当然。ただいずれ問題化するのではないかと懸念されます。初受賞。第34回 ,35回,36回,40回 ,41回 に続き3年連続6度目,豊島将之七段は初。名局賞特別賞に新人王戦の2回戦。343手という超長手数の将棋でした。喜びの半減 という例は,ただ論理的に説明をするという目的だけのための仮定です。現実的にそうしたことが生じることはないでしょう。ただ,この論理的帰結として,現実的に存在する人間は,喜びをそして悲しみを感じるそのたびごとに,現実的本性 を変化させているということを明瞭に示していることは間違いありません。喜びや悲しみの量的変化 が起こるということは経験的事実であり,その量的変化が生じる原因は,喜びおよび悲しみを感じることによって,質的変化が生じているからだとしか説明できないからです。人が変わる 」という慣用表現が実際に,つまり真理として意味している暗黙の前提 というのは,現実的に存在する人間が,喜びを感じ悲しみを感じるごとに,その人間の精神の現実的本性 が変化するということなのだといえるのです。いい換えれば,ある喜びを感じる以前の人間と,その喜びを感じた後の人間は,たとえ同一人物であると措定できるとしても,現実的存在としては様態的に区別することが可能な別の人間であるということなのです。これが喜びを感じまた悲しみを感じるたびごとに生じるのですから,最終的な結論として導き出せるのは,様態的区別が可能な無数の同一人物が存在するということになります。スピノザの説明 を考察していく際に,放置しておいた事柄の探求は完了しました。そこでここからは,ライプニッツの世界観において,人間の行為がどのように説明され得るのかということを考えていくことにします。これを考えることによって,真偽不明というライプニッツの規定の具体的な意味も明らかにすることができます。
四冊目は加藤一二三の『羽生善治論』。2013年4月10日に角川書店より発行。僕が持っているのものには同年4月25日再販とあります。これは重版とは違って,何らかのミスを手直ししたものと思われます。第一部定義六の名目性 については,そのように把握しておけば安全であるという以上の意味はありません。別にそれが実在的にもこの定義Definitioに含まれているのだと考えたとしても,そんなに大きな過ちを犯していることにはならない筈だからです。というのも,絶対に無限な実体substantiaというのが必然的にnecessario存在しなければならないのであれば,無限に多くのinfinita属性もまた必然的に存在するのであって,個々の属性というのはこの無限に多くの属性の中からだけ抽出され得るのであり,それ以外に何らかの属性が存在するということはあり得ないからです。このこと自体は第一部定義六説明 から明白だといわなければなりません。神Deusに比重を置くならば,このゆえに神は自己の類において無限 といわれるのではなく,絶対に無限 absolute infinitumといわれなければならないのです。よって,個々の属性の第一部定義六における名目性と実在性realitasについて,僕は争うことはしません。ただ,少なくとも名目的には,無限に多くの属性が存在するということが前提されているということだけ示すことができれば,これから後の考察にとっては十分です。そしてこの点について異論が出るということはないでしょう。置き換えの可能性 は,この点に着目するのでない限り,不可能ではないかと僕は考えています。つまりライプニッツが無限に多くのモナドMonadeの実在を主張している点と,スピノザが無限に多くの属性の存在を主張している点に着目し,これを一致させるような形で,ライプニッツの形而上学をスピノザの形而上学に当て嵌めるのです。理性的区別 であると考える限り,無限に多くの実体が神という「唯一 」の実体の本性を構成すると考えて,表現上は変であっても,矛盾を来すとまではいえないと考えて構わないと僕は思います。
三冊目は島朗の『島研ノート 心の鍛え方』。2013年3月28日,講談社より刊行。僕が持っているのは翌月発行の第二刷。売れ行きが好調だったので,早々の増刷となったものでしょう。わりと早い段階で入手していたことになりますが,この本に関しては読もうか読むまいか逡巡がありました。高橋和女流三段 が強く推薦されていたのに後押しされて購入したものです。荷物 を預けておくことができなかったため,当日の朝に迎えの支援を要請しました。翌日の帰宅時にも,送りの支援を利用しました。杉田 ですので,母がボーリング場の方へ送りました。
将棋関係の書籍の紹介の第二弾は渡辺明の『頭脳勝負』。2007年11月10日、ちくま新書として発刊。僕が所有しているのは第一刷なので、発行直後に購入したものです。第19期竜王戦七番勝負第三局 は、最終盤で絶妙手を指して勝った将棋。その手を指す前後の自身の精神の動きが克明に記されています。また、相手のおそらくは無意識の呟きを、どのように解したのかも説明されています。第78期棋聖戦五番勝負第四局 は、偉大なる悪手 が指された将棋。その手が指されたときの驚きの様子、▲7五角という応手を選んだ理由、それに対する相手の雰囲気が、昼食休憩を挟んで明らかに変化したのを感じたこと、休憩後の3手目に考えていなかった手を指され、その変化の理由を理解したことなどが赤裸々に語られています。外見 を気にしないのが昔からであったかというと,そうではありません。僕は歯並びが悪いのです。いわゆる出っ歯というやつ。僕にとってこれはコンプレックスのひとつでした。少なくとも高校に入学した頃はそうでしたから,その当時は外見を気に掛けていたことになります。コンプレックスという意味ではこの当時が一番ひどく,たとえば電車の中で笑い声がしたりすると,自分の容姿が笑いの対象になっているのではないかと疑ってしまうほどでした。今から考えればそれこそ僕自身が笑ってしまうような被害妄想ですが,僕にも確かにそういう時代というのはあったのです。ショートステイ へ。南区内の施設を利用。この月のショートステイの利用が,定例よりも早まったのは,この後,母と妹の渡米が予定されていたためでした。イエスの生誕劇 と同様で、事前に説明があったからそう理解できたようです。