寛永十一年のものではないかと考える忠利公の書状が気になっている。(一部割愛)書状の相手は切支丹弾圧で名を馳せた、長崎奉行榊原飛騨守職直である。
前段二項目の切支丹に関わるところでは、「如何/\」と少々反駁めいた文章も見えて興味深い。
全体的に気鬱を思わせるような文章がつらなり、父三齋を持て余している様もみえる。
一、きりしたんせんさくの儀ニ付而思召通之御一書一段面白存候事
一、君臣・父子・夫婦・朋友之理ニ背候ものハきりしたんたるへき由九州不残きりしたんたるへく候日本之中ニ右之五りんニ相候人ハ御座有間敷候
左候ヘハ我等をはしめてきりしたんたるへく候如何/\
一、我等気色緩々と心なかく養生仕へき由御申越候ヘハ扨ハと存候はや能候ヘハ養生ハとく忘申候更とも食事も能しゝも大かたものことくかゝり申候
可御心安候更共ワかき時のことくニ心得候てハ成間敷と覚悟仕候事
一、物事静ニ緩々とおこなひ申候か當代ハよきと思召候由尤とハ存候我等なとハ生付閙 (サワガシイ)敷内の閙敷生付にて候御當代ニ相かね申候事
是非もなきと存候而一人笑申候
一、三齋儀十一月四日ニ早々ゟ熊本へ被参一日我等所にて振舞口切なと仕祝候て候秘参候何事も用も無之候つる可御心安候無残所客人ふりニて
候つる具之御書中不及返事御書中と我等存候と能相申候四月中ニ可得御意候事
一、畢竟はや五十ニあまり申候ま幾程之命も無之候無左とも人間の作法はつれ候てハいきたるかひハ更ニ無之と人毎ニ申候も尤ニて候此心さへ候
ヘハ何國之國々ニ居候ても能候作法はつれ候と我等をはしめて朝夕存候間可御心安候いけんかましき書状かゝせ候もはつかしく候間火中披成
候間(而ヵ)可被下候事
一、自筆にて可申候へとも三齋被参て亭主ふりニ草臥申候間才兵衛ニ書せ進候恐惶謹言
十一月五日
榊 飛騨様
人々御中
山本博文著「江戸城の宮廷政治」によると、この時期三齋・忠利共に熊本に在国しているのは寛永十一年である。
東大史料編纂所の『東京大学史料編纂所報』第37号(p.32-33)によると、同時期のことについて次のようにある。
忠利は、閏七月十八日、九州・中国・四国の大名とともに、家光から帰国の許可を言い渡された。同時に、この時、国元での伴天連の穿鑿強化を直接命じられている(二五〇七号)。八月一日に京を出発し、同十三日に熊本へ着いたが、帰国のその日から領内の伴天連・入満・同宿・切支丹等の穿鑿にとりかかり、「一日も隙無」(二六一三号)という多忙な日々が始まる。手始めに長崎奉行榊原職直らに対して、長崎での伴天連対策を尋ね、それまで行っていた下々からの宗門の書物取り以外に方法がないか探っている。そうする内に、領内の豊後や肥後から伴天連捕縛等の情報が寄せられ始め、伴天連に宿を貸した者の穿鑿も開始された。忠利は、長崎奉行・豊後府内目付や、島津氏・有馬氏(延岡)・稲葉氏(臼杵)氏等の隣接する大名等と連絡を取り合いながら、個々の伴天連摘発に対応している(二六〇二号等多数)。その中で、忠利は切支丹改めは一朝一夕に完了できるものではなく、踏絵の改め等により転んだとしても、「七度ハ成帰り候へとの」教えが「南蛮」より信者に対して出ているとの認識を示し、「とだへなく連々ニ切支丹たやし」続けるより他はないと進言している(二六一四・二六三九・二六四九号等)。
十月に入ると、江戸城普請についての情報が流れ始め、十一月九日付の幕府年寄奉書(十一月晦日熊本着)により、正式に、翌々年の江戸城普請が命じられた。細川氏は石垣普請の担当とされているが、すでに十月段階から普請道具や石場の準備等に取りかかり、金策のことも心配し始めている(二六四七・二七三四号等)。さらに、家光の本心は翌々年よりも、翌年に普請を行いたいのではないかと忖度し、幕府の普請奉行たちに対して来年七月八月からの普請開始を内々申し入れてもいる(二七三五・二七三六号)。
十一月十八日付で山城長岡藩主永井直清に出した書状(二六九六号)の内容は、忠利の幕府に対する意見の上申事績として早くから注目され、『綿考輯録』においても特記されているものである。最近では『部分御旧記』所載の同書状を、吉村豊雄氏が「意見状」として紹介、とくに参勤交代制度化との関係を中心に検討している(「参勤交代の制度化についての一考察ー寛永武家諸法度と細川氏ー」熊本大学文学部『文学部論叢第二九号』一九八九年)。
これ以外にもこの年後半は、様々な事件(家臣借銀に関しての大坂商人から公儀への訴訟、家臣一族の者の寛永寺境内での騒動等々)が頻発し、忠利は一つずつ処理している。そして、次の参勤が年明け以降となったことを喜び、江戸の光尚の疱瘡が思いの外軽かったことに安堵しながら、この年の暮れを迎えている。














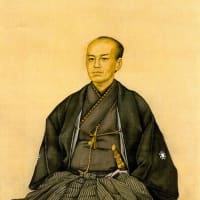
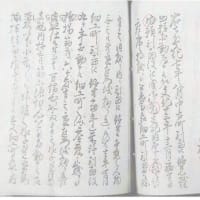
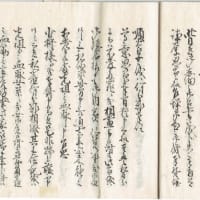
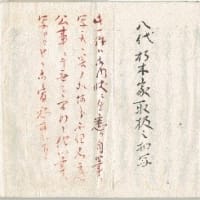







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます