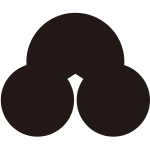鬱憤や声をあらぐる 大暑かな 津々
脳梗塞を起こしてからの妻には、思いがけない変化が出てきて驚かされる。
カレーの皿をスプーンでカチャカチャ音を立てて食べるようになった。思わず「うるさい」と怒鳴ってしまう。
みそ汁の出汁の「袋」を破ってしまって、お椀の底にはそれらが異物のようにたまっている。「なにやってんだよ・・」
かっては愛用のiPadをひらいては、料理のレシピなどをみていろんな料理を出してくれたいたが、オリジナルの料理が作れなくなり、近くのスーパーから出来立ての総菜をかって盛り合わせるというのが毎度のこととなった。
iPadは全く開かなくなり、いろんな買い物をしていたがこれがすっかり止んでしまった。
眼も悪くなっていて、レトルトなどの説明書が読めないと一々声を掛けてくる。鬱陶しいことこの上ない。
いろんなことがかさなって、まずいとは思いながら少々声を荒げてしまう。「ごめんね・・」と返されると反省しきりである。
失語症もあって会話が成り立たず、本人もいらいらがあるのだろうから、こちらも余り声を荒げないように心掛けなければならない。
今日は大暑それにしても熱い・・後2ヶ月ばかり我慢しなければならないかと思うと、欝憤も大いにたまるというものだ。