「やわ肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君」
(みだれ髪:与謝野晶子 明治34・1901年)
これは女の歌だから良いが、男がこんな歌を詠めば色きちがいか、セクハラと言われる。今なら「きも~」昭和30年代なら「お下劣」
男の返歌のような歌に、
「熱き血潮の冷えぬ間に~いざ燃ゆる頬を君が頬に~君が柔手をわが肩に」(ゴンドラの唄:吉井勇 大正4・1915年)
・・・があるが、晶子によって慣らされていた言葉だから、すんなり受け入れられたのだろう。
なぜ男ならダメかと言えば、男は元来こういう言動をとるものと知られているからだ。
女の晶子が、男と同じ立場で詠んだことが新鮮で、インパクトがあったので、その後の女性解放運動などより、よほど突き抜けている。
この歌が出た当時は当然、破廉恥論争が起こったが、それは公、立て前の世界だからだ。晶子には学問以前の日本の女が生きていた。
農耕母系が底辺に流れる日本文化では、本来、女の主権は強く、開放的であり、男は看板に過ぎなかった。女が弱者であるという一方的見方は、欧米の認識が前提になった輸入学問だ。
漢学も男尊女卑であり、歴史の表は男系で一貫しているが、
ごく、近年まで「夜ばい」が存在した日本の男と女の関係は、本質的には女上位で、女が奴隷労働していたと言うより、女が家を支え、男を養っている「ライオン社会」と考える必要があるし、そう考える方がわかりやすい。
「足入れ」婚を女性蔑視の象徴とするが、それを実際に行ったのは、実権を握る女の「姑」であり、小家族制の価値観だけで考えれば人間の本質を見誤り、とんちんかんな「男」悪人説に陥ってしまう。
そして、人間、男女はどうあるべきかを考えることも出来なくなる。











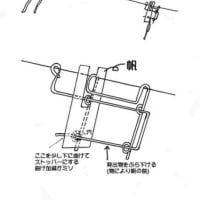






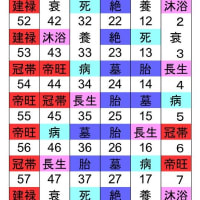
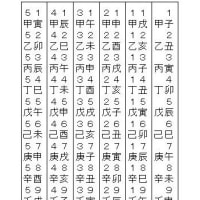
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます