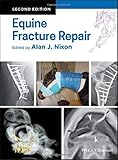センスがない。ある。
よく言われることなのだが、センスとは何か?
たぶん、知識や技術以外のもので必要なものを言うのだろう。
そして、経験によるものであれば経験のおかげだと考えられるが、
年数を重ねても的外れなことをしていると、それもまたセンスがない、ということになる。
では、どうすれば身につくのか?
ー
しばらく手元において読んで、読み返した。
マンガとストーリー仕立てでヒト外科技術の実践的側面について書かれていて読みやすい。
馬外科医に役に立つか・・・・まあまあ。
センスが身につくか?・・・・ほとんどつかない;笑
ー
「傷は縫うから治るのではない」
外科学の基本は勉強しておいて、の話。だけど何でもそのまま縫えば良いというものではない。
当たり前と言えば当たり前。
ー
「切り口に術者の心が表われる」
たしかに、メスでの切開には外科医のセンスが表われるかもしれない。
馬の開腹手術創では・・・
これが、できるかどうかは、やっぱり経験かな。
そもそも、23番ブレードは”腹”で切るんだ、というのは基礎知識かな。
長年やっていてもヘタなのは、センスがないんだろうな。
ー
「すべての手術はアテローマ」
名医の粉瘤オペのマンガ。笑える;笑
ー
「局麻手術はきくばり手術」
局麻うつのにブスブス針を刺す獣医師が居て、注意したことがある。
でも、そういうヤツは注意してもやめないんだよね。
自分の指に針を刺した経験から考えればわかるだろうに。
馬を枠場に入れて、痛いことをして、馬が飛び出しそうになることもある。
それも馬医者としてのセンス。
その馬がおびえてないか?馬が暴れ出したらどうするか?周りは動けるヤツか?
それを観ながら麻酔方法や鎮静状況や手術敢行可能か、判断できるのが・・・センス?経験かな?
ー
「手術器具は柔らかく持つ --脇は締めるべきか?」
これは実技指導に行くと私も言うことがある。
ただ、リラックスした姿勢で、縫合部に目(顔あるいは頭)を近づけずに縫えるかどうかは、手指の感覚で持針器と縫合針を扱えるか、にかかっているのかもしれない。
針がどこに出てくるかわからないから目をこらして見てしまう。
あまり姿勢ばかりうるさく言っても仕方がない。
結局は技術であり、経験あるいは練習で身につけるしかないと思う。
いつまでもタカアシガニだったら・・・・センスがないか・・・・眼鏡を変えた方が良い。
ー
「一寸の針糸にも十分の魂」
”これからの外科医には、材料や糸のコスト意識が求められる”
と書いてあってちょっと安心した;笑
私たちが使っている縫合糸もそれなりに高い。
縫合が上手になるほど無駄に切り落とす末端が短くなる。
糸を無駄にしない縫合もできないなら高い糸を使う資格はない。結局無駄だから。
左手を上手に使えないから、あなたの糸の末端は長すぎるんだよ。
雑巾縫って練習しな。
ー
「感染したら迷わず切開排膿、抗菌薬でお茶を濁さない」
ペットによる咬傷の寓話として出てくるのだが、”膿が溜まっている状態に薬を使っても、焼け石に水だよ”
知っている、のだろうが、やっている獣医師の多いこと。
子宮穿孔・腹膜炎でもそうだろうと、私は思う。
ー
この本は形成外科のお医者さんが書いていて、だから皮膚弁とか、皮膚移植とかに詳しい。
一方、”腫れならいいね、折れたらやだね” だし、
「骨の手術」では、”シンプルだ。折れていたら、元に戻して固定すればよい。” とある。
まあ、ヒトはおとなしくベッドで寝ていてくれるからね。
馬医者にはまたちがったセンスが必要。
ー
「ベテランが手術を独占しては、医療が停滞する」
「先人は伝授を惜しまず、後人は先人を追い越す努力を」
”技術は盗むものでも、背中で伝えるものでもない。”
”大概の、いや全ての手術はちゃんと指導すればそう難しくはない。そうでなければ医療とは言えない”
手術は芸術か芸能か。
百年にひとりの天才が担うべきか、ひろく普及してひろく恩恵が享受されるべきものか。
ヒト医療の需要のひろさがうらやましい気もする。
優秀だとされた獣医さんが居なくなったあとに廃れてしまう地域や組織もある。
本当に優秀な人だったら、その人が居なくなったあとも隆盛が続き、さらに発展するはずだ。
ー
ー
つまるところセンスとは意識。
教わったことや教科書を鵜呑みにせず、自分で考えながらやることで、センス”意識”は磨かれる。
そういった意識は、上手になろう、良い診療をしようという意欲に支えられている。
センスがないヤツのひとつの多いパターンは、「この程度でイイんだ」と開き直っているヤツかな。
/////////

キミに飼い犬としてのセンスはあるか?!



















![義男の空 コミックセット[マーケットプレイスセット]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51l6%2BMGL8aL._SL160_.jpg)