土曜日の朝日新聞朝刊には「be」という別刷りが折り込まれています。昨日の「be」には俳人・高浜虚子に関する宗教学者・山折哲雄さんのエッセイが載っていました。
虚子が鎌倉に住んでいたある時、由比ガ浜に赤潮が発生したと聞き、飼っていた犬を連れて見に行きます。すると海岸に集まっていた人だかりの中から一匹の犬が躍り出て、虚子の犬を脅し、海の中に追い立てました。虚子は持っていたステッキで攻撃を仕掛けてきた犬を追い払おうとしますが、その様子を人々が笑って見物していることに気づきます。
虚子の筆はそのさまを次のように描いています。「ふと気がつきますと、海岸に長く陣を敷いたやうに立つてをる群衆が、皆一せいに私の方を見て笑つてゐるのでありました。犬二匹と私のほかは何物もない、たゞ赤潮がひたひたと波打つてをる海中にあつて、運動神経の鈍い私が、杖を振り上げて一匹の犬と格闘してをつたのが、人々の良い観せ物になつてをつたといふことを知つて、俄に恥づかしいやうな心持がいたしました。」
そこで虚子は「穴があったら入りたい」ような気持になったでしょうか? 然に非ず、虚子の先の文章は「しかし私はそのことについて後悔はしませんでした」と続きます。そこで、山折さんは虚子晩年の句、「去年今年貫く棒の如きもの」を引いて、虚子の惑わされぬ強い気持ちを「棒の如きもの」に例えています。
さて、鎌倉・由比ガ浜と言えば、鎌倉時代に武士たちが活躍した舞台であります。司馬遼太郎さんは鎌倉武士の倫理観を「名こそ惜しけれ」の精神と呼んでいたように思います。「名を惜しむ」とは、つまりルース・ベネディクトの「恥の文化」のことでしょうが、単に人の目を気にする、笑いものにならないようにするといったものではなく、道義的なものやレーゾンデートルに照らして恥ずかしいことはしない、そのように司馬さんは見ていたと思います。時代も違い、松山出身の虚子は鎌倉武士の末裔でもありませんが、虚子における「棒の如きもの」は司馬さんの「名こそ惜しけれ」に通ずるものがあると考えてみたくなりました。
虚子が鎌倉に住んでいたある時、由比ガ浜に赤潮が発生したと聞き、飼っていた犬を連れて見に行きます。すると海岸に集まっていた人だかりの中から一匹の犬が躍り出て、虚子の犬を脅し、海の中に追い立てました。虚子は持っていたステッキで攻撃を仕掛けてきた犬を追い払おうとしますが、その様子を人々が笑って見物していることに気づきます。
虚子の筆はそのさまを次のように描いています。「ふと気がつきますと、海岸に長く陣を敷いたやうに立つてをる群衆が、皆一せいに私の方を見て笑つてゐるのでありました。犬二匹と私のほかは何物もない、たゞ赤潮がひたひたと波打つてをる海中にあつて、運動神経の鈍い私が、杖を振り上げて一匹の犬と格闘してをつたのが、人々の良い観せ物になつてをつたといふことを知つて、俄に恥づかしいやうな心持がいたしました。」
そこで虚子は「穴があったら入りたい」ような気持になったでしょうか? 然に非ず、虚子の先の文章は「しかし私はそのことについて後悔はしませんでした」と続きます。そこで、山折さんは虚子晩年の句、「去年今年貫く棒の如きもの」を引いて、虚子の惑わされぬ強い気持ちを「棒の如きもの」に例えています。
さて、鎌倉・由比ガ浜と言えば、鎌倉時代に武士たちが活躍した舞台であります。司馬遼太郎さんは鎌倉武士の倫理観を「名こそ惜しけれ」の精神と呼んでいたように思います。「名を惜しむ」とは、つまりルース・ベネディクトの「恥の文化」のことでしょうが、単に人の目を気にする、笑いものにならないようにするといったものではなく、道義的なものやレーゾンデートルに照らして恥ずかしいことはしない、そのように司馬さんは見ていたと思います。時代も違い、松山出身の虚子は鎌倉武士の末裔でもありませんが、虚子における「棒の如きもの」は司馬さんの「名こそ惜しけれ」に通ずるものがあると考えてみたくなりました。
















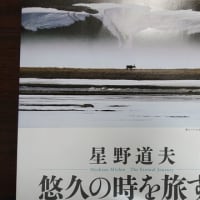



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます