大英博物館のニール・マクレガー館長は博物館の所蔵品から100の展示品を選び、そのひとつひとつに関する歴史研究の成果を踏まえながら、モノを通じて見えてくる歴史 ―その時代で担った役割や、その後の人類の歩みに与えた影響― を、「100のモノが語る世界の歴史」(筑摩選書)として著書にしています。100あるモノのうち38番目に紹介されているのは、西暦100~500年頃、メキシコあたりでスポーツ競技に際する儀式で使われていた石製のベルトです。スポーツ競技とはゴムのボールを腰や尻で撥ね返しながら相手の陣地に入れる球技で、石のベルトでは素早く動くことが出来ないことから、また、石のベルトに彫られたヒキガエルが幻覚を招く物質を分泌することや、大地の女神と考えられていたことから、儀式的に使われていたのではないかと推測されています。
今を遡る1500年以上も前に行われていた球技に対して、著者はこう述べます。「団体競技には歴史を通して驚くべき特徴が見られる。その一つが、文化的差異や社会的区分をだけでなく、政治不安ですら超越する潜在能力だ。聖と俗のあいだの境界線を超えて、スポーツは社会を見事に統一もするし、分裂もさせる。現代社会でわれわれが一丸となって関心を寄せる対象は、ほかにはほとんどない。このメキシコの儀式用ベルトは、どんな社会もいかに組織的な団体スポーツを楽しみうるのかを表す強力なシンボルとなっている。」
つい、先日まで世界中の人びとの関心を集めていたロンドン五輪も、まさしく「われわれが一丸となって関心を寄せる対象」でした。しかしながら、私たちははるか昔のメキシコの人間のままではありません。スポーツが「社会を見事に統一」することは善しとしても、「分裂」につながるものであってはならないことを知っています。「健闘を讃え合う」と言いますが、高い水準で全力を出し切る試合を見れば、勝者も天晴れながら、敗者もまた天晴れです。敗れはしても勝者に肉薄する力量を持つ選手には、勝者に匹敵する尊敬の念が生まれます。その意味では、五輪の場は各国の選手全体を讃え合う機会になったかと思います。そもそも、スポーツはたった一人では成り立ちません。同じ土俵で競い合う相手の存在を前提としています。それは、競り合える相手がなければ、観衆に、そしてもちろん競技者自身にも感動が生まれないからです。
今を遡る1500年以上も前に行われていた球技に対して、著者はこう述べます。「団体競技には歴史を通して驚くべき特徴が見られる。その一つが、文化的差異や社会的区分をだけでなく、政治不安ですら超越する潜在能力だ。聖と俗のあいだの境界線を超えて、スポーツは社会を見事に統一もするし、分裂もさせる。現代社会でわれわれが一丸となって関心を寄せる対象は、ほかにはほとんどない。このメキシコの儀式用ベルトは、どんな社会もいかに組織的な団体スポーツを楽しみうるのかを表す強力なシンボルとなっている。」
つい、先日まで世界中の人びとの関心を集めていたロンドン五輪も、まさしく「われわれが一丸となって関心を寄せる対象」でした。しかしながら、私たちははるか昔のメキシコの人間のままではありません。スポーツが「社会を見事に統一」することは善しとしても、「分裂」につながるものであってはならないことを知っています。「健闘を讃え合う」と言いますが、高い水準で全力を出し切る試合を見れば、勝者も天晴れながら、敗者もまた天晴れです。敗れはしても勝者に肉薄する力量を持つ選手には、勝者に匹敵する尊敬の念が生まれます。その意味では、五輪の場は各国の選手全体を讃え合う機会になったかと思います。そもそも、スポーツはたった一人では成り立ちません。同じ土俵で競い合う相手の存在を前提としています。それは、競り合える相手がなければ、観衆に、そしてもちろん競技者自身にも感動が生まれないからです。
















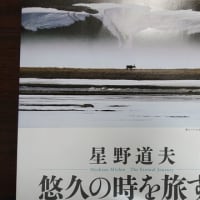



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます