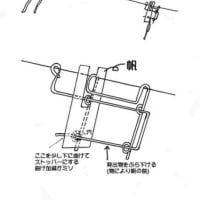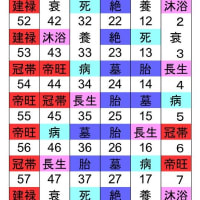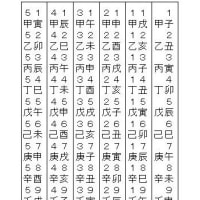「さんま御殿」で、若者言葉について、「語んなし(=語るな)」と言う表現が一般化していると、若手が披露していた。
言葉のニュアンスはすぐ解ったし、その語源のプロセスもすぐ想像できた。
6年前2007年に、東西文化「し」で書いたように、「し」は元々、京都弁だ。それがお笑いの関西弁の広がりに乗って、原型とは関係ない形で一人歩きしたのだろう。
それでも、「語るな」の、否定の「な」に付く「し」は、京都弁の原型のニュアンスを止めているから面白い。
京都弁の「し」は、「男もいるし、女もいる」のような、多重姓を含ませる接続詞の「し」で終わらせることで、言質を取られないように断定を避け、どうにでも展開できるようにした、いわゆる日本語の智恵の原点であり、その発展形だ。
一つの言葉を多重的にボカす言い方が、実際には、相手の言葉を否定する時に多く使われることで、拒否や否定のニュアンスになる。
(少なくとも、桂小枝はそのニュアンスのギャグにしていた)
「そんなんゆうても、うちも、もう大人やし」
「そろそろ時間やし」
多くは、相手の意思をさえぎる時に使われるか、無自覚な拒否感がある場合だ。
京都弁の婉曲な拒否感が、「し」と供に伝わり、否定語の修辞のように使われ始めたのだろう。
「語んな」より、「語んなし」の方が、小さなクッションになり、ソフトになる。
ここには、京都弁の姿は無いように見えるが、思わぬ形で生まれ変わっている。